こんにちは!
陣内です。
久しぶりのブログの更新になります。
目次
— 背部緊張亢進症例への刺鍼介入 —
背部に生じる慢性緊張は、運動不足・デスクワーク姿勢・呼吸不全・心理ストレスなど複数要素が絡む“難治領域”です。
軽擦・押圧・表層鍼だけでは改善が一時的に留まり、再発性が高いケースも多いでしょう。
本記事では、動画で紹介された盤龍刺をベースに、
✔解剖学的狙い
✔深層筋アプローチの意義
✔安全性の確保
まで体系的に整理します。
◆ 盤龍刺とは:脊柱起立筋群への連続刺鍼
鍼を脊柱に沿って連続配置し、深層筋を面的に捉える刺鍼法です。
龍が背を這うようなラインになることから“盤龍”と名付けられています。
対象筋の主軸
- 脊柱起立筋(最長筋・腸肋筋)
- 多裂筋(椎骨間の重要安定筋)
臨床的ターゲット
- 胸椎T3–T7付近の呼吸補助筋+交感神経節レベル
- 肩甲骨内縁筋の緊張波及領域
深層でトリガーポイント化しやすい箇所に一致します。
◆ 深層筋を狙う意義:筋×自律神経への同時介入
背部緊張が強いケースは…
✅ 呼吸運動の低下
✅ 交感神経緊張の慢性化
✅ 防御反応による後鎖線の過緊張
これらが 悪循環を形成しています。
鍼は電気刺激と併用することで…
- 筋紡錘の再調整
- 浅深層の血流差解消
- 交感神経興奮の沈静化
を期待できます。
臨床的には
「筋機能改善 → 呼吸改善 → 情動緩和」
という順の変化が多い印象です。
◆ 手技の流れ(臨床ポイント付き)
| ステップ | 目的 | 技術ポイント |
|---|---|---|
| 触診 | 緊張ラインの同定 | 棘突起両側の圧痛・陥凹消失を確認 |
| 刺入 | 深層筋狙い | 斜刺〜横刺、棘突起寄りに浅く入れすぎない |
| 回旋進入 | 深度調整 | 患者の表情反応を確認しつつ響きをコントロール |
| 連続刺鍼 | 面で捉える | T3〜T9の7〜10本が汎用 |
| 低周波通電 | 筋ポンピング | 周波数:1〜5Hzの低頻度が適応 |
| 置鍼後抜鍼 | 自律神経調整 | 施術後の過度な刺激回避 |
✅ 臨床的には 片側→症状強側からの刺激量調整が望ましいです。
◆ 症状別応用例(術者向け)
| 主訴 | 重点レベル | 刺鍼の工夫 |
|---|---|---|
| 反り腰+背部痛 | T11–L2 | 腸肋筋外側まで含める |
| ストレス・不眠 | T5–T7 | 交感神経節レベルを重点 |
| 肩甲間部痛 | T3–T6 | 肩甲骨内縁へ響かせる |
| 呼吸が浅い | T3–T4 | 呼吸同調で低周波流す |
症状像に応じてどの高さを軸にするかが結果を大きく左右します。
◆ リスクマネジメント:特に胸椎部深鍼の注意
背部は“安全と思われがち”ですが、誤刺リスクがあります。
特に注意すべきポイント
- 肩甲骨内縁部は肺尖に近接
- 瘦せ型・女性は肋骨弧が鋭い
- 呼吸介入中は深度変化が大きい
- 通電刺激により筋収縮で深度変動が起こる
→ 棘突起との位置関係を常に意識
→ 深い縦刺は禁忌/斜刺で安全域を確保
安全性は臨床家の責任です。
◆ 通電刺激の意義:動画実演要点
動画では鍼通電が併用されていました。
盤龍刺×低周波は相性が良く、以下が期待できます。
- 筋緊張の能動的弛緩
- 疲労物質循環の促進
- 伸張反射の再学習
周波数は 1–5Hzが基本。
過刺激は交感神経反応を高めるため、
患者の呼吸と脈を観察し調整が必須です。

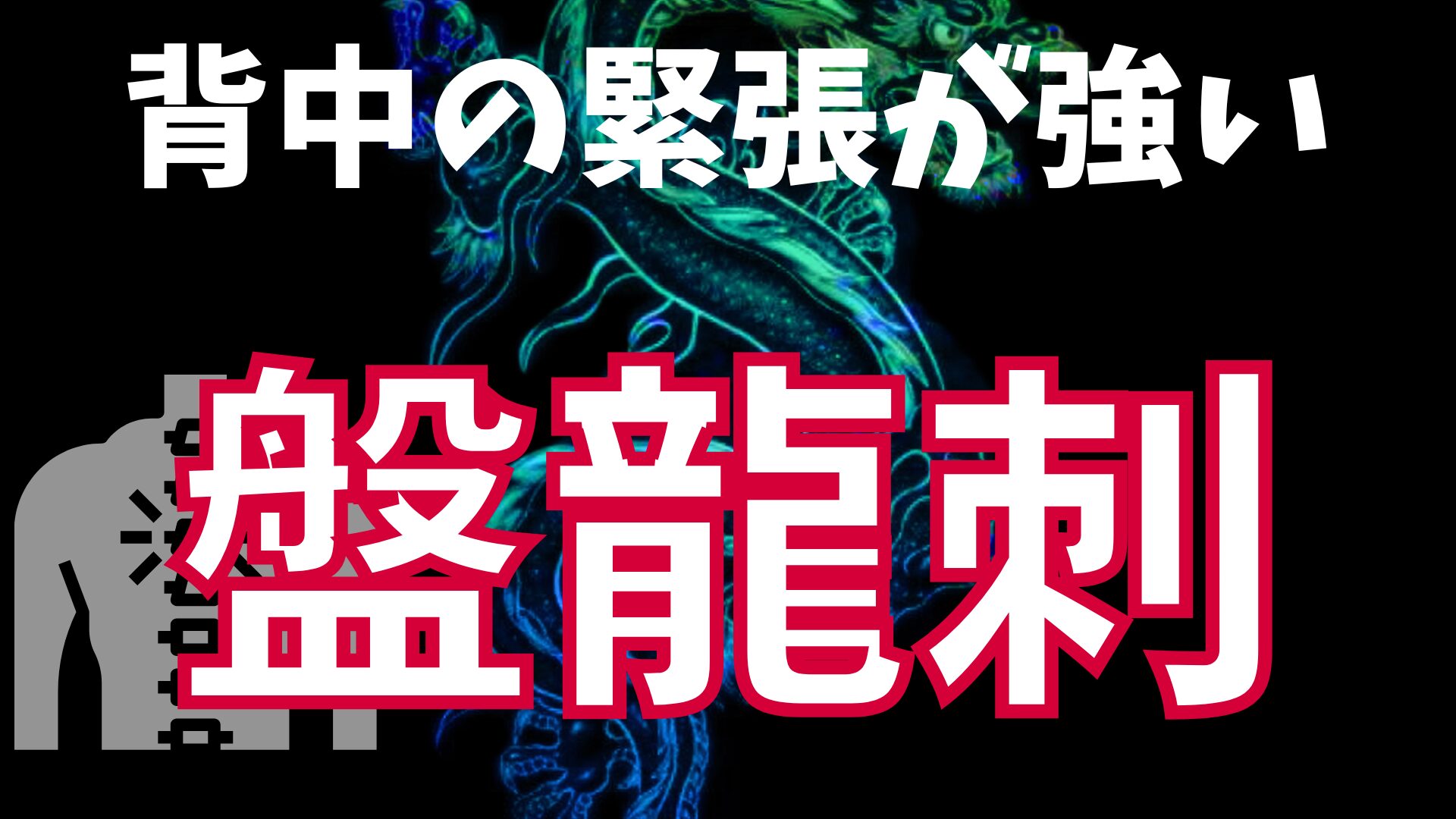
コメント