こんにちは!
陣内です。
今回も論文をご紹介していきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
最近発表された興味深い論文「The Prophylactic Effect of Acupuncture for Migraine Without Aura: A Randomized, Sham‑Controlled, Clinical Trial(2025年)(PubMed)についてご紹介していきたいと思います。
はじめに:なぜこの研究が注目されるのか
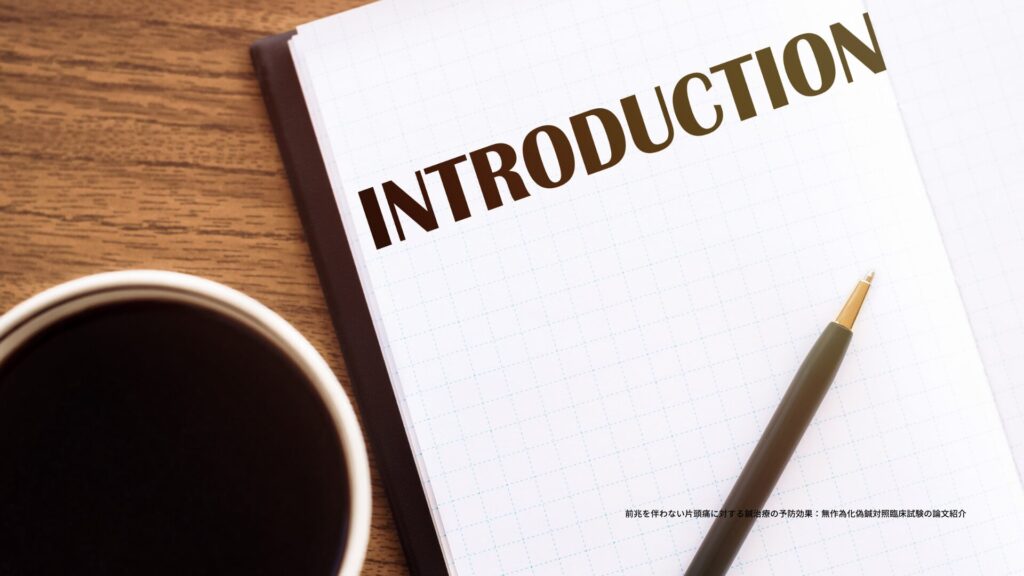
まずこの論文の背景からみていくと片頭痛(特に「前兆なし」のタイプ=Migraine without aura)は多くの方が悩まれており、再発予防が重要なテーマです。論文の冒頭では、「鍼治療は片頭痛において有効と認められているが、同一の経穴(ツボ)を使用しても手技がその長期効果にどう影響するかは明らかでない」という問題意識が示されています。(PubMed)
鍼灸師としては「ツボを選んだらそれで終わり」というわけではなく、「どのように刺入し、どのような手技操作をするか」が結果に影響する可能性がある、という点に大きな臨床的意義があります。
この論文は、「穿刺する鍼(manual penetrating acupuncture:MPA)対 非穿刺あるいは模倣鍼(non-penetrating acupuncture:NPA/シャム鍼)を、同じ経穴を用いて比較」するというデザインをとっています。(PubMed)
つまり、ツボの“場所”は同じでも、「刺すか刺さないか」、あるいは「本物の鍼刺激かどうか」が予防効果にどう関わるかを検証したという点が特徴です。
鍼灸師として、日々の臨床で「どこを刺すか」以上に「どう刺すか」「どれくらいの刺激を入れるか」「持続効果を出せるか」という点を考えるうえで示唆になる研究です。
刺激に関して考えるのはとても重要です。
研究の設計(方法)を押さえましょう

では、この研究がどのようにデザインされたかを整理しておきましょう。
- 多施設、ランダム化、シングルブラインド(被験者はどちらの群か分からない)という設計。(PubMed)
- 対象:前兆なし片頭痛(International Classification of Headache Disorders 3rd edition基準)をもつ患者さん。(PubMed)
- 被験者数:192名が1:1で割り付けられ、各群99名。(PubMed)
- 介入:12回の鍼治療を実施(詳細な頻度・期間は論文に記載)。群A=MPA(刺鍼群)、群B=NPA(シャム鍼)を同じ経穴で。(PubMed)
- 主なアウトカム:介入前ベースラインから16週目時点での「片頭痛発作頻度の変化」。副次アウトカムとして、発作回数、発作日数、痛みの強度、4週ごと評価など。(PubMed)
- フォローアップ期間もあり、治療終了後に持続効果や生活の質(QOL)の変化も検証されています。(PubMed)
- 安全性(有害事象)も報告されており、MPA群では5.1%に有害事象あり。(PubMed)
このように、鍼灸治療の予防的役割を真正・シャム対照で比較した設計という点で、信頼性が高めです。鍼灸師として「刺入あり/なし」でどこまで変わるか」という議論を、エビデンス的に吟味できる貴重なデータと言えます。
結果:なにがわかったか

さて、結果を整理します。
主な結果
- 16週時点で、MPA群はNPA群に比べて片頭痛発作の頻度がより大きく減少しましたが、その差は統計学的な「明確な有意差」には達しませんでした(平均差=-0.6回、95%CI:-1.5~0.05、p=0.069) (PubMed)
- ただし、「レスポンダー率(例えば発作が○回以下になった/○%以上減少したなど)」では、MPA群が有意に優れていました(リスク差=17.2%、95%CI:5.2~29.1、p=0.007) (PubMed)
- 痛みの強さ(痛みスコア)も、MPA群がNPA群より優れていました(平均差=-0.6、95%CI:-1.1~-0.2、p=0.003) (PubMed)
- フォローアップ時点では、MPA群は発作頻度・日数・痛み・生活の質の改善をNPA群に比べて持続的に示しました。 (PubMed)
- 安全性については大きな問題なし。有害事象率5.1%(MPA群)。 (PubMed)
解釈
つまり、「刺入ありの鍼治療(MPA)は、刺入なし・シャム鍼(NPA)に比べて、痛みの強さや生活の質の改善、応答される患者の割合という面では明らかに優れていた」ということです。一方で、発作頻度そのものの「差」が統計学的有意レベルに届かなかった(p=0.069)という点は、「無刺刺鍼もある程度効果をもたらした可能性/サンプル数・効果量がもう少し大きければ差が出た可能性がある」という解釈がされます。
そのため、論文では「刺入鍼(MPA)とシャム鍼(NPA)は予防効果としては大きく差が出なかったが、刺入鍼のほうが症状緩和・生活の質改善・長期持続性という点で優れていた」と結論しています。(PubMed)
鍼灸師として知っておきたい「臨床への示唆」

ここからは、「鍼灸師の立場でこの論文から学べること」「臨床に活かせる視点」を整理します。
1. ツボ選びだけで安心してはいけない
多くの臨床では「どこを刺すか(経穴選択)」が中心になりがちですが、この研究は「どこを刺すか」よりも「どう刺すか/刺すか刺さないか」が長期効果に影響する可能性を示しています。
つまり、同じ経穴を選んでも、刺入を伴う鍼(MPA)とシャム鍼(NPA)では、結果に差が出るということです。刺入鍼のほうが、痛みの軽減・QOL改善・長期維持で優れていました。
鍼灸師として日常臨床を振り返ると、「この患者さんにはどんな刺入操作をしたか」「鍼の深さ・鍼の操作(捻転・引き抜き)・通電や手技の有無」などを改めて見直すヒントになります。
2. 長期フォローアップの重要性
この研究では、介入終了後もフォローアップ期間を設け、持続効果を確認しています。鍼灸の臨床でも「治療直後に症状が軽くなった」だけで満足せず、「1ヶ月後・3ヶ月後にもどれだけ持続しているか」「日常生活・QOLにどう影響しているか」を意識することが大切です。
この研究で刺入鍼のほうが持続性・QOL改善に優れていたという点は、鍼灸師として「継続的なケア・フォローアップ」の設計を考えるうえで貴重な示唆です。
3. モデルとして使える「レスポンダー率」の概念
臨床現場で「何回鍼治療したらどれくらい症状が改善するか」「このくらいの割合の患者に効果が出やすいか」を把握することは有益です。本研究ではレスポンダー率(発作頻度があらかじめ設定した基準以上減った人の割合)で刺入鍼群が有意に優れていました。これは「ただ平均値が減ったかどうか」以上に、「どれくらいの患者が臨床的に意味ある改善を得たか」という視点を与えてくれます。
鍼灸師としては、治療計画・説明時に「このくらいの頻度・回数でレスポンダーになりやすい」という見通しを、エビデンスをもとに提示できると、患者さんの信頼・納得度が上がります。
4. 刺入を伴う鍼の“質”を意識する
「刺入鍼だから自動的に良い」というわけではありませんが、本研究のように刺入を伴う手技が予防的効果・生活の質改善で優れていたという結果は、鍼灸師として鍼の“質”を意識する動機になります。例えば:
- 鍼の深さ・角度・刺入部位の組織(筋・筋膜・神経近傍など)
- 鍼を入れた後の操作(捻転・提挙・置鍼時間)
- 患者さんの反応(得気/軽い絡み感/響き)や安全管理
- 継続治療デザイン(どのくらいの頻度・サイクルで施術するか)
などをあらためて検討することで、鍼治療の効果をより引き出せる可能性があります。
5. 患者説明・インフォームドコンセントにも活用できる
鍼灸師として患者さんに「なぜ鍼を行うのか」「どんな効果が期待できるのか」「どれくらい続ける必要があるのか」を伝える場面があります。本研究を参照しながら、「片頭痛の再発予防という観点で、刺入鍼にはシャム鍼よりメリットが出たというデータがあります」という説明ができます。ただし「発作頻度そのものの差では統計学的有意差が出なかった」という留保も含めて、過度な期待を持たせずに説明することが重要です。
6. 限界も理解しておく
どんな研究にも限界がありますので、臨床応用する際にはこの点も鍼灸師自身が踏まえておくべきです。たとえば:
- 発作頻度の主解析で有意差に届かなかった(p=0.069)こと。
- 被験者が「鍼治療未経験者(鍼灸初心者)」が対象であった可能性など。
- 鍼の手技・治療回数・期間などが臨床現場と異なる可能性。
- 無刺入シャム鍼も一定の効果を示しており、鍼治療=劇的効果、という単純化は避けるべき。
- 「適切な経穴・鍼刺激・継続治療」が前提であり、鍼灸治療そのものの“好き勝手な実施”で同じ効果が出るとは限らない。
このように限界を理解しつつ、「刺入を伴う鍼治療が予防的観点で有用な可能性がある」という方向性を鍼灸師として臨床に活かしていくことが現実的です。
まとめ:臨床での活用に向けて
今回ご紹介した論文は、鍼灸師として刺入の有無という手技の側面から片頭痛予防に対する鍼治療の可能性を改めて示してくれたものです。ツボを選んだだけでなく、「どう刺すか」「どれくらい続けるか」「どのようにフォローアップするか」という手技・治療設計の重要性を改めて考えさせてくれます。
特に以下の点を臨床で意識いただくと、お役立ていただけるかと思います。
- 刺入鍼(MPA)を主体にした鍼治療プログラムを設計する。
- 初期段階から計画的に継続・維持期を設ける。
- 患者さんへエビデンスに基づいた説明を行う。
- 治療効果を定量的にモニタリングする。
- 鍼治療に加えて、生活習慣・セルフケア指導も併用して再発予防力を高める。
とはいえ、「発作頻度そのもの」で明確な統計学的優位差が出なかった」という点などからも過度な期待は禁物です。「鍼が万能」というわけではありません。しかし、前兆なし片頭痛の予防という観点では、鍼灸師が提供できる価値が十分にあることも示唆されています。

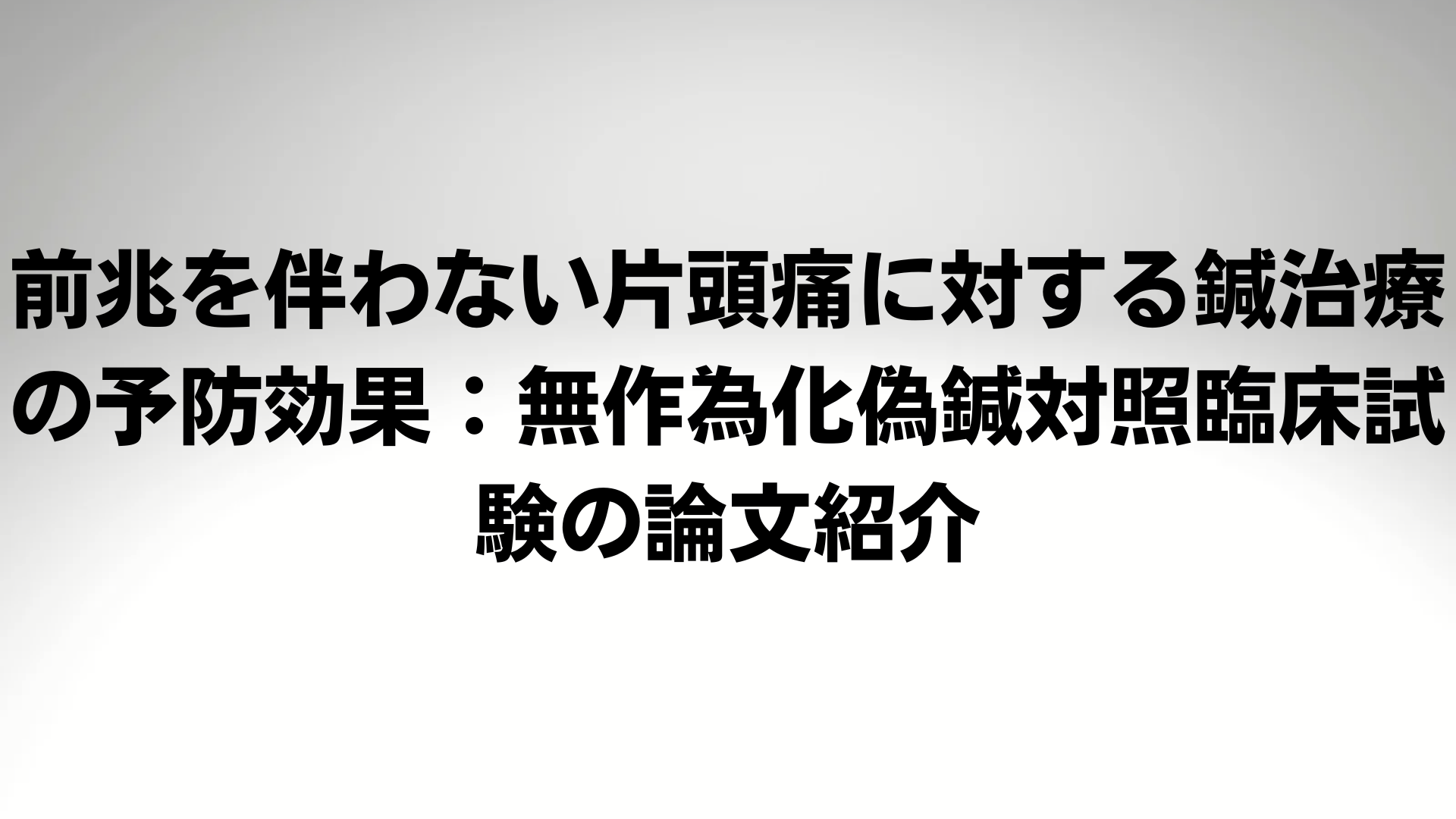
コメント