※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
参考文献はこちら
あくまで私の私見も入っていますので全てを鵜吞みにしないようにしてくださいね‼
はじめに
臨床で鍼通電を使われている先生方なら、その効果を日々実感されていることと思います。
でも「なぜ効くのか?」と患者さんに聞かれたとき、どう説明されていますか?
これまで鍼鎮痛のメカニズムといえば、中枢神経系でのエンドルフィン放出や、脊髄レベルでのゲートコントロール理論が主に語られてきました。
しかし最近、Local analgesia of electroacupuncture is mediated by the recruitment of neutrophils and released β-endorphins」(Shi et al., Pain, 2023)で報告された研究によりこれまであまり注目されてこなかった「末梢の免疫系」を介した鎮痛メカニズムが明らかになってきたそうです。
今日はこの興味深い発見について、できるだけわかりやすくご紹介していきたいと思います。
従来の理解:神経系中心のメカニズム
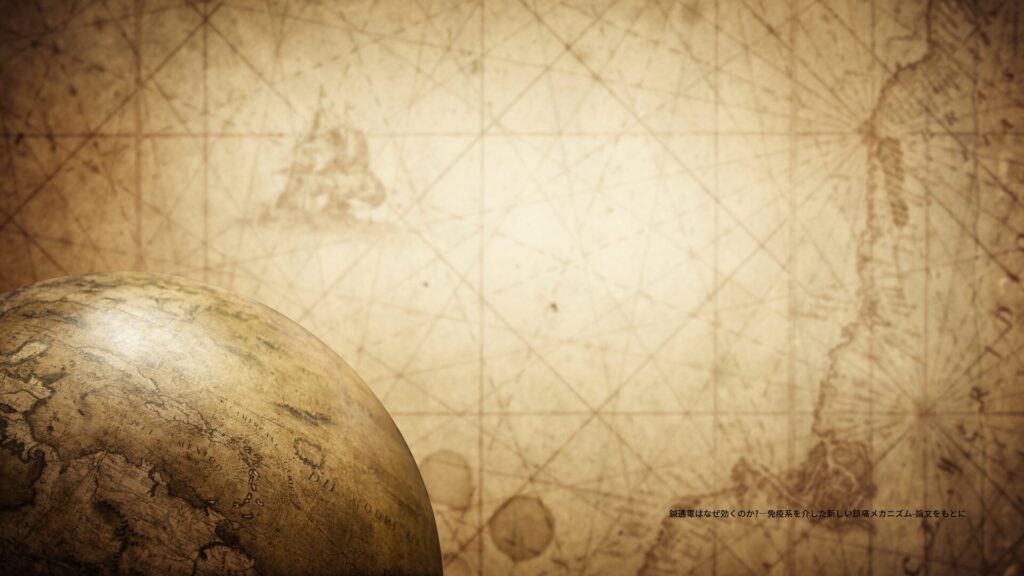
まず、これまでのわかっていることを簡単におさらいしましょう。
鍼鎮痛の研究は長い歴史があり、主に神経系に焦点が当てられてきました。低頻度(2〜10Hz)の鍼通電は、中枢神経系でエンケファリンやβ-エンドルフィンといった内因性オピオイドの放出を促進します。高頻度(100Hz)ではダイノルフィンの放出が促されるという周波数依存性も知られていますね。
また、脊髄レベルでは、セロトニンやノルアドレナリンといった下行性疼痛抑制系が活性化され、NMDA受容体(グルタミン酸受容体)のリン酸化が抑制されることで鎮痛効果が得られます。
これらは教科書的な知識として、多くの先生方がご存知のことと思います。
しかし、ここで一つ疑問が生まれます。鍼の刺激は局所にも作用しているはず。
末梢で何が起きているのでしょうか?
末梢で起きていることで有名なのはアデノシン鎮痛などですが
免疫系の関与
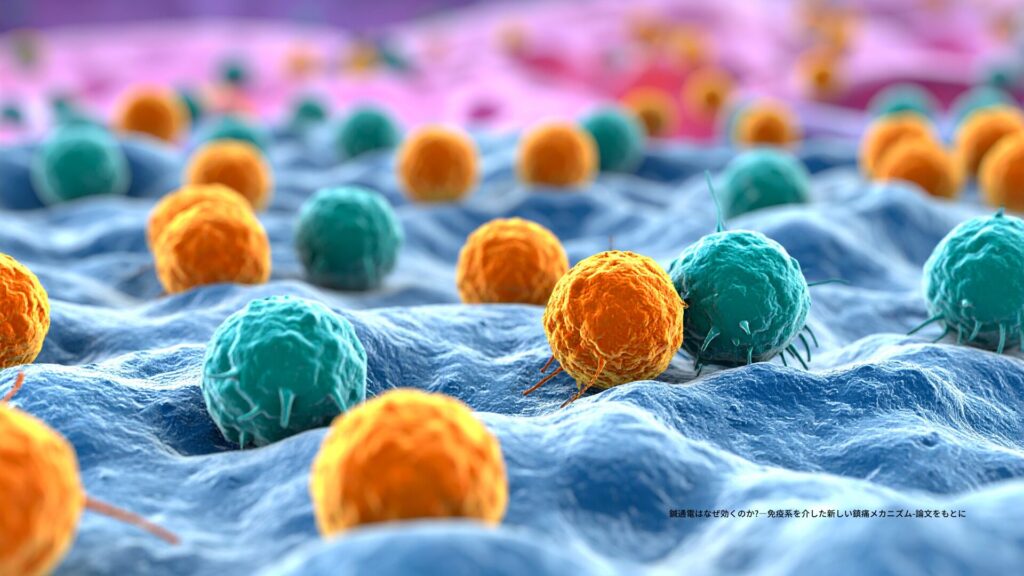
ここからが今回ご紹介する研究のポイントです。
Shi et al.の研究グループは、CFA(Complete Freund’s Adjuvant)誘発性の炎症性疼痛モデルラットを用いて、鍼通電が局所の炎症部位で何をしているのかを詳細に調べました。その結果、非常に面白い事が明らかになったんです。
β-エンドルフィンを運ぶ免疫細胞:好中球の重要な役割
鍼通電を行うと、炎症部位にβ-エンドルフィンを含んだ免疫細胞が集まってくることがわかりました。具体的には、ICAM-1陽性かつCD11b陽性の免疫細胞(主に好中球、一部マクロファージ)が、炎症組織に動員されるんです。
これまで、β-エンドルフィンといえば脳や脊髄で作られる鎮痛物質として理解されていましたが、実は末梢の免疫細胞も持っているんですね。そして鍼通電は、この免疫細胞を「鎮痛物質の運び屋」として炎症部位に呼び寄せているわけです。
好中球:意外な鎮痛の立役者
ここで主役となる好中球について、少し詳しく見ていきましょう。好中球といえば、感染症や組織損傷の際に真っ先に駆けつける「第一応答部隊」として知られています。貪食作用や活性酸素の産生により病原体を排除する、いわば身体の防衛軍です。
ところが、この好中球が鎮痛にも関与しているとは、多くの研究者にとって意外な発見でした。実は好中球は、その細胞質内にβ-エンドルフィンを含む顆粒を保持しているんです。そして適切な刺激を受けると、この顆粒からβ-エンドルフィンを放出します。
研究では、鍼通電後の炎症組織を免疫組織化学で詳細に分析した結果、β-エンドルフィン陽性細胞の多くが好中球マーカー(Ly6G)を発現していることが確認されました。フローサイトメトリー解析でも、鍼通電によってCD11b+/Ly6G+細胞(好中球)の数が有意に増加し、これらの細胞の約20-30%がβ-エンドルフィン陽性であることが示されました。
好中球の動員プロセス
では、好中球はどのようにして炎症部位に集まってくるのでしょうか?
- ケモカイン勾配の形成: 鍼通電により、局所でCXCL1(別名KC)というケモカインが産生されます。このCXCL1は、好中球表面に発現しているCXCR2受容体のリガンドで、好中球にとっての強力な「誘引物質」です。
- 血管内皮への接着: 好中球は血流中を循環していますが、CXCL1の濃度勾配を感知すると、まず血管内皮に接着します。この過程で、ICAM-1(細胞間接着分子-1)と好中球表面のインテグリンとの相互作用が重要な役割を果たします。
- 血管外遊走: 接着した好中球は、内皮細胞間を通り抜けて(遊走して)炎症組織へと移動します。この一連のプロセスは「白血球ローリング、接着、遊走」として知られる古典的な免疫学の基本メカニズムです。
- 組織内での集積: 組織に到達した好中球は、さらにケモカイン勾配に沿って炎症の中心部へと移動し、集積します。
研究では、鍼通電後の組織で好中球の浸潤が時間依存的に増加し、それに伴ってβ-エンドルフィン陽性細胞も増加することが示されました。つまり、好中球の動員とβ-エンドルフィンの供給が連動しているわけです。
β-エンドルフィンの放出メカニズム
組織に到達した好中球から、どのようにβ-エンドルフィンが放出されるのでしょうか?
好中球内のβ-エンドルフィンは、特殊な顆粒(二次顆粒や三次顆粒)に貯蔵されています。好中球が組織環境中の様々な刺激(炎症性サイトカイン、補体成分、細菌産物など)に曝されると、顆粒の内容物が細胞外に放出されます。この過程を「脱顆粒(degranulation)」といいます。
鍼通電後の炎症環境では、すでにIL-1βやTNF-αといった炎症性サイトカインが存在しており、これらが好中球の脱顆粒を促進すると考えられます。放出されたβ-エンドルフィンは、組織内の侵害受容器(痛覚神経)に発現しているμ-オピオイド受容体に結合し、鎮痛効果を発揮します。
好中球の二面性:炎症と鎮痛
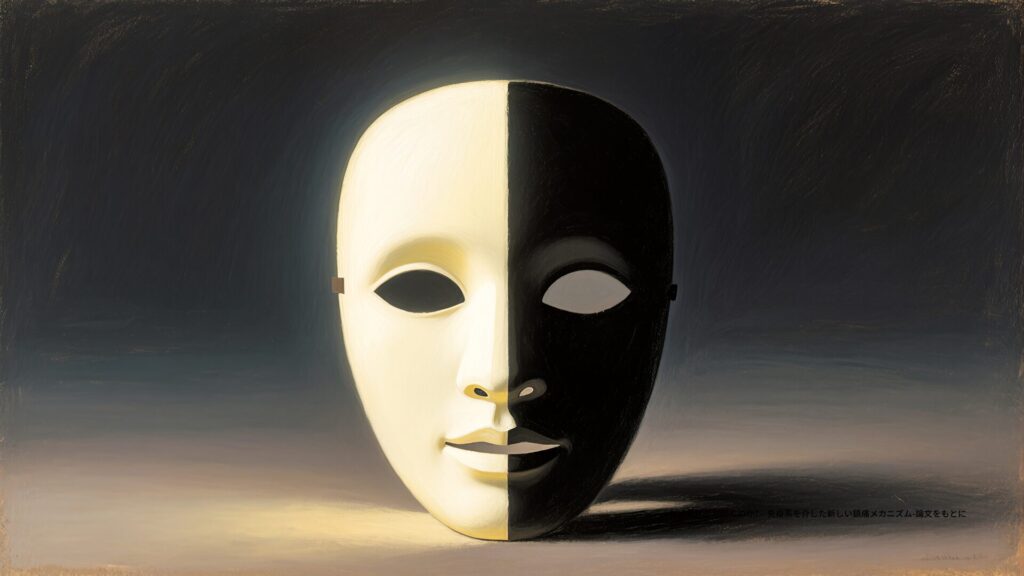
ここで興味深いのは、好中球の「二面性」です。
通常、好中球の浸潤は組織損傷や炎症を悪化させる可能性があると考えられています。活性酸素種やプロテアーゼの放出により、健常な組織まで傷つけてしまうことがあるからです。
しかし、この研究が示しているのは、好中球には「鎮痛」という別の顔があるということです。おそらく、急性炎症の初期段階では病原体の排除が最優先ですが、ある程度炎症が制御された段階では、同じ好中球が今度は鎮痛物質を供給することで、組織の回復を促進しているのかもしれません。
実際、研究では鍼通電によって動員された好中球が組織損傷を悪化させるという証拠は見られませんでした。むしろ、これらの好中球は主にβ-エンドルフィンを供給する「鎮痛細胞」として機能しているようです。
交感神経系の巧妙な役割
さらに面白いのは、この免疫細胞の動員に交感神経が関与しているという点です。
研究では、鍼通電によって局所のノルアドレナリン(NE)濃度が上昇することが示されました。このノルアドレナリンは交感神経の末端から放出されるのですが、これが一種の「誘導信号」として働くんです。
RNAシーケンス解析により、鍼通電後に炎症組織でCxcl1という遺伝子の発現が上昇することが明らかになりました。このCxcl1は好中球を呼び寄せるケモカインをコードする遺伝子で、ノルアドレナリン濃度と正の相関を示しました。つまり、交感神経→ノルアドレナリン放出→Cxcl1発現増加→好中球動員、という連鎖反応が起きているわけです。
実験的証拠の積み重ね:好中球の決定的役割
この仮説を証明するため、研究グループは様々な実験を行いました。
まず、交感神経系の関与を確認するため、6-OHDA(交感神経毒)で交感神経を破壊すると、鍼通電の鎮痛効果が消失しました。また、末梢に投与できるオピオイド拮抗薬(naloxone methiodide)や、β-エンドルフィンに対する抗体を投与すると、やはり鎮痛効果が阻害されました。
逆に、CXCL1を外から投与すると、鍼通電なしでも好中球が集まり、鎮痛効果が得られました。これらの実験は、このメカニズムが本当に機能していることを強く示唆しています。
好中球除去実験:決定的な証拠
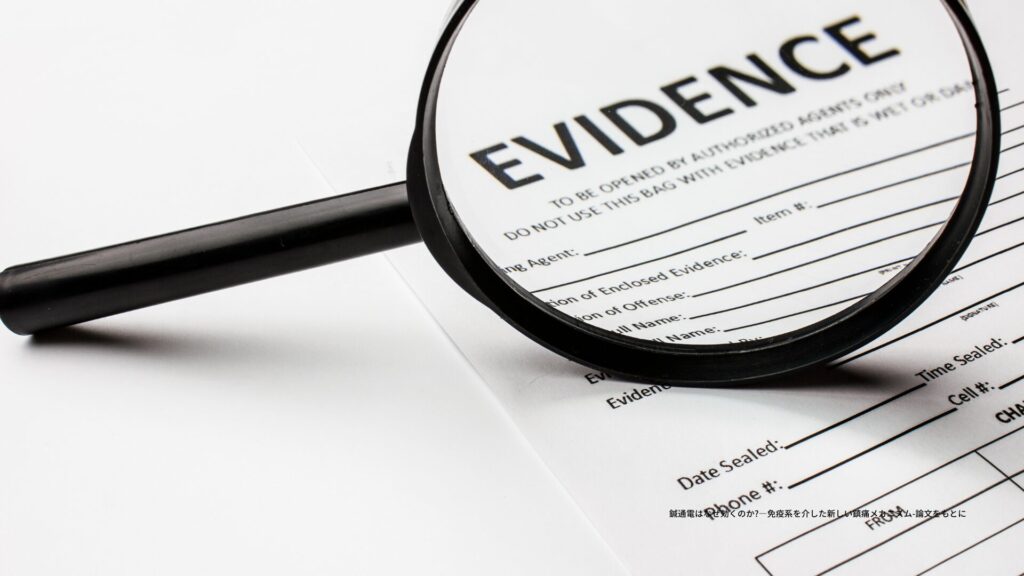
さらに決定的だったのが、好中球を選択的に除去する実験です。
研究では抗Ly6G抗体を用いて好中球を除去したところ、鍼通電による鎮痛効果が完全に消失しました。この実験は、好中球が単なる傍観者ではなく、鎮痛メカニズムの中心的プレーヤーであることを明確に示しています。
また、CXCR2ノックアウトマウス(CXCL1の受容体を持たないマウス)を用いた実験では、鍼通電を行っても好中球が炎症部位に集まらず、鎮痛効果も得られませんでした。これは、CXCL1-CXCR2経路を介した好中球の動員が、このメカニズムの必須ステップであることを証明しています。
時間経過の解析:好中球動態と鎮痛効果の相関
さらに興味深いのは、時間経過の解析です。
鍼通電後、炎症組織内の好中球数は時間とともに増加し、約6-12時間でピークに達します。そして、この好中球増加のタイムコースが、鎮痛効果の発現と非常によく一致するんです。
具体的には:
- 0-2時間: 好中球の増加は軽度、鎮痛効果も限定的
- 4-6時間: 好中球が顕著に増加し始め、鎮痛効果も明確に
- 8-12時間: 好中球数がピーク、最大の鎮痛効果
- 24時間以降: 好中球数は減少傾向だが、鎮痛効果は持続
この相関関係は、好中球の動員が鎮痛効果の主要因であることを強く支持しています。
好中球以外の免疫細胞の役割
ただし、好中球だけが関与しているわけではありません。
研究では、マクロファージもβ-エンドルフィンを含んでおり、炎症部位に存在することが確認されました。ただし、マクロファージは主に組織常在性で、鍼通電による急性の動員という点では好中球ほど顕著ではありませんでした。
おそらく、急性期の鎮痛には主に好中球が、より慢性的な段階ではマクロファージなど他の免疫細胞も関与する、という時間的な役割分担があるのかもしれません。これは今後の研究課題ですね。
臨床への示唆:局所治療と好中球動態の再評価

この発見は、臨床にとってどんな意味を持つのでしょうか?特に、好中球の関与という新しい知見は、私たちの治療戦略を再考させてくれます。
局所刺激の重要性:好中球を呼ぶために
まず、「痛いところに鍼を打つ」という古典的なアプローチが、科学的に裏付けられたと言えます。遠隔部位への刺激も重要ですが、炎症部位近傍への直接的な刺激には、免疫系、特に好中球を介した独自の鎮痛メカニズムが働いているんですね。
好中球は血流中を循環していますが、CXCL1などのケモカインによって特定の部位に誘導されます。つまり、鍼刺激によって局所でケモカインを産生させることが、好中球動員の起点となります。この意味で、局所への適切な刺激は単なる伝統的な知恵ではなく、免疫学的に合理的な治療戦略なのです。
実際、論文では「局所鎮痛効果(local analgesic effect)」という言葉が使われています。これは全身性の下行性疼痛抑制とは異なる、末梢レベルでの鎮痛です。
好中球動態を考慮した治療計画
好中球の動員には時間がかかることを理解しておく必要があります。
前述のように、好中球が炎症部位に集積し、鎮痛効果が最大になるまで6-12時間程度かかります。これは臨床的に重要な意味を持ちます:
- 即効性と持続性の違い: 鍼通電直後の鎮痛は主に神経系(ゲートコントロール、下行性抑制)によるものですが、数時間後からの持続的な鎮痛には好中球が関与している可能性があります。
- 治療間隔の設定: 好中球の動員と鎮痛効果が12-24時間持続することを考えると、毎日の治療よりも1-2日おきの治療の方が、免疫系を介したメカニズムを最大限に活用できるかもしれません。
- 治療効果の評価時期: 「今日治療して、明日また来てください」というスケジュールの場合、好中球を介した鎮痛がまだ十分に発現していない可能性があります。治療効果の適切な評価には、少なくとも24-48時間後の状態を見る必要があるでしょう。
好中球機能を最適化する生活指導
好中球の機能は、患者さんの全身状態に大きく影響されます。臨床では以下の点も考慮すべきでしょう:
- 栄養状態: 好中球の産生と機能には適切な栄養が必要です。特にタンパク質、亜鉛、ビタミンCなどの不足は好中球機能を低下させます。
- ストレス管理: 慢性的なストレスはコルチゾールレベルを上昇させ、好中球の動員や機能に影響します。鍼治療と並行して、ストレス管理の重要性を伝えることも大切です。
- 睡眠: 睡眠不足は免疫機能全般を低下させ、好中球の活性にも悪影響を及ぼします。
- 薬剤との相互作用: 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やステロイドは、好中球の動員や機能に影響する可能性があります。これらの薬剤を服用している患者さんでは、鍼通電の効果が修飾される可能性を念頭に置くべきです。
※薬剤指導はもちろん禁忌です。
刺激パラメータの最適化
この研究では、鍼通電の周波数や強度についても検討されています。炎症性疼痛の場合、2〜10Hzの低周波刺激が100Hzの高周波より効果的であることが複数の研究で示されています。
おそらく、周波数によって活性化される神経線維や、放出される神経伝達物質が異なり、それが免疫細胞の動員にも影響するのでしょう。今後、どの周波数が最も効率的に免疫細胞を動員するのか、さらなる研究が期待されます。
メカニズムの統合:末梢と中枢の協調
ここで大切なのは、この末梢の免疫メカニズムが、中枢神経系のメカニズムと対立するものではない、という点です。
鍼通電は多層的に作用します。末梢では今回明らかになった免疫系を介した鎮痛が起こり、同時に脊髄や脳幹レベルでの下行性疼痛抑制系も活性化されます。さらに、大脳レベルでは痛みの情動的側面(不快感)も軽減されます。
これらが総合的に働くからこそ、鍼通電は単なる一時的な鎮痛ではなく、持続的で包括的な疼痛管理につながるのだと考えられます。
今後の研究の方向性

この研究をよんで私は疑問を思った事が何個かあります。ちょっと列記してみます。
慢性痛への応用
今回の研究は主に急性〜亜急性の炎症性疼痛モデルで行われました。では、神経障害性疼痛や慢性痛では同じメカニズムが働くのでしょうか?
慢性痛では免疫系の状態も変化しているため、異なるアプローチが必要かもしれません。
最適な刺激条件の探索
免疫細胞の動員を最大化するための最適な刺激条件(周波数、強度、持続時間、刺激部位)をさらに詳細に検討する必要があります。
また、雀琢などの手技鍼でも同様の効果が得られるのか、それとも電気刺激特有の現象なのかも興味深い点です。
個体差の理解
患者さんによって鍼の効き方が異なるのは、鍼灸師なら誰もが経験することです。
免疫系の状態、交感神経の活性度、遺伝的背景などが、この末梢メカニズムの効率に影響している可能性があります。こうした個体差を理解できれば、より個別化された治療が可能になるでしょう。
他の治療法との併用
この研究は、鍼通電と他の治療法の併用についても示唆を与えてくれます。例えば、抗炎症薬との併用で相乗効果が得られるのか、それとも免疫細胞の動員が阻害されて効果が減弱するのか。こうした相互作用の理解は、統合医療の観点から重要です。
臨床で意識すべきこと
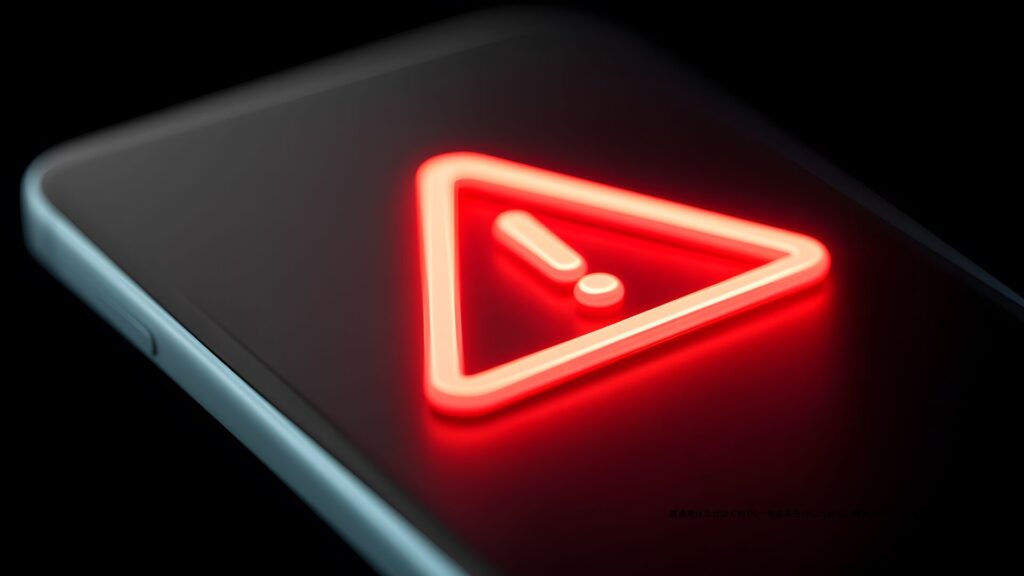
最後に、この知見を臨床でどう活かすか、いくつかポイントをまとめておきましょう。
1. 局所刺激を軽視しない
遠隔部位の経穴も大切ですが、炎症性疼痛の場合、患部周辺への刺激には独自の価値があります。免疫系を介した鎮痛メカニズムを活用するためにも、局所への適切な刺激を心がけましょう。
2. 交感神経系の状態を考慮する
このメカニズムは交感神経を介しているため、極度に交感神経が抑制されている状態(過度の疲労、副交感神経優位など)では効果が限定的かもしれません。全身状態の評価も忘れずに。
3. 適切な刺激強度と周波数
炎症性疼痛には2〜10Hzの低周波が効果的とされています。また、刺激強度は患者さんが耐えられる範囲で、しっかりとした得気が得られる程度が良いでしょう。免疫細胞を動員するには、ある程度の刺激量が必要と考えられます。
4. 効果発現の時間を考慮する:好中球動員の時間軸
免疫細胞、特に好中球が動員され、組織に集積し、β-エンドルフィンが放出されるまでには一定の時間が必要です。前述の通り、好中球数と鎮痛効果がピークに達するのは治療後6-12時間です。
ただし、好中球の主な動員は治療後に起こるため、「長時間通電すれば効果が比例して増す」わけではないことも理解しておきましょう。むしろ、適切な強度で十分な時間刺激を与えることで、好中球動員のスイッチを確実に入れることが重要です。
また、患者さんには「治療後、数時間から半日程度かけて徐々に効果が高まる」ことを説明しておくと良いでしょう。「治療直後はまだ効いていない」と不安にならないための配慮です。
5. 好中球の状態を推測する:効果予測の試み
すべての患者さんで同じように好中球が動員されるわけではありません。以下のような場合、好中球を介したメカニズムの効果が限定的かもしれません:
- 白血球数が極端に少ない患者: 化学療法中、重度の栄養不良など
- 慢性炎症を抱えている患者: 好中球がすでに他の部位に動員されている
- ステロイド長期使用者: 好中球機能が抑制されている
- 高齢者: 免疫応答全般が低下している可能性
逆に、これらの要因がない健康な若年〜中年の患者さんでは、好中球を介したメカニズムが十分に機能し、より良好な治療効果が期待できるでしょう。
もちろん、好中球機能が低下していても、中枢神経系を介した鎮痛メカニズムは依然として機能します。ただし、持続的な効果という点では、やや限定的になる可能性があります。
おわりに
鍼通電の鎮痛メカニズムにおける免疫系の役割という、この新しい知見は、古くて新しい鍼治療の科学的理解を大きく前進させるものです。
中枢神経系だけでなく、末梢の免疫系という「もう一つの鎮痛システム」を鍼が活性化していること。それが交感神経を介して巧妙に制御されていること。これらの発見は、何千年も前から経験的に積み重ねられてきた鍼治療の知恵が、現代の免疫学・神経科学の視点からも理にかなっていることを示しています。
同時に、これは終着点ではなく、新たな研究の出発点でもあります。この知見をベースに、さらに効果的な治療法の開発や、個別化医療への応用が進んでいくことでしょう。
私たち臨床家にできることはこうした科学的知見を学びながら、日々の臨床で患者さんと向き合い、効果を検証し続けることだと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。皆さんの臨床の一助となれば幸いです。
参考文献
- Shi JT, Cao WY, Zhang XN, et al. Local analgesia of electroacupuncture is mediated by the recruitment of neutrophils and released β-endorphins. Pain. 2023;164(9):1965-1975.
- Mechanisms of Acupuncture-Electroacupuncture on Persistent Pain. Anesthesiology 2014
- Local analgesia of electroacupuncture is mediated by the recruitment of neutrophils and released β-endorphins(Shi et al., Pain, 2023)


コメント