※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
今回は
この論文を中心に記事を書いていきたいと思います。
いつも通りすべてを鵜呑みにしてしまったらだめですよ!
宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼
お金持っている人は新品買ってね!
では内容に入っていきましょう♪
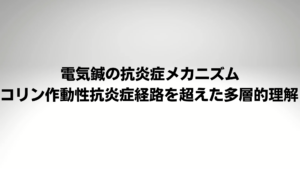
はじめに

鍼灸治療は何千年もの歴史を持つ伝統的な東洋医学の療法ですが、近年になってその作用機序が科学的に解明されつつあります。
特に注目されているのが、皮下組織に存在する肥満細胞(マスト細胞)が鍼灸による鎮痛効果の引き金として重要な役割を果たしているという知見です。
この記事では、複数の研究成果をもとに、鍼灸刺激がどのように肥満細胞を活性化し、鎮痛効果をもたらすのか、その分子メカニズムについて詳しく解説させていただきます。
経穴における肥満細胞の特異的な分布
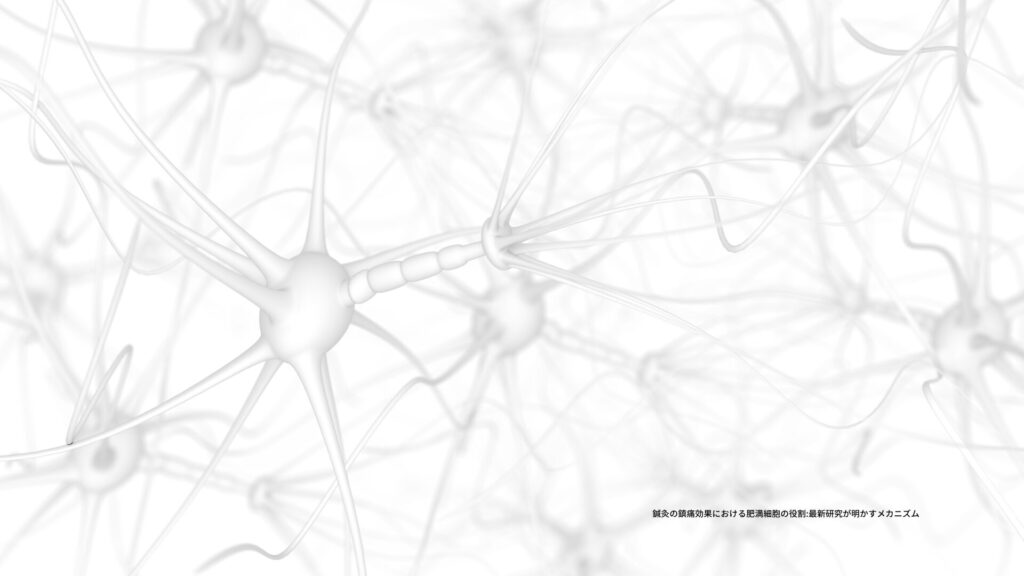
肥満細胞とは
肥満細胞は、骨髄由来の免疫細胞であり、結合組織や粘膜組織に広く分布しています。刺激を受けると脱顆粒を起こし、さまざまな生理活性物質を放出することが知られています[2]。
従来、肥満細胞はアレルギー反応や炎症反応の主要な担い手として理解されてきましたが、最近の研究では疼痛の緩和にも関与することが明らかになってきました[7]。
経穴における高密度分布
1977年に宋先生によって初めて提唱された仮説以来[2]、経穴部位における肥満細胞の分布が注目されてきました。
研究によると、経穴部位では非経穴部位と比較して肥満細胞が有意に高密度で分布していることが確認されています。ウサギのPC6(内関)経穴を調べた研究では、経穴部位の肥満細胞密度が明らかに高いことが組織学的に示されました。
さらに興味深いことに、ヒトの皮膚生検を用いた大規模な研究では、285例の検体を解析した結果、真皮における肥満細胞が豊富な特別な部位は、頭部、四肢、そして体表の開口部周辺に存在し、そのパターンが14の古典的な経絡における経穴の分布と高い相関を示すことが報告されています[6]。
この発見は、鍼灸の神経免疫学的基盤を示す組織学的証拠として重要な意味を持っているといえるでしょう。
肥満細胞の微細な局在パターン
肥満細胞の分布をさらに詳しく観察すると、正常なラットにおいて、肥満細胞は表皮内や真皮の血管周囲に集積しており、一部は下層真皮や皮下組織で脱顆粒している様子が確認されています[2]。免疫組織化学的染色を用いた詳細な解析では、肥満細胞は毛包、血管、神経線維に沿って比較的集中して分布していることが明らかになりました[2,6]。
さらに、脂肪組織や筋組織の境界部にも肥満細胞が分布していることが観察されています[2]。統計学的分析によると、毛包、神経、血管、脂肪組織、骨格筋の近傍には、離れた場所と比べて有意に多くの肥満細胞が集積する傾向があることが示されています[2]。
組織硬度と肥満細胞の分布
興味深いことに、肥満細胞は組織の硬度が変化する部位に集まる傾向があることが明らかになっています。in vitro実験では、異なる硬度領域を持つポリジメチルシロキサン(PDMS)膜上でラット好塩基球性白血病細胞株(RBL-2H3)を培養したところ、細胞は硬度が変化する境界部位に移動して留まることが観察されました[2]。in vivo実験でも、ラットの皮下肥満細胞が空間的に不均一に分布し、組織や細胞外基質の硬度変化がある部分に優先的に分布することが確認されています[2]。
これらの知見は、局所組織の硬度を変化させることが肥満細胞の集積を引き起こす可能性を示唆しています。肥満細胞の起源と実験結果を考慮すると、肥満細胞は透過性毛細血管を含む組織に存在し、硬度変化のある領域を選好する傾向があると予測されます[2]。
ポリジメチルシロキサン(PDMS)は、シリコーンの一種で、透明で安定した性質を持つ高分子化合物
好塩基球性白血病細胞株とは、好塩基球(白血球の一種)の細胞ががん化した白血病から樹立された細胞株のことです。主に好塩基球の機能研究や、アレルギー反応に関わるヒスタミン遊離のメカニズム解析、アレルギー治療薬の候補を探索する研究などに利用されます。ラットの好塩基球性白血病細胞株「RBL-2H3」が代表的です。
肥満細胞数の調節機構
肥満細胞数の増加は、肥満細胞の発達と集積の増加として理解することができます。肥満細胞前駆細胞は幹細胞因子(SCF)とその受容体c-kitによって成熟肥満細胞へと発達します。加えて、局所のサイトカインやケモカインも肥満細胞数を増加させることが知られています[2]。
特に重要なのが、単球走化性タンパク質-1(MCP-1)です。これは肥満細胞の遊走と浸潤を調節する主要なケモカインとして知られています。正常ラットを用いた研究では、胃兪(BL21)と足三里(ST36)への電気鍼刺激(0.1mA、2/15Hz交互波、25分間)により、局所の肥満細胞数が増加し、脱顆粒が促進されることが報告されています。この肥満細胞数の増加は、SCF抗体の局所投与により抑制されることも確認されています[2]。
一連の実験により、経穴における肥満細胞数がMCP-1含量と正の相関を示すことが明らかになりました。ラットのBL21にMCP-1抗体を投与すると、局所の肥満細胞数と脱顆粒率が減少し、さらに電気鍼による肥満細胞数の増加と脱顆粒率の上昇も予防されることが示されています[2]。
また、細胞間接着分子-1(ICAM-1)は白血球が血管壁を透過して組織に出ることを可能にします。電気鍼治療(0.1mA、2/15Hz交互波、25分間)を受けたST36において、ICAM-1 mRNAの発現増加が観察されることも報告されています[2]。
ケモカインは、主に白血球などの細胞の遊走(移動)を誘導するサイトカイン(細胞間の情報伝達物質)の一種です。
鍼灸刺激による肥満細胞の活性化メカニズム

機械的刺激の伝達
鍼灸治療において、経穴への刺鍼と手技操作によって鎮痛効果が生み出されます。機械的刺激は、刺鍼によって経穴に加えられる主要な刺激様式です。ラットを用いた研究では、刺入手技により240〜280mNの力が発生し、捻転手技により10〜15mN×mm⁻¹のトルクが生じることが測定されています[2]。
これらの機械的刺激は、皮下のコラーゲン線維が鍼の周りに巻きつく(!?)ことによって、より広く深い空間へと伝達されていきます[22,24]。この現象は「得気」や「鍼感」として臨床的に認識されており、鍼灸師が感じる「鍼の抵抗感」として体験されます[22,24]。
TRPVチャネルを介した活性化
肥満細胞が機械的刺激に応答できる理由の一つは、細胞膜上に複数のタイプの機械感受性チャネルを発現しているためです。特に重要なのが、一過性受容体電位バニロイド(TRPV)ファミリーのチャネルです[2]。
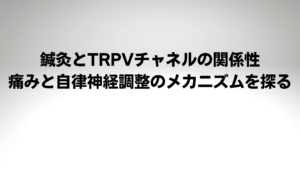
TRPV1チャネル
TRPV1は、カプサイシンと熱に感受性を示すカルシウム透過性イオンチャネルとして1997年に初めて記述され、この発見によりDavid Julius氏は2021年にノーベル賞を受賞しました。TRPV1は疼痛シグナル伝達活動に関与していることが示されており、鎮痛剤の重要な標的となっています[2]。
TRPV1は43℃を超える温度によって特徴的に活性化されますが、これはお灸治療中に皮膚表面で到達する温度です。興味深いことに、熱刺激だけでなく機械的な刺激もTRPV1の活性化に関与していることが示されています。全細胞パッチクランプ実験により、細胞外培地の浸透圧変化や、パッチピペットへの吸引による圧力がTRPV1を介した電流の増加をもたらすことが明らかになっています[2]。
さらに、レーザー光もTRPV1イオンチャネルを活性化できることが示されています。緑色レーザー光(406nm)をTRPV1を異種発現させたアフリカツメガエル卵母細胞に照射した実験や、赤色レーザー光(640nm)をヒト肥満細胞株HMC-1細胞に照射した実験で、TRPV1の活性化が確認されています[2]。43℃への温度上昇により、細胞内カルシウム活性が増加し、この増加はEGTAによる細胞外カルシウムのキレートによって減弱することも示されています[2]。
TRPV2チャネル
TRPV2も二価陽イオンに対して選択的に透過性を示し、カルシウムが細胞内に流入することを可能にします。このチャネルは52℃を超える侵害性の温度に対する感受性によって特徴づけられています。加えて、機械的ストレスもTRPV2を活性化します[2]。
ヒト肥満細胞株HMC-1を用いた全細胞パッチクランプ実験では、パッチピペットを介して−60cmH₂Oの細胞内圧減少を加えると、TRPV2特異的阻害剤SKF96365に感受性を示す電流成分が活性化されることが示されました。また、53℃への温度上昇や赤色レーザー光もTRPV2を活性化することが確認されています[2]。これらの刺激は実際に、TRPV2の活性化を介した細胞内カルシウムの増加をもたらします[2]。
TRPV2の活性化は、上記のすべての物理的刺激によって肥満細胞の脱顆粒を引き起こすことが示されています。in vivo実験でTRPV2欠損マウスを用いた研究では、野生型マウスと比較して、足関節炎症を持つTRPV2ノックアウトマウスでは鍼刺激に対する反応が見られず、肥満細胞の脱顆粒も少ないことが明らかになりました[2]。
これらの知見は、肥満細胞関連のTRPV2チャネルが、肥満細胞の機械感受性脱顆粒を媒介することによって、鍼灸鎮痛の引き金機構に寄与する可能性を示唆しています[2]。
TRPV4チャネル
TRPV1やTRPV2とは対照的に、TRPV4は温度受容器ではありません。TRPV4の主な特徴は機械的ストレスに対する感受性であり、このことがTRPV4を鍼灸によって活性化される候補としています[2]。
ラットの経穴皮膚組織にはTRPV4 mRNAが存在しますが、骨格筋層には存在しません。TRPV4チャネルは主に疼痛センサーとして考えられており、その機械感受性を介して機械的異痛を維持しています[2]。
これらの知見と一致して、炎症部位でのTRPV4チャネルの薬理学的阻害は触覚異痛を緩和しますが、熱性痛覚過敏には効果がないことが示されています。興味深いことに、治療される足三里経穴でのTRPV4チャネルの遮断は、鍼灸介入による抗侵害受容機能の発揮を妨げることが報告されています[2]。
TRPV1、TRPV2、そしてTRPV4の活性化が肥満細胞の脱顆粒につながることが複数の研究で確認されています。TRPV1特異的アゴニストであるカプサイシンによる活性化により、HMC-1細胞の脱顆粒が60%以上に増加します。低張ストレスによって誘導された肥満細胞の脱顆粒は、TRPV2特異的アンタゴニストSKF96365の存在下で減弱することも示されています。また、化合物48/80によって誘導される脱顆粒は、TRPV4特異的アンタゴニストHC067047によって減弱することが報告されています[2]。
クロライドチャネルの役割
機械的ストレスは、伸展活性化クロライドチャネル(SAC)も活性化することができます。これらは肥満細胞において、4,4′-ジイソチオシアノ-2,2′-スチルベンジスルホン酸(DIDS)に対する感受性によって同定できます[2]。
低張溶液は、HMC-1細胞およびラット組織由来の肥満細胞において、DIDSに部分的に感受性を示す外向き整流電流成分を活性化します。全細胞モードでパッチピペットに負圧を加えることによって同様の結果が得られました[2]。SACsの活性化は、蛍光技術によって測定された[Ca²⁺]ᵢの上昇にもつながります。その結果、肥満細胞はDIDS感受性の脱顆粒で応答します[2]。
鍼灸シグナル伝達における化学的メディエーター

アデノシンとATPの役割
細胞外ATP(eATP)およびその他のプリンおよびピリミジン化合物、例えばADP、アデノシン、UTP、UDP、UDP-グルコースなどは、プリン作動性シグナル伝達における重要なメディエーターです。これらは、さまざまな物理的刺激、特に伸展、変形、せん断応力などの機械的ストレスに応答して、組織内の細胞から放出されます[14,15]。
2009年にBurnstock博士は、鍼灸の有益な効果が経穴でのATP放出を介してプリン作動性シグナル伝達カスケードを引き起こすことに関与している可能性があるという仮説を提唱しました[14,15]。この概念により、プリン作動性シグナル伝達、特に神経系のP2受容体の鍼灸における役割に関する研究が活発化しました[14]。
刺鍼が経穴での細胞外アデノシンの蓄積を促進することは、ヒトとげっ歯類の両方で証拠が示されています。健康な男性ボランティアを対象とした研究では、30分間の鍼治療により、治療されたST36における間質アデノシン濃度が増加することが確認されています[12]。足関節炎症マウスでは、30分間の鍼治療に応答して、治療されたST36においてアデノシンとともにAMP、ADP、ATPが集積することが示されています[12]。
さらに詳細な研究として、足関節炎症ラットを用いた研究では、刺鍼治療されたST36におけるアデノシン蓄積が、肥満細胞安定化剤であるクロモグリク酸ナトリウム(CRO)の投与によって肥満細胞の脱顆粒を防ぐことで抑制されることが明らかになりました。これは前述の鍼灸鎮痛効果の抑制と並行して起こります[12]。
手技鍼だけでなく、電気鍼もアデノシンの集積を媒介することができます。下垂体後葉ホルモン誘発性急性心拍数低下ウサギにおいて、内関(PC6)への30分間の電気鍼治療によってアデノシン蓄積が起こることが報告されています[12]。
アデノシンA1受容体の重要性
足関節炎症または神経障害性疼痛モデルマウスにおいて、経穴ST36でのアデノシンA1受容体の活性化は、2-クロロ-N6-シクロペンチルアデノシン(CCPA、A1受容体特異的アゴニスト)により抗侵害受容効果を示すことが明らかになっています[12]。同様に、足関節炎症ラットにおいて、経穴ST36へのCCPA注射は、刺鍼誘導性の抗侵害受容を再現することができます[12]。一方、A1受容体がノックアウトされると、鍼灸はもはや機能しなくなります[12,21]。
これらの発見は、アデノシンA1受容体が鍼灸による局所的な抗侵害受容効果を媒介する上で中心的な役割を果たしていることを示しています[12,21]。
2-クロロ-N6-シクロペンチルアデノシン(CCPA、A1受容体特異的アゴニスト)はアデノシンA1受容体という特定の受容体に対して選択的に作用する物質(アゴニスト)です。
ATPの二面性と代謝
集積したアデノシンは、活性化された肥満細胞から直接放出されるか、他の共放出されたヌクレオチド(ATPやADPなど)から変換されることができます[14,15]。後者も無視できません。なぜなら、ATPはさまざまな哺乳類細胞におけるストレス応答分子であり、機械的な力が刺鍼によって経穴で発生する主な刺激だからです[2]。
鍼灸刺激が機械感受性の皮下肥満細胞からのATP放出を促進する可能性は十分にあります。実際に、in vitro実験では、肥満細胞がさまざまな物理的刺激によってATPを放出することが確認されています[14]。HMC-1細胞株を用いた実験では、刺鍼を模倣した50%低張ショック、お灸を模倣した熱、レーザー鍼を模倣した657nmレーザー照射により、ATPが放出されることが示されています[14]。
in vivoでも、刺鍼操作は足関節炎症ラットの治療されたST36の間質空間において、eATP= 細胞外アデノシン三リン酸(extracellular adenosine 5′-triphosphate:eATP)を一過性に蓄積させることが報告されています[14]。
一般的に、eATPは炎症促進性メディエーターとして受け入れられており、プリン作動性受容体(P2受容体)の活性化を介して疼痛知覚を増強する可能性があります[14]。しかし、エクトヌクレオチダーゼの存在は、アデノシン産生を促進することによって疼痛機構におけるeATPの役割を逆転させる可能性があります[14]。
エクトヌクレオチダーゼの非特異的アンタゴニストであるARL67156によってATP分解を防ぐと、in vitroでHMC-1細胞からの機械感受性ATP放出が増強され、in vivoで刺鍼治療された経穴でのeATP蓄積が増強されることが示されています[14]。これは、肥満細胞および経穴におけるエクトヌクレオチダーゼの発現を示しています[14]。
ラットの経穴におけるRT-PCR測定により、複数のタイプのエクトヌクレオチダーゼの存在が確認されています。中でも、NTPDase 1とNt5eが主要なヌクレオチド加水分解酵素であり、ATPをADPを中間体としてAMPに分解し、AMPをアデノシンに加水分解します[14]。
さらなる研究により、足関節炎症ラットにおいて、治療されたST36でeATPレベルを上昇または低下させることが、鍼灸鎮痛効果を減弱または再現できることが報告されています[14]。このことは、ATPの動員(放出と分解を含む)が鍼灸鎮痛に寄与していることをさらに示唆しています。
エクトヌクレオチダーゼは、細胞膜の外側に存在する、細胞外のヌクレオチドを分解する酵素です。主にアデノシン三リン酸(ATP)を分解してアデノシンを産生する働きがあり、細胞外のATPを分解してATPのシグナル伝達を終結させる一方、アデノシンの産生を通じてアデノシン受容体(P1受容体)を活性化します。
ATPによるシグナル増幅
肥満細胞から放出されたATPは、アデノシンの前駆体であることに加えて、刺鍼シグナルの増幅においても機能する可能性があります。鍼灸によって生成される音響せん断波は、in vitroおよびin vivoで[Ca²⁺]ᵢショックとカルシウム波伝播(CWP)を引き起こすことが示されています[14]。これは、局所化された鍼灸シグナルの増幅と伝達を示しています。
同様のCWP現象が、機械的刺激に応答してin vitroで肥満細胞に起こり、これはP2Y13およびP2X7受容体によって媒介されるATP誘導性ATP放出に起因することが示されています[14]。ラット肥満細胞(RBL-2H3細胞株)を培地置換によって刺激すると、細胞外空間へ放出されるATPが6倍に上昇します。この機械感受性ATP放出は、刺激の20分前に細胞に導入されたスラミン(100μM)の存在によって減弱されることが確認されています[14]。
ヒスタミンの役割

ヒスタミンは主に肥満細胞によって産生され、貯蔵されています。ラット結合組織の典型的な肥満細胞は、約10〜20pgのヒスタミンを含んでいます[2]。細胞を離れると、ヒスタミンはヒスタミンN-メチルトランスフェラーゼ(HMT)またはジアミンオキシダーゼによって速やかに分解されます。組織に放出されたヒスタミンの半減期は約1分であり、これがヒスタミン効果の空間的および時間的範囲を制限しています[2]。
in vitroでHMC-1細胞において機械感受性ヒスタミン放出が確認されています。正常ラットのLI4経穴において、免疫組織化学的分析により、ヒスタミンが肥満細胞上で弱く発現しており、3分間の鍼治療後には肥満細胞およびその分離した顆粒上で強く発現するようになることが確認されています[2]。
さらに、ST36へのヒスタミン単独の局所投与は、足関節炎症ラットにおいて鍼治療用量と同様の抗侵害受容効果を発揮します[2]。同様の知見がVieira博士らによっても観察されており、ヒスタミン(20μL、0.03、0.3、3または30mg)の局所投与が、マウスのCFA誘発性足関節炎症および慢性絞扼損傷(CCI)神経障害性疼痛において用量依存的な鎮痛効果を誘導することが示されています[2]。
ヒスタミンH1受容体の重要性
ヒスタミン受容体には4つのタイプがありますが、特にヒスタミンH1受容体が、多様な応答のための末梢組織におけるヒスタミンの相互作用標的として注目されています[2]。足関節炎症ラットにおいて、鍼灸鎮痛効果は、2-ピリジンエタンアミン二塩酸塩(Pyrid.)によるH1受容体の局所活性化によって再現することができ、クロルフェニラミンマレイン酸塩(CPM)によるH1受容体の局所阻害によって大幅に減弱することが示されています[2]。
さらなる探究により、中枢神経系におけるβ-エンドルフィンの調節がその下流の事象であることが明らかになっています[2]。これらの知見は、肥満細胞関連のヒスタミンが、局所のヒスタミンH1受容体を活性化することによって、鍼灸鎮痛の引き金機構において重要な役割を果たしていることを示しています。
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン、5-HT)
セロトニンは肥満細胞のもう一つの重要なメディエーターであり、肥満細胞と神経終末との相互作用において潜在的な役割を果たしています[2]。モノヨード酢酸誘発性膝関節変形性関節症ラットにおいて、セロトニンはトリプターゼおよびヒスタミンとともに、感作された経穴(GB34およびEX-LE2)において上方調節されており、これが経穴における循環系、神経系、免疫系の相互作用を媒介する可能性があります[2]。
正常ラットのLI4において、セロトニン免疫陽性肥満細胞が皮下組織と真皮に存在し、3分間の鍼治療に応答してそれらの脱顆粒が起こることが観察されています[2]。同様の知見が正常ラットのST36でも観察されています[2]。加えて、経穴ST36へのセロトニンの局所投与は、CFA誘発性足関節炎症またはCCI神経障害性疼痛に苦しむマウスにおいて抗侵害受容効果を持つことが報告されています[2]。
「モノヨード酢酸誘発性膝関節変形性関節症ラット」とは、研究目的でモノヨード酢酸(monoiodoacetic acid)という薬剤をラットに投与し、人為的に膝関節の変形性関節症を再現した実験動物モデルです。
CFA(完全フロイントアジュバント)誘発性足関節炎症は、主に動物実験における関節炎(特に関節リウマチ)のモデルとして使用される現象です。結核菌の死菌を含むCFAを足関節腔またはその周囲組織に注入することにより、強い炎症反応とそれに伴う症状が人工的に引き起こされます。
肥満細胞と神経終末の相互作用による鎮痛シグナルの上行

皮膚への鍼灸治療は神経シグナルに変換され、求心性ニューロンから脊髄および中枢神経系へと伝導されることが知られています[2]。肥満細胞と神経の空間的接触の特異性は、in vitroおよびin vivoで実証されており、皮膚組織においても確認されています[2]。ラットの経穴においても、肥満細胞と神経線維、そして微小血管の共局在が存在することが示されています[2]。
神経伝達の重要性
足関節炎症ラットにおいて、治療されたST36でリドカインによって末梢神経を遮断すると、鍼灸鎮痛効果が減弱しますが、肥満細胞の脱顆粒は著しく抑制されないことが観察されています[2]。ST36は坐骨神経の枝の一つである腓骨神経によって支配されています。正常ラットにおいて、ST36への刺鍼は坐骨神経および腰椎4〜5の後根における神経放電を増加させますが、この増加はCROによる肥満細胞脱顆粒の抑制によって減弱されます[2]。
これらの知見は、刺鍼によって活性化された肥満細胞が、最終的には近傍の神経終末に生物学的シグナルを伝達し、その後中枢神経系へと上行することによって鎮痛効果に関与していることを示唆しています[2]。
神経原性炎症の役割
皮下肥満細胞の活性化は、皮膚において神経原性炎症を引き起こすことができます[2]。サブスタンスP(SP)およびカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)は、ヒスタミンおよびセロトニンとともに、鍼治療後のラットのLI4経穴においてより多く発現することが確認されています[2]。
実際には、神経原性炎症と肥満細胞の活性化との間には相互的な因果関係が存在します。肥満細胞の活性化は、ブラジキニン、サブスタンスP(SP)、血管作動性腸管ペプチド(VIP)、CGRP、そしてヒスタミンやセロトニンなどのアミンを含むペプチドの末梢神経終末からの放出を誘導し、これらがアレルギー反応の炎症媒介性悪化に寄与します[2]。
さらに、CGRP、SP、VIPなどの神経ペプチドも、脱顆粒を通じて肥満細胞から多数の炎症性メディエーターの放出をもたらし、その結果として肥満細胞メディエーター媒介性の神経活性化が起こり、これが神経原性炎症および疼痛知覚をさらに増強します[2]。
経穴感作における神経原性炎症
神経原性炎症は経穴感作の生物学的基盤の一つです。経穴感作とは、身体が特定の疾患に罹患すると、対応する経穴が活性化され感作される現象を指します[2]。神経原性炎症は、後根反射または軸索反射による経穴感作の生物学的基盤の一つとなっています[19,20]。
例えば、ラットにおいて胃粘膜損傷は、関連する経穴の皮膚において神経原性血漿漏出をもたらし、SPおよびCGRPの増加を伴うことが報告されています[2]。感作された経穴の刺激は、より良好な臨床効果を生み出す潜在的な傾向を示します[2]。経穴感作は局所の肥満細胞の活性化と密接に関連しています[2]。
組織損傷に伴う炎症
神経原性炎症に加えて、鍼の刺入と手技操作による組織損傷に関連する炎症も、治療された経穴で発生します。損傷関連分子である高移動度グループボックス1(HMGB1)およびトール様受容体4(TLR4)、そしてTNF-αやIL-6などのいくつかの炎症性因子が、正常ラットにおいて2分間の刺鍼によって治療されたST36で上方調節されることが報告されています[2]。
このような局所化された炎症は、全身性免疫応答を開始することによって鍼灸効果を引き起こす上で重要な役割を果たしていると考えられています[2]。この局所炎症は、必ずしも有害なものではなく、むしろ治療効果を引き出すための生理学的なシグナルとして機能している可能性が示唆されています[19,20]。
臨床的意義と応用
肥満細胞欠損モデルからの知見
肥満細胞欠損動物を用いた研究は、肥満細胞の重要性をさらに明確にしています。c-kit遺伝子変異誘発性肥満細胞欠損ラット(WsRC⁻⁺/⁺ラット)は、野生型ラットと比較して、経穴を含む全身で肥満細胞数が少なく、より高い機械的疼痛閾値を示します[2]。
重要な知見として、非疼痛性のWsRC⁻⁺/⁺ラットにおいて、鍼治療(10分間、ST36)が依然として機械的疼痛に対する鎮痛効果を生み出すことができるものの、その効果は野生型ラットと比較して実質的に減少していることが示されています[2]。加えて、WsRC⁻⁺/⁺ラットは他の伝統中医学治療に対しても感受性が低下しています。46℃のお灸を模倣した侵害性刺激や3mAの電気鍼のみが、機械的疼痛に対してより少ない抗侵害受容効果を生み出すことができます[2]。
これらの知見は、肥満細胞が鍼灸による鎮痛効果において中心的な役割を果たしていることを強く支持しています[2]。
電気鍼における肥満細胞の役割
手技鍼だけでなく、電気鍼においても肥満細胞の活性化が重要な役割を果たしています。下垂体後葉ホルモン誘発性急性心拍数低下ウサギモデルを用いた研究では、内関(PC6)への30分間の電気鍼治療が肥満細胞の脱顆粒とアデノシン放出を促進し、これが心拍数の改善と関連していることが示されています[12]。
この研究では、経穴特異性も検討されており、PC6への電気鍼刺激が他の非経穴部位への刺激と比較して、より顕著な効果を示すことが確認されています[12]。これは、経穴における肥満細胞の高密度分布と機能的特性が、治療効果における経穴特異性の基盤となっている可能性を示唆しています。
レーザー鍼灸のメカニズム
近年、レーザー光を用いた鍼灸治療が注目されています[11]。レーザー鍼灸は、可視光線または赤外線ビームを経穴に照射する治療法です。興味深いことに、レーザー光もTRPVチャネルを活性化し、肥満細胞からのメディエーター放出を誘導できることが示されています[2]。
緑色レーザー光(532nm)はTRPV4チャネルを活性化し、青色(405nm)または緑色(532nm)レーザー光はRBL-2H3細胞からヒスタミン放出を引き起こします[2]。赤色レーザー光(640nm)はTRPV1およびTRPV2チャネルを活性化し、HMC-1細胞からのATP放出を促進します[2,14]。
これらの知見は、レーザー鍼灸の治療効果も、従来の刺鍼と同様に肥満細胞の活性化を介して発揮される可能性を示唆しています。レーザー鍼灸は皮膚を貫通しないため、感染リスクが低く、小児や鍼恐怖症の患者への応用が期待されます[11]。
今後の研究の方向性と課題
未解明の分子機構
本稿で紹介した研究により、皮下肥満細胞が鍼灸誘発性鎮痛の引き金として重要な役割を果たしていることが明らかになってきましたが、シグナル伝達経路における個々のステップにはまだ解明が必要な部分が残されています[2]。
特に、セロトニンの放出と5-HT1受容体の刺激が鎮痛においてどのような役割を果たすのか、さらなる調査が必要とされています[2]。また、複数のTRPVチャネル(TRPV1、TRPV2、TRPV4)がそれぞれどの程度寄与しているのか、またそれらの相互作用についても詳細な解析が求められます。
個人差と体質への応用
肥満細胞の分布密度や機能には個人差があることが予想されます。実際、経穴における肥満細胞の密度や応答性の個人差が、鍼灸治療の効果の個人差を説明する可能性があります。今後、個々の患者における肥満細胞の状態を評価し、それに基づいて治療プロトコルを最適化するオーダーメイド医療への応用が期待されます。
伝統中医学における「体質」の概念と、肥満細胞の分布や機能との関連性を探ることも、興味深い研究テーマとなるでしょう。例えば、アレルギー体質を持つ患者では肥満細胞の活性が異なる可能性があり、これが鍼灸治療への応答性に影響を与えるかもしれません。
他の疾患への応用可能性
本稿では主に鎮痛効果に焦点を当てましたが、肥満細胞の活性化は他の多くの生理学的プロセスにも影響を与える可能性があります。肥満細胞は免疫系の重要な構成要素であり、サイトカインやケモカインの産生を通じて炎症応答を調節します[2,7]。
したがって、鍼灸による肥満細胞の活性化が、自己免疫疾患、アレルギー性疾患、慢性炎症性疾患などの治療においてどのような役割を果たすのか、今後の研究が期待されます。また、肥満細胞は血管新生や組織修復にも関与することが知られており、創傷治癒や組織再生における鍼灸の効果を説明する手がかりとなる可能性があります[7]。
トランスレーショナルリサーチの推進
動物実験で得られた知見をヒトに応用するためには、トランスレーショナルリサーチの推進が不可欠です。ヒトの経穴における肥満細胞の分布と機能を詳細に調べ、動物モデルとの類似点と相違点を明らかにする必要があります。
また、非侵襲的な画像診断技術を用いて、鍼灸治療中および治療後の経穴における肥満細胞の動態や、メディエーターの放出をリアルタイムで観察する技術の開発も重要です。これにより、臨床効果と分子レベルの変化との相関をより直接的に評価することが可能になるでしょう。
まとめ
鍼灸治療による鎮痛効果のメカニズムについて、特に肥満細胞の役割に焦点を当てて解説してまいりました。複数の研究から得られた知見を統合すると、以下のような鎮痛機構が浮かび上がってきます。
経穴に分布する高密度の肥満細胞は、刺鍼による機械的刺激、お灸による熱刺激、レーザーによる光刺激など、さまざまな物理的刺激を感知します。これらの刺激はTRPV1、TRPV2、TRPV4などの機械感受性・熱感受性イオンチャネルや、伸展活性化クロライドチャネルを活性化し、細胞内カルシウム濃度の上昇をもたらします。
カルシウム濃度の上昇により肥満細胞は脱顆粒を起こし、ヒスタミン、セロトニン、ATPなどの多様なメディエーターを放出します。放出されたATPは、エクトヌクレオチダーゼによってアデノシンに変換され、A1受容体を介して鎮痛効果を発揮します。同時に、ヒスタミンはH1受容体を、セロトニンは5-HT受容体を活性化し、複数の経路を通じて疼痛シグナルを抑制します。
これらのメディエーターは、経穴に密に分布する感覚神経終末を刺激し、シグナルは末梢神経、脊髄を経て中枢神経系へと伝達されます。中枢レベルでは、β-エンドルフィンなどの内因性オピオイドの放出が促進され、下行性疼痛抑制系が活性化されることで、最終的な鎮痛効果がもたらされます。
このように、鍼灸による鎮痛効果は、局所の肥満細胞活性化から始まる複雑なカスケードを通じて実現されていると考えられます。伝統的な経験則に基づいて発展してきた鍼灸治療の効果が、現代の分子生物学的手法によって科学的に裏付けられつつあることは、東洋医学と西洋医学の統合という観点からも大変意義深いことといえるでしょう。
今後、さらなる研究の進展により、より効果的で個別化された鍼灸治療プロトコルの開発や、新たな鎮痛療法の開発につながることが期待されます。肥満細胞を標的とした新しい治療戦略の可能性も含め、鍼灸医学の科学的基盤はますます確固たるものとなっていくものと思われます。
参考文献
- Goldman N, Chen M, Fujita T, Xu Q, Peng W, Liu W, Jensen TK, Pei Y, Wang F, Han X, et al. Adenosine A1 receptors mediate local anti-nociceptive effects of acupuncture. Nat Neurosci. 2010;13(7):883-888.
- Wang LN, Wang XZ, Huang M, Li BR, Wang XY, Guo R, Liu YJ, Ding GH, Schwarz W. Activation of Subcutaneous Mast Cells in Acupuncture Points Triggers Analgesia. Cells. 2022;11(5):809.
- Zhang D, Spielmann A, Wang L, Ding G, Huang F, Gu Q, Schwarz W. Mast-cell degranulation induced by physical stimuli involves the activation of transient-receptor-potential channel TRPV2. Physiol Res. 2012;61(1):113-124.
- Huang M, Wang X, Xing B, Yang H, Sa Z, Zhang D, Yao W, Yin N, Xia Y, Ding G. Critical roles of TRPV2 channels, histamine H1 and adenosine A1 receptors in the initiation of acupoint signals for acupuncture analgesia. Sci Rep. 2018;8(1):6523.
- Li YM. The neuroimmune basis of acupuncture: Correlation of cutaneous mast cell distribution with acupuncture systems in human. Am J Chin Med. 2019;47(8):1781-1793.
- Yang HW, Liu XY, Shen ZF, Yao W, Gong XB, Huang HX, Ding GH. An investigation of the distribution and location of mast cells affected by the stiffness of substrates as a mechanical niche. Int J Biol Sci. 2018;14(9):1142-1152.
- Galli SJ, Tsai M. IgE and mast cells in allergic disease. Nat Med. 2012;18(5):693-704.
- Bradding P, Walls AF, Holgate ST. The role of the mast cell in the pathophysiology of asthma. J Allergy Clin Immunol. 2006;117(6):1277-1284.
- Abraham SN, St John AL. Mast cell-orchestrated immunity to pathogens. Nat Rev Immunol. 2010;10(6):440-452.
- Theoharides TC, Alysandratos KD, Angelidou A, Delivanis DA, Sismanopoulos N, Zhang B, Asadi S, Vasiadi M, Weng Z, Miniati A, Kalogeromitros D. Mast cells and inflammation. Biochim Biophys Acta. 2012;1822(1):21-33.
- Chon TY, Mallory MJ, Yang J, Bublitz SE, Do A, Dorsher PT. Laser acupuncture: A concise review. Med Acupunct. 2019;31(3):164-168.
- Wang X, Huang M, Yang H, Zhang D, Yao W, Xia Y, Ding G. Mast cell degranulation and adenosine release: Acupoint specificity for effect of electroacupuncture on pituitrin-induced acute heart bradycardia in rabbits. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;2020:1348914.
- Zylka MJ, Sowa NA, Taylor-Blake B, Twomey MA, Herrala A, Voikar V, Vihko P. Prostatic acid phosphatase is an ectonucleotidase and suppresses pain by generating adenosine. Neuron. 2008;60(1):111-122.
- Burnstock G. Acupuncture: a novel hypothesis for the involvement of purinergic signalling. Med Hypotheses. 2009;73(4):470-472.
- Burnstock G, Krügel U, Abbracchio MP, Illes P. Purinergic signalling: from normal behaviour to pathological brain function. Prog Neurobiol. 2011;95(2):229-274.
- Chen L, Zhang J, Li F, Qiu Y, Wang L, Li YH, Shi J, Pan HL, Li M. Endogenous anandamide and cannabinoid receptor-2 contribute to electroacupuncture analgesia in rats. J Pain. 2009;10(7):732-739.
- Zhang RX, Lao L, Wang X, Fan A, Wang L, Ren K, Berman BM. Electroacupuncture combined with indomethacin enhances antihyperalgesia in inflammatory rats. Pharmacol Biochem Behav. 2005;81(1):146-151.
- Zhao ZQ. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol. 2008;85(4):355-375.
- Iwa M, Matsushima M, Nakade Y, Pappas TN, Fujimiya M, Takahashi T. Electroacupuncture at ST-36 accelerates colonic motility and transit in freely moving conscious rats. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2006;290(2):G285-G292.
- Takahashi T. Mechanism of acupuncture on neuromodulation in the gut-a review. Neuromodulation. 2011;14(1):8-12.
- Takano T, Chen X, Luo F, Fujita T, Ren Z, Goldman N, Zhao Y, Markman JD, Nedergaard M. Traditional acupuncture triggers a local increase in adenosine in human subjects. J Pain. 2012;13(12):1215-1223.
- Langevin HM, Churchill DL, Cipolla MJ. Mechanical signaling through connective tissue: a mechanism for the therapeutic effect of acupuncture. FASEB J. 2001;15(12):2275-2282.
- Langevin HM, Bouffard NA, Badger GJ, Churchill DL, Howe AK. Subcutaneous tissue fibroblast cytoskeletal remodeling induced by acupuncture: evidence for a mechanotransduction-based mechanism. J Cell Physiol. 2006;207(3):767-774.
- Langevin HM, Konofagou EE, Badger GJ, Churchill DL, Fox JR, Ophir J, Garra BS. Tissue displacements during acupuncture using ultrasound elastography techniques. Ultrasound Med Biol. 2004;30(9):1173-1183.

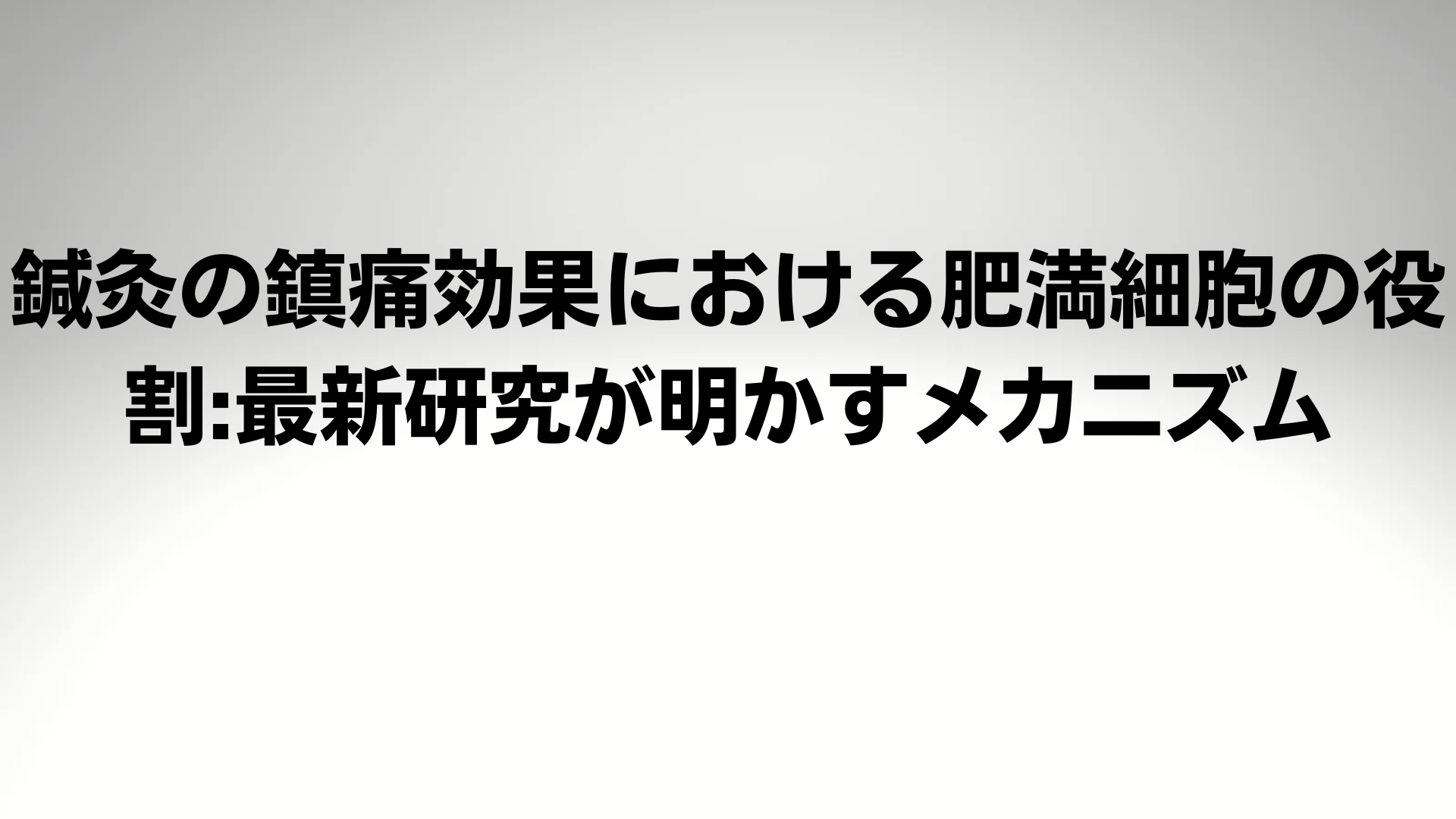
コメント