※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
参考文献はこちら
すべてを鵜呑みにしないでくださいね!
宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼
お金持っている人は新品買ってね!
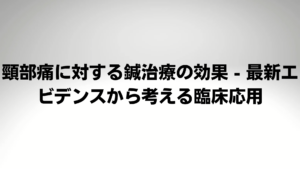
頸部痛に対しての鍼灸の論文に対して書いている別記事もどうぞ(^^♪
それでは内容に入っていきましょう‼
はじめに

頸椎症性神経根症(Cervical Spondylotic Radiculopathy、以下CSR)は、現代社会において増加傾向にある疾患のひとつです。
頸部の痛みや上肢への放散痛を主訴とし、患者さんの日常生活の質を大きく低下させる可能性があります。近年、保存的治療の選択肢として鍼灸治療、特に電気鍼(Electroacupuncture、以下EA)が注目を集めています。
本稿では、Suらによって2023年に発表された研究を中心に、電気鍼がCSRによる神経障害性疼痛を軽減するメカニズムについて、特にCaMKII/CREB/BDNF信号伝達経路と脊髄シナプス可塑性の調節という観点から解説いたします。
神経障害性疼痛と中枢性感作のメカニズム

CSRによる慢性的な痛みは、いわゆる神経障害性疼痛(Neuropathic Pain)に分類されます。この種の痛みは、アロディニア(本来痛みを感じないはずの刺激で痛みを感じる現象)や痛覚過敏といった特徴を持ち、通常の痛み止めでは効果が得られにくいことが知られています。
神経障害性疼痛の発生と維持には、「中枢性感作(Central Sensitization)」と呼ばれる現象が深く関わっています。これは、脊髄後角(痛み信号が最初に処理される場所)の神経細胞が過度に興奮しやすくなり、通常では痛みを引き起こさない程度の刺激でも強い痛み信号を脳に送ってしまう状態を指します。
この中枢性感作の背景には、脊髄レベルでのシナプス可塑性(神経細胞間の情報伝達効率が変化する現象)の変化があると考えられています。
BDNFと痛みの悪循環

脳由来神経栄養因子(Brain-Derived Neurotrophic Factor、以下BDNF)は、本来は神経細胞の生存や成長を支える重要な物質です。しかし、近年の研究により、BDNFが慢性疼痛の発症と維持において、むしろ痛みを増強する役割を果たしていることが明らかになってきました。
神経損傷が起こると、脊髄後角においてBDNFの発現が増加します。このBDNFは、チロシンキナーゼ受容体B(TrkB)という受容体に結合することで、様々な細胞内信号伝達を活性化させます。その結果、神経細胞の興奮性が高まり、痛み信号の伝達が増強されてしまうのです。
複数の研究が示すところによれば、BDNFは以下のような機序で痛みの慢性化に寄与すると考えられています。
第一に、BDNFは活動依存性にシナプス可塑性を調節し、長期増強(Long-term Potentiation、LTP)と呼ばれる現象を引き起こします。これにより、痛み信号を伝える神経回路が強化され、痛みが慢性化しやすくなります。
第二に、BDNFは脊髄後角の神経細胞において、グルタミン酸という興奮性神経伝達物質の放出を増加させ、NMDA受容体やAMPA受容体といった受容体の機能を変化させることで、痛み信号の増幅に寄与します。
第三に、BDNFはミクログリア(脳や脊髄に存在する免疫細胞)からも放出され、神経炎症を促進することで、痛みの悪循環を作り出す可能性があります。
CaMKII/CREB/BDNF信号伝達経路とは
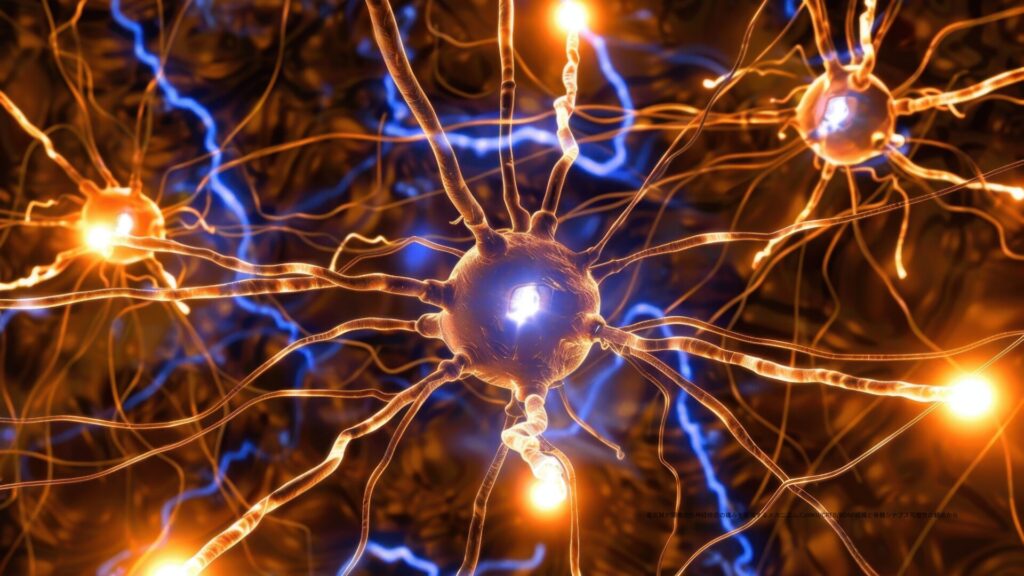
Suらの研究が着目したのは、カルシウム・カルモジュリン依存性プロテインキナーゼII(CaMKII)、cAMP応答配列結合タンパク質(CREB)、そしてBDNFという三つの分子が形成する信号伝達経路です。
この経路は以下のように作動すると考えられています。
まず、神経細胞内へのカルシウムイオンの流入が、カルモジュリンという分子を活性化させます。活性化されたカルモジュリンは、CaMKIIという酵素に結合し、これを活性化します。活性化されたCaMKIIは自己リン酸化(自分自身にリン酸基を付加すること)を起こし、カルシウムイオンがなくても活性を維持できる状態になります。
次に、活性化されたCaMKIIは、CREBという転写因子をリン酸化します。リン酸化されたCREB(p-CREB)は、細胞核内でDNAに結合し、特定の遺伝子の発現を調節します。その標的遺伝子のひとつが、BDNFをコードする遺伝子なのです。
こうして産生されたBDNFは細胞外に放出され、周囲の神経細胞のTrkB受容体に結合することで、さらなる細胞内信号伝達を引き起こします。これにより、シナプスの構造や機能が変化し、痛み信号の伝達が増強されることになります。
この一連の信号伝達経路は、慢性疼痛における中枢性感作の重要なメカニズムのひとつと考えられています。
シナプス可塑性と痛みの関係

シナプス可塑性とは、神経細胞間の情報伝達効率が、神経活動のパターンに応じて変化する現象を指します。本来は学習や記憶といった高次脳機能に重要な役割を果たしていますが、脊髄レベルでのシナプス可塑性の異常な亢進が、慢性疼痛の発症に関与することが分かってきました。
神経障害性疼痛の動物モデルにおいて、脊髄後角ではシナプス可塑性のマーカーとなる様々なタンパク質の発現が増加することが報告されています。これらには、シナプス後部密度タンパク質95(PSD-95)、成長関連タンパク質43(GAP-43)、シナプトフィジン(SYN)、アルファシヌクレイン(α-syn)などが含まれます。
さらに、電子顕微鏡による観察では、シナプス間隙(神経細胞間の隙間)の幅が減少し、シナプス後部の厚みが増加していることも確認されています。これらの変化は、シナプスでの情報伝達効率が高まっていることを示唆しています。
こうしたシナプス可塑性の変化により、通常では痛みを引き起こさない程度の刺激でも、強い痛み信号として伝達されるようになると考えられます。
Suらの動物実験が明らかにしたこと

Suらは、ラットを用いてCSRのモデルを作製し、電気鍼の効果とそのメカニズムを詳細に検討しました。
実験では、ラットの頸髄に圧迫を加えることでCSRモデルを作製しました。これにより、神経根の機械的圧迫と化学的刺激が生じ、ヒトのCSRに類似した病態が再現されました。
モデル作製の5日後、ラットには明らかな機械的痛覚過敏(通常では痛みを感じない程度の圧力刺激に対して過敏に反応する状態)と歩行障害が認められました。
このCSRモデルラットに対して、研究者らは7日間にわたり、1日1回20分間の電気鍼治療を施しました。使用したツボは、合谷(LI4)と太衝(LR3)でした。これらのツボは、伝統的な東洋医学において、気の流れを調整し、痛みを緩和する効果があるとされている経穴です。
治療後の評価において、電気鍼を受けたラットでは、痛覚過敏と歩行障害の両方が有意に改善されていることが確認されました。
電気鍼による分子レベルでの変化
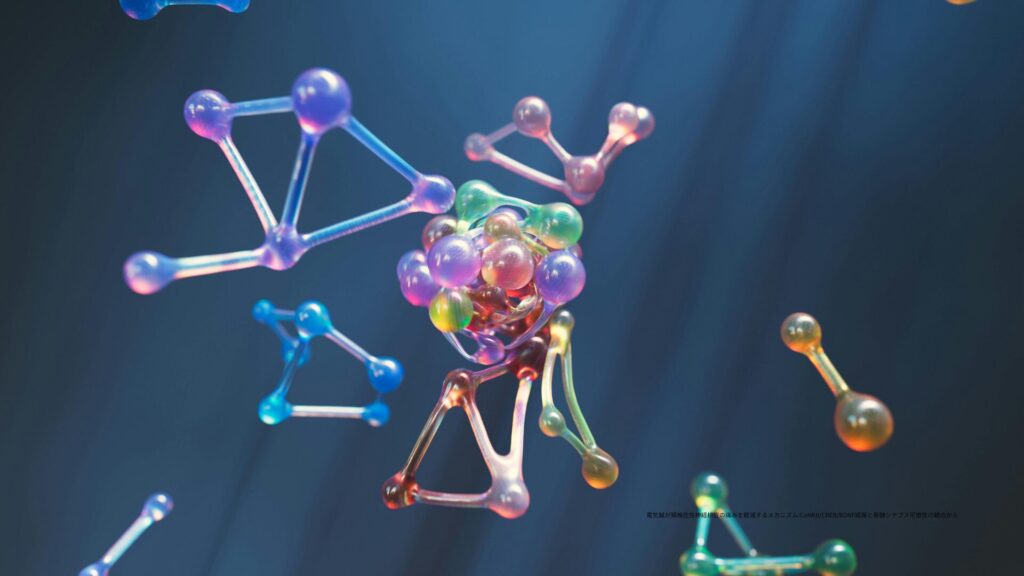
Suらの研究で最も重要な発見は、電気鍼がCaMKII/CREB/BDNF信号伝達経路を抑制することで、鎮痛効果を発揮している可能性を示したことです。
具体的には、CSRモデルラットの脊髄後角において、CaMKIIのmRNA(遺伝子から転写された情報分子)とリン酸化CaMKII(p-CaMKII、活性化された形態)の発現が増加していました。さらに、p-CREBとBDNFの発現も有意に上昇していました。
これらの変化は、神経損傷により脊髄レベルでCaMKII/CREB/BDNF経路が過剰に活性化され、中枢性感作が進行していることを示唆しています。
興味深いことに、電気鍼治療を受けたラットでは、これらの分子の異常な発現が抑制されていました。つまり、電気鍼はCaMKII/CREB/BDNF経路の過剰な活性化を正常化することで、中枢性感作を抑制し、鎮痛効果を発揮していると考えられるのです。
さらに、研究者らは免疫組織化学的手法を用いて、これらの分子が脊髄後角の神経細胞で発現していることを確認しました。また、c-fosという神経細胞の活動マーカーの発現も、電気鍼治療により減少していました。これは、電気鍼が脊髄後角の神経細胞の過剰な興奮を抑制していることを示しています。
シナプス可塑性の正常化

Suらの研究では、シナプス可塑性に関連するタンパク質の発現変化についても詳細に検討されました。
CSRモデルラットでは、PSD-95、GAP-43、SYNといったシナプス可塑性マーカーの発現が脊髄後角で増加していました。これは、神経損傷によりシナプスの構造や機能が変化し、痛み信号の伝達が増強されていることを示唆しています。
電気鍼治療を受けたラットでは、これらのシナプス可塑性マーカーの異常な発現が抑制されていました。さらに、透過型電子顕微鏡による観察では、電気鍼治療によりシナプスの超微細構造の異常が改善されていることも確認されました。
具体的には、CSRモデルで見られたシナプス間隙の減少やシナプス後部の肥厚といった変化が、電気鍼治療により正常化される傾向が認められたのです。
これらの結果は、電気鍼が脊髄レベルでのシナプス可塑性を調節することで、中枢性感作を抑制し、神経障害性疼痛を軽減している可能性を強く示唆しています。
関連する研究からの知見
Suらの研究と同様の結果は、他の研究グループからも報告されています。
Yangらの研究では、CSRモデルラットに対する電気鍼治療が、脊髄後角におけるシナプス可塑性を調節することで鎮痛効果を発揮することが示されました。この研究でも、シナプス関連タンパク質の発現変化や、透過型電子顕微鏡によるシナプス超微細構造の観察が行われ、Suらの結果を支持する知見が得られています。
また、Shiらの研究では、CSRに対する「益気活血」という伝統的な鍼治療法の効果が検討されました。この研究では、MAPK(マイトゲン活性化プロテインキナーゼ)経路を介した脊髄ミクログリアの活性化調節が、鍼治療の鎮痛メカニズムの一部である可能性が示唆されました。
さらに、Guoらの研究では、電気鍼がアストロサイト(脳や脊髄に存在するグリア細胞の一種)の活性化とHMGB1/TLR4/MyD88信号伝達経路を調節することで、CSRの鎮痛効果を発揮する可能性が報告されています。
これらの研究結果を総合すると、電気鍼は単一のメカニズムではなく、複数の分子経路を同時に調節することで、包括的な鎮痛効果を発揮していると考えられます。
脳レベルでの変化:皮質可塑性とBDNF
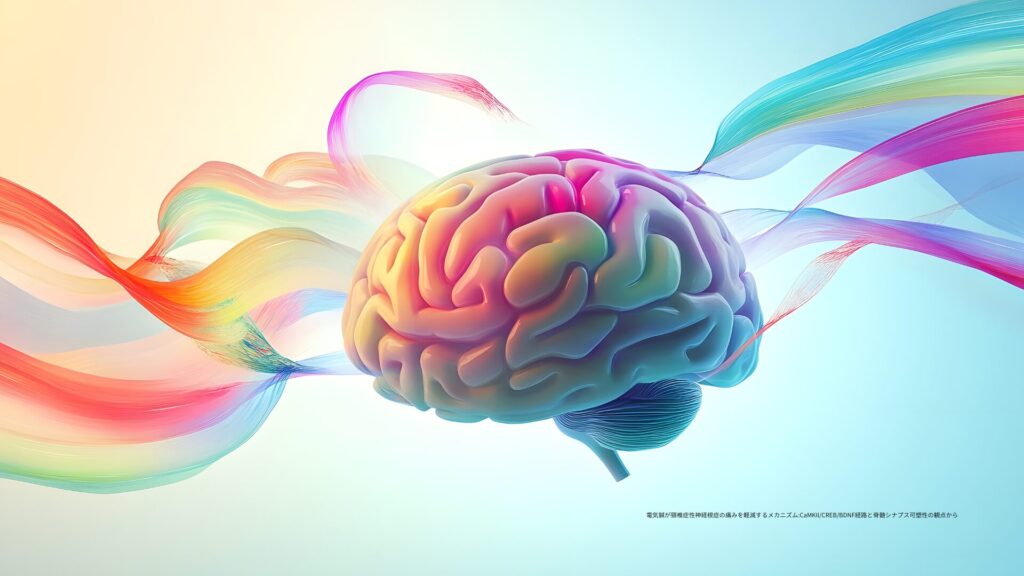
痛みの慢性化には、脊髄だけでなく、大脳皮質レベルでの神経可塑性の変化も関与していることが分かってきました。
Gharehら、およびBinauxらの研究では、炎症性疼痛モデルにおいて、一次体性感覚野(S1)や前帯状皮質(ACC)といった脳領域でBDNFの発現が増加し、これが皮質レベルでの神経可塑性の変化と痛みの慢性化に関与していることが示されました。
これらの脳領域は、痛みの感覚的側面(どこが、どれくらい痛いか)だけでなく、情動的側面(痛みによる不快感や苦痛)の処理にも関わっています。BDNFによる皮質可塑性の変化が、慢性疼痛における痛みの増強や、痛みに伴う不安や抑うつといった情動変化に寄与している可能性があります。
電気鍼が脊髄レベルだけでなく、皮質レベルでもBDNF関連の神経可塑性を調節している可能性は、今後の研究で明らかにされるべき重要な課題といえるでしょう。
CaMKII/CREB経路と痛み:癌性疼痛やその他の研究からの示唆
CaMKII/CREB経路が痛みの発症に重要であることは、CSR以外の疼痛モデルでも確認されています。
Wangらの研究では、癌性骨痛のモデルにおいて、ケモカイン受容体CXCR4が脊髄神経細胞のCaMKII/CREB経路を活性化することで、痛みの発症に寄与することが示されました。この研究では、CaMKII阻害剤の投与が痛みを軽減することも確認されており、CaMKII/CREB経路が痛みの治療標的として有望であることが示唆されています。
また、Zhouらの研究では、片頭痛モデルにおいて、酸性溶液による三叉神経痛覚経路の活性化が、CaMKII/CREB信号伝達経路を介して酸感受性イオンチャネル(ASIC)の発現を増加させることが明らかにされました。CaMKII阻害剤の投与により、これらの痛み行動が抑制されることも確認されています。
これらの研究は、CaMKII/CREB経路が様々な種類の慢性疼痛に共通して関与する重要な信号伝達経路であり、この経路を標的とした治療アプローチが広範な臨床応用の可能性を持つことを示唆しています。
電気鍼の抗炎症作用:もうひとつの重要なメカニズム
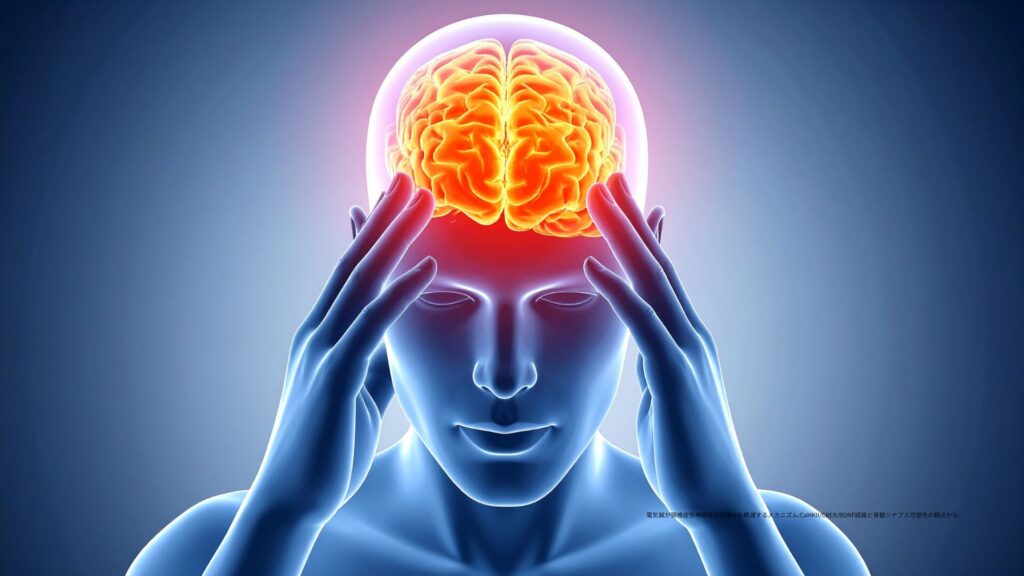
電気鍼の鎮痛効果には、神経可塑性の調節だけでなく、抗炎症作用も重要な役割を果たしていると考えられています。
神経根の機械的圧迫や化学的刺激により、脊髄において炎症性サイトカインと呼ばれる物質が放出されます。これらには、腫瘍壊死因子アルファ(TNF-α)、インターロイキン-1ベータ(IL-1β)、インターロイキン-6(IL-6)などが含まれます。これらの炎症性サイトカインは、神経細胞やグリア細胞を活性化し、痛みの発症と維持に寄与します。
多くの研究が、電気鍼がこれらの炎症性サイトカインの発現を抑制することを報告しています。
例えば、Shiらの研究では、CSRモデルラットの脊髄において、TNF-α、IL-6、IL-1βといった炎症性サイトカインの発現が増加しており、鍼治療がこれらを抑制することが示されました。
また、Sunらのレビューでは、足三里(ST36)というツボへの電気鍼が、様々な炎症性疾患モデルにおいて、TNF-α、IL-6、IL-1βなどの炎症性サイトカインを抑制することが報告されています。
これらの抗炎症作用は、迷走神経の活性化、TLR4/NF-κB信号伝達経路の抑制、マクロファージ(免疫細胞の一種)の極性化の調節など、複数のメカニズムを介して発揮されると考えられています。
炎症の抑制により、神経細胞の過剰な興奮が減少し、結果として中枢性感作が抑制されることで、電気鍼の鎮痛効果の一部が説明できるかもしれません。
神経-免疫相互作用の調節
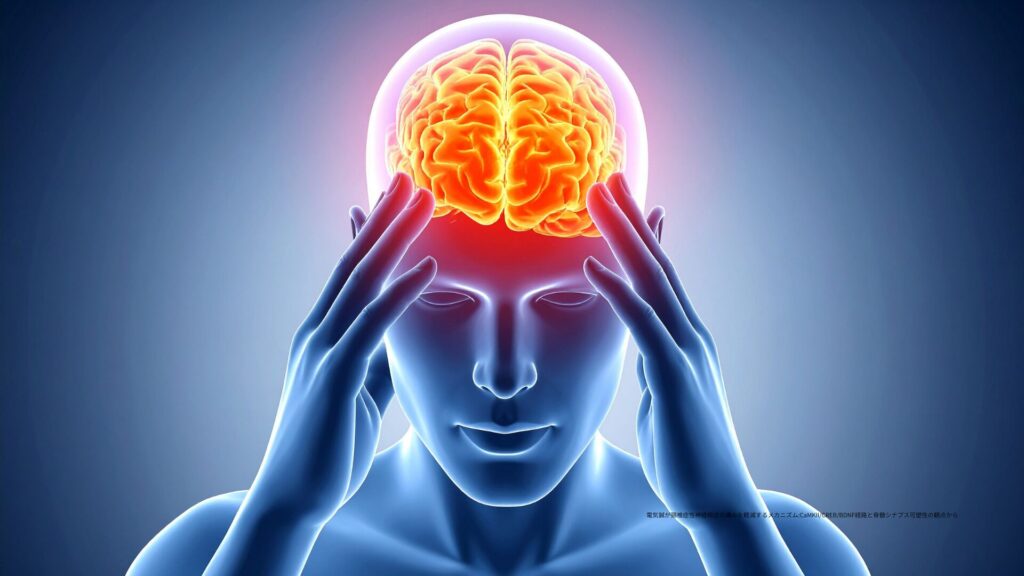
近年の研究により、神経系と免疫系は密接に相互作用しており、この相互作用が慢性疼痛の発症と維持に重要な役割を果たしていることが明らかになってきました。
電気鍼は、この神経-免疫相互作用を調節することで、治療効果を発揮している可能性があります。
例えば、迷走神経を介した抗炎症経路(cholinergic anti-inflammatory pathway)は、電気鍼の重要な作用機序のひとつと考えられています。迷走神経が活性化されると、脾臓に信号が伝わり、マクロファージからの炎症性サイトカインの産生が抑制されます。
Sunらのレビューでは、ST36への電気鍼が、迷走神経とカテコールアミン(アドレナリンなど)の産生に依存して、全身性の炎症を抑制することが報告されています。
また、電気鍼はマクロファージの極性化を調節することで、抗炎症作用を発揮する可能性も示唆されています。マクロファージには、炎症を促進するM1型と、組織修復を促進し炎症を抑制するM2型があります。電気鍼は、M1型からM2型への移行を促進することで、炎症環境を改善すると考えられています。
これらの神経-免疫相互作用の調節が、脊髄レベルでの神経可塑性の正常化と相まって、電気鍼の包括的な鎮痛効果につながっていると考えられます。
臨床応用への示唆と今後の展望
Suらの研究をはじめとする基礎研究の成果は、CSRに対する電気鍼治療の科学的根拠を提供し、臨床応用への道を開くものといえます。
現在のところ、CSRに対する保存的治療としては、理学療法、頸椎牽引、経皮的電気神経刺激、疼痛管理教育、頸椎カラーなどが行われていますが、これらの長期的な効果については議論があります。
電気鍼は、これらの従来の保存的治療に対する有効な代替療法または補完療法となる可能性があります。特に、薬物療法で十分な効果が得られない、あるいは副作用のために薬物療法を継続できない患者さんにとって、有用な選択肢となるかもしれません。
しかし、基礎研究の知見を臨床に応用するためには、いくつかの課題が残されています。
第一に、臨床試験における電気鍼の効果を適切に評価する必要があります。これまでの臨床研究の多くは、サンプルサイズが小さく、適切な対照群が設定されていないなどの限界がありました。今後は、より大規模で質の高い臨床試験が求められます。
第二に、最適な治療パラメータ(ツボの選択、刺激強度、刺激頻度、治療期間など)を決定する必要があります。伝統的な東洋医学の理論に基づくツボ選択と、現代科学的な知見に基づく刺激パラメータの最適化を、いかに統合するかが重要な課題となります。
第三に、電気鍼の作用機序についての理解をさらに深める必要があります。CaMKII/CREB/BDNF経路は重要な作用機序のひとつですが、これがすべてではありません。他の信号伝達経路、神経-免疫相互作用、中枢神経系における変化など、多角的な視点からのメカニズム解明が求められます。
第四に、手技鍼と電気鍼の効果の違いについても検討する必要があります。多くの基礎研究では電気鍼が用いられていますが、臨床現場では手技鍼も広く使用されています。両者の効果や作用機序に違いがあるのか、それともほぼ同等なのかを明らかにすることは、臨床応用において重要です。
おわりに
本稿では、Suらの研究を中心に、電気鍼がCSRによる神経障害性疼痛を軽減するメカニズムについて解説しました。
電気鍼は、脊髄後角におけるCaMKII/CREB/BDNF信号伝達経路の過剰な活性化を抑制し、シナプス可塑性を正常化することで、中枢性感作を抑制し、鎮痛効果を発揮すると考えられます。さらに、抗炎症作用や神経-免疫相互作用の調節も、電気鍼の治療効果に寄与している可能性があります。
これらの基礎研究の知見は、伝統的な東洋医学である鍼灸治療に、現代科学的な根拠を提供するものといえます。今後、さらなる研究により、電気鍼の作用機序が解明され、より効果的な治療プロトコルが確立されることが期待されます。
CSRをはじめとする慢性疼痛に苦しむ患者さんに対して、電気鍼が有効な治療選択肢となる日が来ることを願っています。
参考文献
- Su H, Chen H, Zhang X, Su S, Li J, Guo Y, Wang Q, Xie C, Yang P. Electroacupuncture ameliorates pain in cervical spondylotic radiculopathy rat by inhibiting the CaMKII/CREB/BDNF signaling pathway and regulating spinal synaptic plasticity. Brain Behav. 2023;13(10):e3177.
- Yang P, Chen HY, Zhang X, Wang T, Li L, Su H, Li J, Guo YJ, Su SY. Electroacupuncture Attenuates Neuropathic Pain in a Rat Model of Cervical Spondylotic Radiculopathy: Involvement of Spinal Cord Synaptic Plasticity. J Pain Res. 2023;16:2447-2460.
- Shi T, Liu Y, Ji B, Wang J, Ge Y, Fang Y, Xie Y, Xiao H, Wu L, Wang Y. Acupuncture Relieves Cervical Spondylosis Radiculopathy by Regulating Spinal Microglia Activation Through MAPK Signaling Pathway in Rats. J Pain Res. 2023;16:3919-3936.
- Guo YJ, Su SY, Su H, et al. Mechanism of analgesic effect of electroacupuncture on rats with cervical spondylosis radiculopathy based on activation of astrocytes and HMGB1/TLR4/MyD88 signaling pathway. Zhen Ci Yan Jiu. 2024;49(9):909-916.
- Sikandar S, Minett MS, Millet Q, Santana-Varela S, Lau J, Wood JN, Zhao J. Brain-derived neurotrophic factor derived from sensory neurons plays a critical role in chronic pain. Brain. 2018;141(4):1028-1039.
- Merighi A, Salio C, Ghirri A, Lossi L, Ferrini F, Betelli C, Bardoni R. BDNF as a pain modulator. Prog Neurobiol. 2008;85(3):297-317.
- Meléndez-García R, Segura-Olvera A, Mercado-Morales M, Castellanos-Pérez J, Ruiz-Pineda C, Del Ángel-García G. The Role of the Brain-Derived Neurotrophic Factor in Chronic Pain: Links to Central Sensitization and Neuroinflammation. Biomedicines. 2024;12(1):162.
- Garraway SM, Hochman S. Spinal Plasticity and Behavior: BDNF-Induced Neuromodulation in Uninjured and Injured Spinal Cord. Neural Plast. 2016;2016:9857201.
- Ghosh M, Pearse DD. The Role of the Serotonergic System in Locomotor Recovery after Spinal Cord Injury. Front Neural Circuits. 2015;8:151.
- Binaux D, Gaumond I, Boulanger A, Laferrière-Langlois P, Charbonneau L, Roussel M, Marchand S. BDNF-Dependent Plasticity Induced by Peripheral Inflammation in the Primary Sensory and the Cingulate Cortex Triggers Cold Allodynia and Reveals a Major Role for Endogenous BDNF As a Tuner of the Affective Aspect of Pain. J Neurosci. 2013;33(49):18755-18763.
- Wang LN, Yang

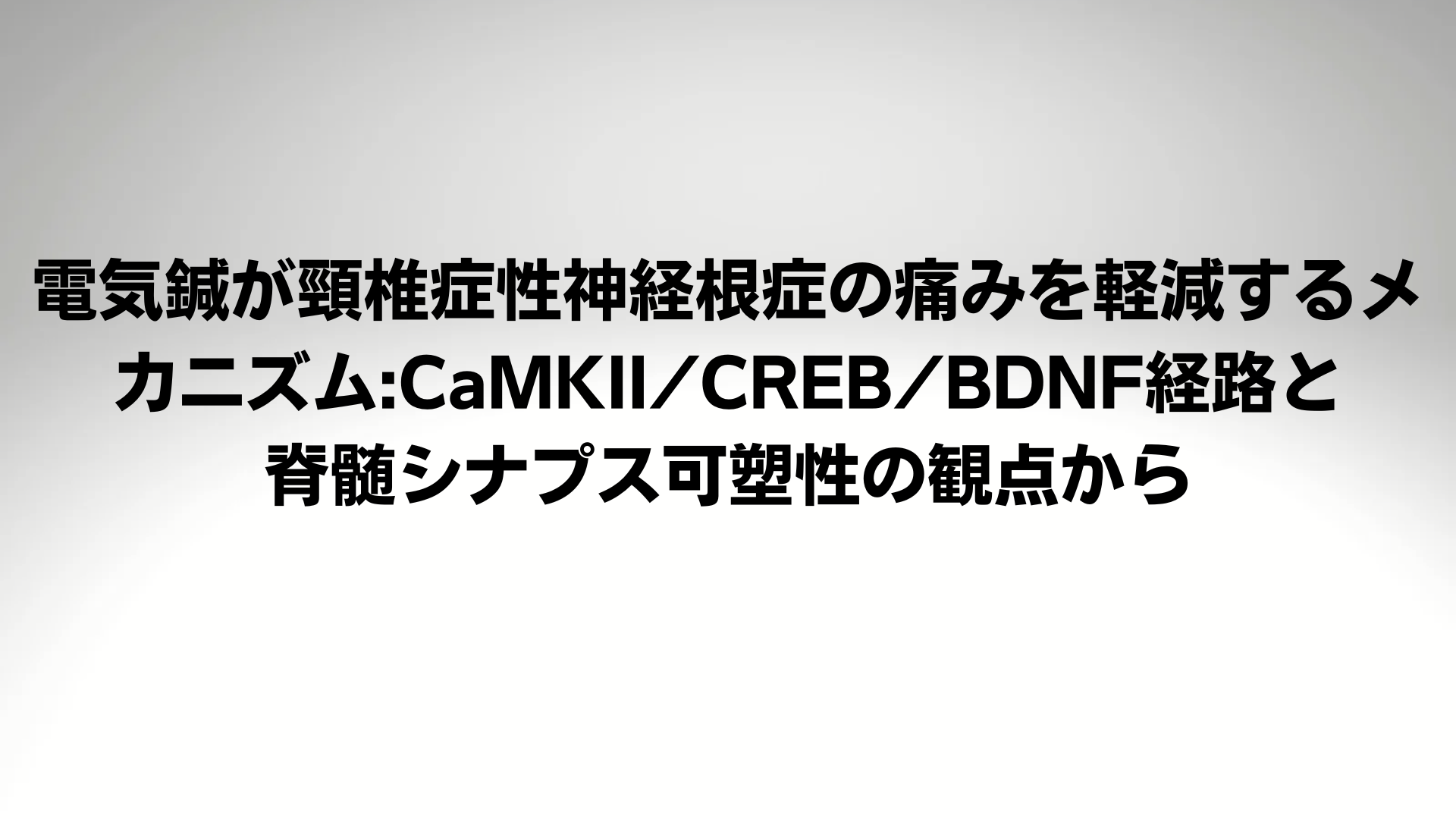
コメント