こんにちは!
陣内です。
今回も論文をご紹介していきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
ただ妄信的にみるのではなく参考程度にみていただければ幸いです。
はじめに

日々の診療で頸部痛の患者さんを診る機会は多いのではないでしょうか。慢性的な痛みだけでなく、急性の寝違えで来院される患者さんも少なくないと思います。今回は、2024年にBMJ Openに掲載された研究を中心に、頸部痛に対する鍼治療の効果について、最新のエビデンスを交えながらご紹介したいと思います。
論文タイトル: “Acupuncture combined with active exercise for acute stiff neck: a protocol for a randomised sham-controlled trial”
掲載誌: BMJ Open 2024; 14(7): e084122
PMID: 39043589
URL:https://bmjopen.bmj.com/content/14/7/e080793.long
頸部痛の臨床的重要性

頸部痛は多くの人々が抱える健康問題です。
特に急性の寝違えは、突然の痛みと可動域制限によって、患者さんの日常生活に大きな支障をきたします。
朝起きたら首が回らなくなったという訴えで来院される患者さんは、早い症状の改善を求めていることが多いですね。
鍼灸分野は得意な領域かなと思います。
注目の研究:10分間の迅速治療プロトコル

今回ご紹介する研究は、中国で実施されているランダム化比較試験のプロトコル論文です。この研究で最も興味深いのは、「10分間で痛みと運動障害を改善する」という、非常に実践的な治療目標を設定している点です。
研究デザインの特徴
本研究では、急性寝違えの患者120名を以下の3つのグループに無作為に割り付けています:
- グループA: 鍼治療+能動的運動療法
- グループB: 偽鍼治療+能動的運動療法
- グループC: 能動的運動療法のみ
この研究デザインの優れている点は、鍼治療の特異的効果と運動療法との相乗効果を明確に評価できることです。偽鍼をコントロールとして設定することで、プラセボ効果を除外した真の治療効果を検証できる設計になっています。
「10分間」という時間設定の意義
臨床現場での観察から、鍼治療と能動的運動を組み合わせることで、短時間で著明な改善が得られるケースが報告されていました。10分という時間設定は、忙しい臨床現場でも実施可能な現実的な治療時間であり、患者さんの待ち時間も最小限に抑えることができます。この「迅速性」は、急性期の痛みで苦しむ患者さんにとって重要な要素といえるでしょう。
鍼治療の痛み緩和メカニズム

鍼治療の鎮痛メカニズムについては、多くの研究が進められています。主なメカニズムとしては以下が挙げられます:
- 内因性オピオイドの放出: エンドルフィンやエンケファリンなどの分泌促進
- ゲートコントロール理論: 脊髄レベルでの痛み信号の抑制
- 神経可塑性の変化: 中枢神経系における痛み処理の変容
- 炎症性物質の調整: サブスタンスPなどの神経伝達物質レベルの変化
実際、中年女性の慢性頸部痛を対象とした研究では、4週間の鍼治療後に痛みの指標(VAS)と頸部障害指数(NDI)が有意に改善し、同時に血中のサブスタンスP濃度も減少したことが報告されています。これは鍼治療の生物学的メカニズムを裏付ける重要なエビデンスといえます。
急性期と慢性期での効果の違い

頸部痛に対する鍼治療の効果を考える際、急性期と慢性期では異なるアプローチが必要になります。
急性期(寝違えなど)
急性期においては、今回ご紹介した研究のように、迅速な痛み緩和と可動域の改善が主要な治療目標となります。鍼治療は薬物療法よりも早く効果が現れる可能性があり、特に運動療法と組み合わせることで相乗効果が期待できます。
臨床実践において、遠位の経穴(例:後渓穴)を用いることで、局所の過敏な組織を直接刺激せずに効果を得られるという利点があります。これは患者さんの治療中の不快感を軽減し、能動的な運動を促進する上でも重要なポイントです。
慢性期
慢性頸部痛に対しては、より長期的な視点での評価が重要になります。2024年の系統的レビューとメタアナリシスでは、鍼治療が慢性頸部痛に対して持続的な効果を持つことが示されました。
具体的には:
- 3ヶ月後の痛み緩和: 標準化平均差(SMD)-0.79という中等度から大きな効果量
- 6ヶ月後の持続効果: 平均差(MD)-18.13という有意な改善の維持
- 機能障害の改善: Northwick Park頸部痛質問票のスコアが3ヶ月後も有意に改善
興味深いことに、偽鍼との比較では統計学的に有意な差は見られませんでしたが、機能的アウトカムについては鍼治療群で有意な改善が認められました。これは、鍼治療の効果が単純な鎮痛効果だけでなく、機能回復にも寄与していることを示唆しています。
エビデンスの全体像:メタアナリシスからの知見
複数のメタアナリシスから、頸部痛に対する鍼治療の効果について一貫した知見が得られています。
2009年の系統的レビューでは、14の研究を対象に9つのメタアナリシスが実施され、そのうち7つで肯定的な結果が得られました。特に、短期的な痛み軽減を主要アウトカムとしたメタアナリシスでは、プール標準化平均差が-0.45(95%信頼区間:-0.69から-0.22)と、鍼治療がコントロール群よりも有意に効果的であることが示されました。
さらに、偽鍼との比較でも、プールSMDが-0.53(95%信頼区間:-0.94から-0.11)と、真の鍼治療の特異的効果が確認されています。
安全性について

治療の有効性と同じくらい重要なのが安全性です。複数の研究で報告されている有害事象の発生率は8.5〜13.8%程度で、そのほとんどが軽度かつ一過性のものでした。
一般的に報告される有害事象としては:
- 刺鍼部位の軽度の痛みや不快感
- 一時的な疲労感
- 軽度の皮下出血
重篤な有害事象の報告は極めて稀であり、適切な訓練を受けた施術者による治療であれば、鍼治療は安全性の高い治療法といえます。
かといって安易に考えるのは危険なので常に安全面に気を配るのは大事なことだと思います。
臨床応用のポイント
これらのエビデンスを臨床に活かす際のポイントをまとめてみましょう。
1. 治療期間と頻度の設定
- 急性期: 週2〜3回、2〜4週間程度
- 慢性期: 週1〜2回、6〜12週間程度の継続治療
ただし、患者さんの反応を見ながら柔軟に調整することが大切です。
2. 経穴の選択
研究では、局所的な経穴と遠位の経穴を組み合わせて使用することが一般的です。急性期には患者さんの痛みを考慮して、遠位穴をメインに使用するのも良い選択肢でしょう。感作されたツボ(sensitized acupoints)を見つけて刺鍼することで、より高い効果が得られる可能性も示唆されています。
研究の中では手三里(LI-10)、後渓(SI-3)、中渚(TE-3)を紹介しています。
3. 運動療法との併用
今回ご紹介した研究プロトコルのように、鍼治療と能動的運動療法を組み合わせることで、相乗効果が期待できます。患者さんに適切な頸部の運動を指導し、治療中や治療後に実施してもらうことが重要です。
4. 患者さんへの説明
鍼治療の効果メカニズムや期待できる効果、安全性について、患者さんに分かりやすく説明することで、治療へのアドヒアランスが向上します。特に慢性期の場合は複数回の治療が必要であることを事前に説明しておくことが大切です。
今後の展望と課題

頸部痛に対する鍼治療の効果について、多くのエビデンスが蓄積されてきていますが、まだ明らかにすべき点も残されています。
さらなる研究が必要な領域
- 最適な刺鍼パラメータ: 刺鍼深度、刺激強度、留鍼時間などの標準化
- 個別化医療: どのような患者さんに特に効果的か(予測因子の同定)
- 長期的効果: 6ヶ月以上の長期フォローアップデータ
- 費用対効果: 医療経済学的な評価
今回ご紹介したBMJ Openの研究プロトコルのような、質の高いランダム化比較試験の結果が公表されることで、これらの疑問に対する答えが得られることを今後期待していきたいと思っています。
まとめ
頸部痛に対する鍼治療は、短期的にも長期的にも一定の効果が認められており、安全性も高い治療法であることが、多くのエビデンスから示されています。特に注目すべき点は以下の点です。
- 急性期の寝違えに対して、鍼治療と運動療法の併用により10分程度で症状改善が得られる可能性があること
- 慢性頸部痛に対して、3〜6ヶ月にわたる持続的な効果が期待できること
- 痛みの軽減だけでなく、機能障害の改善にも寄与すること
- 有害事象は軽度かつ一過性のものがほとんどで、安全性が高いこと
もちろん、鍼治療は万能ではありませんし、すべての患者さんに同じように効果があるわけではありません。
しかし、薬物療法の代替または補完として、また理学療法などの他の非薬物療法と組み合わせて使用することで、患者さんのQOL向上に大きく貢献できる治療選択肢の一つであることや他業種の方との共同でより良いものが提供していく事が出来ていくと思います。。
今後も質の高い研究が蓄積されることで、より効果的で個別化された鍼治療のプロトコルが確立されていくことを期待しています。
先生方の日々の臨床にも、ぜひこれらのエビデンスを活かしていただければと思います。
本記事で紹介した主な文献:
- Sun M, et al. BMJ Open. 2024 (PMID: 39043589)
- Zhang Q, et al. Front Neurol. 2023
- Current Pain and Headache Reports. 2024
- Fu LM, et al. J Altern Complement Med. 2009

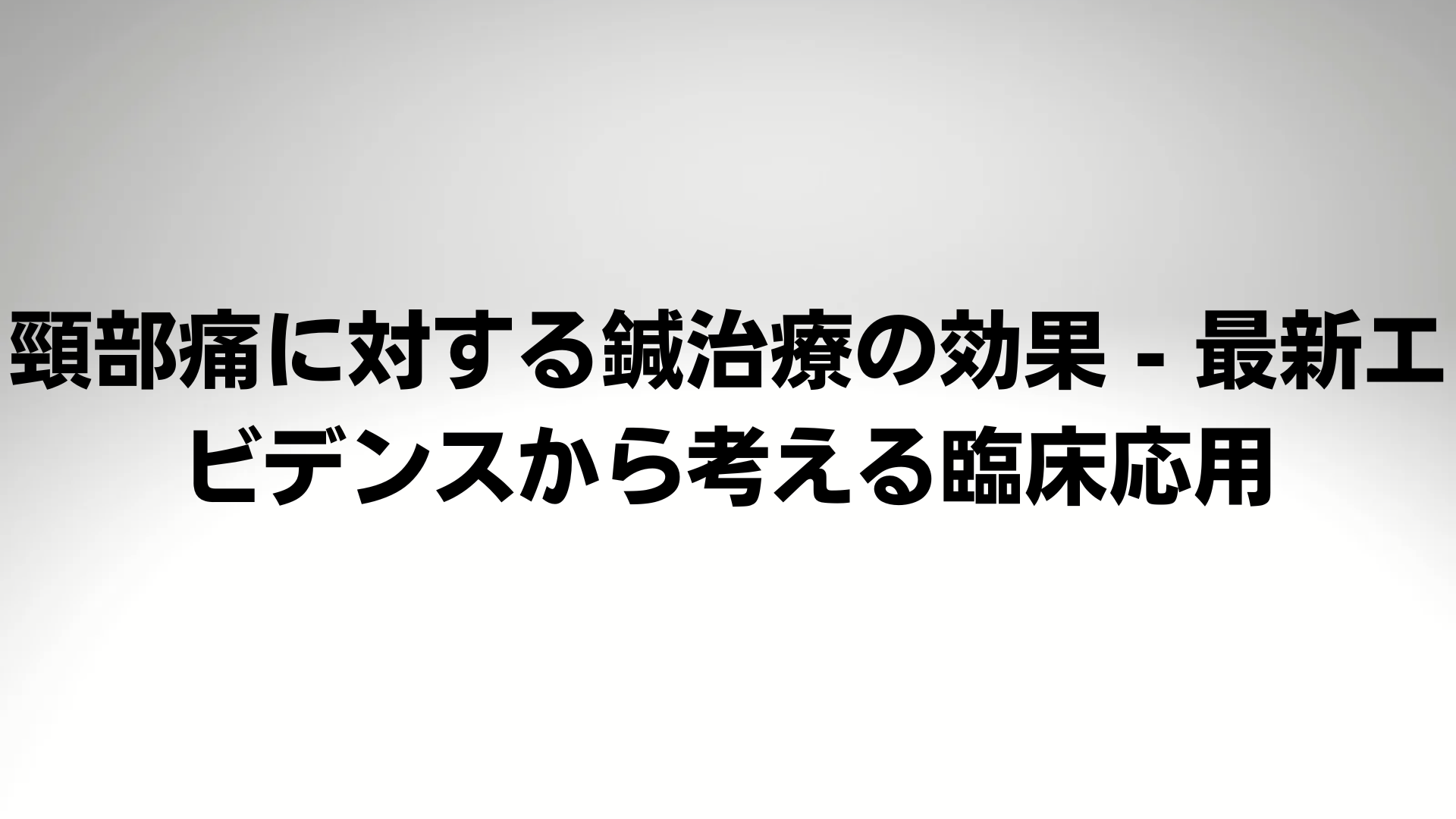
コメント