※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
参考文献はこちら
あくまで私の私見も入っていますので全てを鵜吞みにしないようにしてくださいね‼
宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼
お金持っている人は新品買ってね!
はじめに

スポーツ現場や臨床の場で、肉離れ(骨格筋損傷)に悩まされる患者さんは少なくありません。実は、高齢者のスポーツ関連傷害の約40%を骨格筋損傷が占めているという報告もあるほどです。
(肌感覚ではそんなにないような気もします・・・)
しかし、残念なことに完全に回復するケースは意外と少ないのが現状です。
その大きな理由のひとつが「線維化(fibrosis)」です。これは、損傷した筋肉が修復される過程で、本来の筋線維ではなく硬いコラーゲン組織に置き換わってしまう現象のこと。たとえるなら、破れた絹の服を修繕するときに、柔らかい絹糸ではなく硬いビニール糸で縫ってしまうようなものです。見た目は塞がっても、本来の柔軟性や機能は失われてしまいます。
今回ご紹介する研究では、鍼通電(electroacupuncture:EA)がこの線維化を抑制し、筋肉の修復を促進する可能性が示されました。
その詳しいメカニズムを、できるだけ分かりやすく解説していきます。
研究の概要:どのような実験が行われたのか

研究チームは、ラット(生後12週齢のSprague-Dawley系)の前脛骨筋にカルディオトキシン(CTX)という薬剤を注射することで、急性の筋損傷モデルを作成しました。これは、人間の肉離れに相当する状態を再現する標準的な方法です。
実験グループは以下の3つに分けられました:
- 対照群:生理食塩水を注射された健康な群
- モデル群:筋損傷を起こしたが治療を受けない群
- 鍼通電群:筋損傷後に鍼通電治療を受けた群
鍼通電治療は、「腎兪(じんゆ)」と「後三里(こうさんり)」というツボに鍼を刺し、100Hzの周波数で2mAの電気刺激を20分間流すという方法で行われました。これを1日1回、7日間または14日間継続したのです。
鍼通電の主な効果:炎症を抑え、線維化を防ぐ

1. 炎症反応の調節
筋肉が損傷すると、まず炎症反応が起こります。これは本来、組織を修復するための必要なプロセスですが、過剰になると逆効果です。
研究の結果、鍼通電治療を受けたグループでは:
- 炎症性サイトカイン(IL-6、IL-4、TNF-α)が有意に減少
- 抗炎症性サイトカイン(IL-33、IL-10)が増加
これは、炎症の「火加減」を適切に調整できたということです。料理で例えるなら、強火で焦がさずに、ちょうどいい火加減で調理できた状態といえるでしょう。
2. マクロファージの変換を促進
ここで重要な役割を果たすのが「マクロファージ」という免疫細胞です。マクロファージには主に2つのタイプがあります:
- M1型マクロファージ:炎症を起こす「戦闘モード」の細胞。損傷初期に必要だが、長期化すると組織にダメージを与える
- M2型マクロファージ:組織修復を助ける「平和維持モード」の細胞。傷を治し、再生を促進する
鍼通電治療によって、M1型からM2型への変換が促進されることが分かりました。つまり、「戦う兵士」を「復興支援者」に変えることができたのです。これにより、破壊的な炎症から建設的な修復へと、体内の環境がシフトしたわけですね。
3. コラーゲン沈着と線維化の抑制
マッソン染色という特殊な染色法を用いた観察では、鍼通電群において筋組織内のコラーゲン沈着が明らかに減少していました。
さらに、免疫組織化学的検査により、線維化に関連するタンパク質(Axin2、コラーゲンII、β-カテニン)の発現も有意に低下していることが確認されました。
これは、鍼通電が「硬い組織への置き換わり」を防ぎ、本来の柔軟な筋肉への回復を促したことを意味します。
メカニズムの深掘り:TGF-β1シグナル経路の調節

では、鍼通電はどのようにして、これらの効果を生み出しているのでしょうか?研究チームは、その鍵が「TGF-β1/Smad3/p38/ERK1/2シグナル経路」にあることを突き止めました。
TGF-β1とは?
TGF-β1(トランスフォーミング成長因子β1)は、線維化を引き起こす中心的な因子です。腎臓、肝臓、肺、そして筋肉など、さまざまな臓器の線維化に関与しています。
筋肉においては、TGF-β1は:
- 筋芽細胞の増殖を抑制する
- 筋細胞を筋線維芽細胞(コラーゲンを大量に作る細胞)に変化させる
- MAPKシグナル伝達を活性化し、最終的に線維化を促進する
鍼通電による調節効果
研究では、ウエスタンブロット法を用いて各種タンパク質の発現レベルを測定した結果:
鍼通電群では:
- TGF-β1の発現が減少
- MMP-2(マトリックスメタロプロテアーゼ2)とMMP-7の発現が減少
- p38の活性化が低下
- 一方で、ERK1/2とSmad3の活性化は増加
この結果が意味することは、鍼通電がTGF-β1を中心とした線維化促進経路を抑制しながら、同時に組織修復に有利な経路を活性化しているということです。
MMPsの役割について
MMP-2やMMP-7は「マトリックスメタロプロテアーゼ」と呼ばれる酵素の一種で、細胞外マトリックスを分解する働きがあります。
一見すると、組織の分解を助ける酵素が減少するのは良いことのように思えますが、実際には複雑です。これらの酵素は:
- 筋衛星細胞の移動や分化を助ける
- 新しい筋繊維の形成を促進する
- 血管新生を支援する
しかし、その一方で、M1型マクロファージから分泌されるとき、過剰なMMPsは線維化を悪化させることもあります。研究では、鍼通電によってこのバランスが適切に調整されたと考えられます。
臨床応用への示唆:どう活かすべきか

治療タイミングの重要性
この研究では、損傷後24時間から治療を開始していますが、7日間の治療よりも14日間の治療でより顕著な効果が認められました。
これは、鍼通電治療の効果が「継続的な介入」によって蓄積されることを示唆しています。臨床では、急性期から一定期間継続して治療を行うことが重要といえるでしょう。
刺激パラメータについて
今回使用された刺激条件は:
- 周波数:100Hz
- 強度:2mA
- 時間:20分/回
- 頻度:1日1回
高周波(100Hz)の刺激が選択されていますが、これは組織修復や炎症調節に適していると考えられます。ただし、個々の患者さんの状態に応じて調整する必要があることは言うまでもありません。
取穴について
研究では「腎兪」と「後三里」が選択されました。これらは:
- 腰部と局所の両方からアプローチする組み合わせ
- 下肢の気血循環を改善する効果が期待できる
- 筋肉の修復に関与する経絡理論に基づく選択
臨床では、損傷部位に応じて取穴を調整することになりますが、局所と遠隔を組み合わせるという原則は参考になるでしょう。
作用機序のまとめ:全体像を理解する
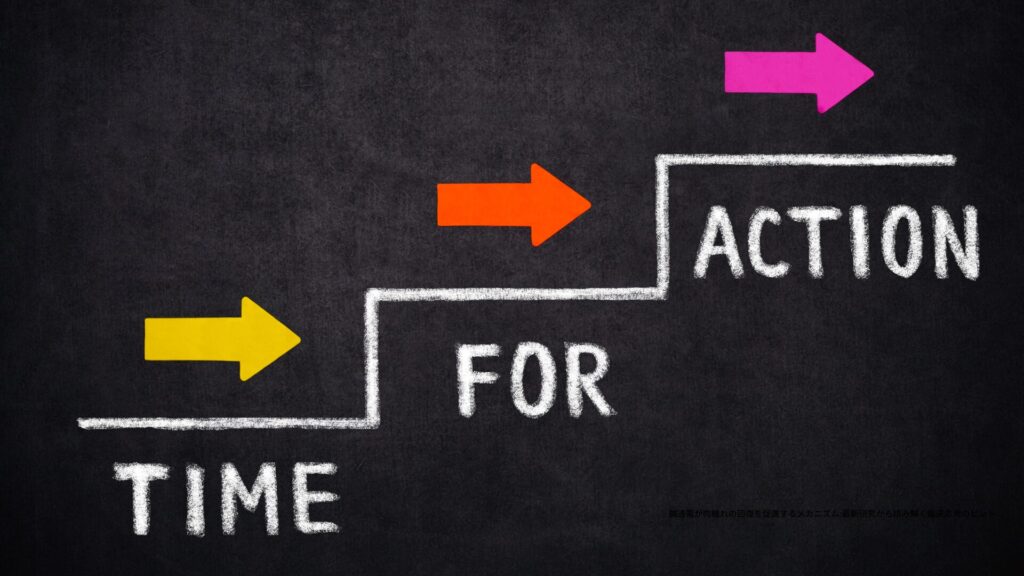
鍼通電による肉離れの回復促進メカニズムを、一連の流れとして整理してみましょう:
- 鍼通電刺激
- 炎症性サイトカインの減少、抗炎症性サイトカインの増加
- マクロファージのM1型からM2型への変換促進
- TGF-β1/Smad3/p38/ERK1/2経路の調節
- TGF-β1発現↓(線維化促進因子の減少)
- p38活性化↓(炎症シグナルの抑制)
- ERK1/2活性化↑(細胞増殖・生存促進)
- コラーゲン沈着の抑制、線維化の軽減
- 筋繊維の再生促進、機能回復
この一連のプロセスが、鍼通電という物理的刺激によって引き起こされるというのは、大変興味深い知見です。
今後の課題と展望
この研究は、動物実験レベルでの基礎的なエビデンスを提供してくれました。しかし、臨床応用に向けては、まだいくつかの課題があります:
1. ヒトでの検証が必要
ラットでの結果が、そのままヒトに当てはまるとは限りません。筋肉の構造、修復過程、代謝速度などに種差があるためです。ヒトを対象とした臨床試験が待たれます。
2. 至適刺激条件の探索
周波数、強度、時間、頻度など、刺激パラメータの組み合わせは無数にあります。最も効果的な条件を見つけるためには、さらなる研究が必要です。
3. 他の治療法との併用効果
理学療法、栄養療法、薬物療法など、他の治療法と組み合わせることで、さらに効果を高められる可能性があります。
4. 個別化医療への応用
年齢、性別、損傷の程度、基礎疾患の有無などによって、最適な治療法は異なるはずです。個々の患者さんに合わせた治療プロトコルの確立が求められます。
研究の限界について
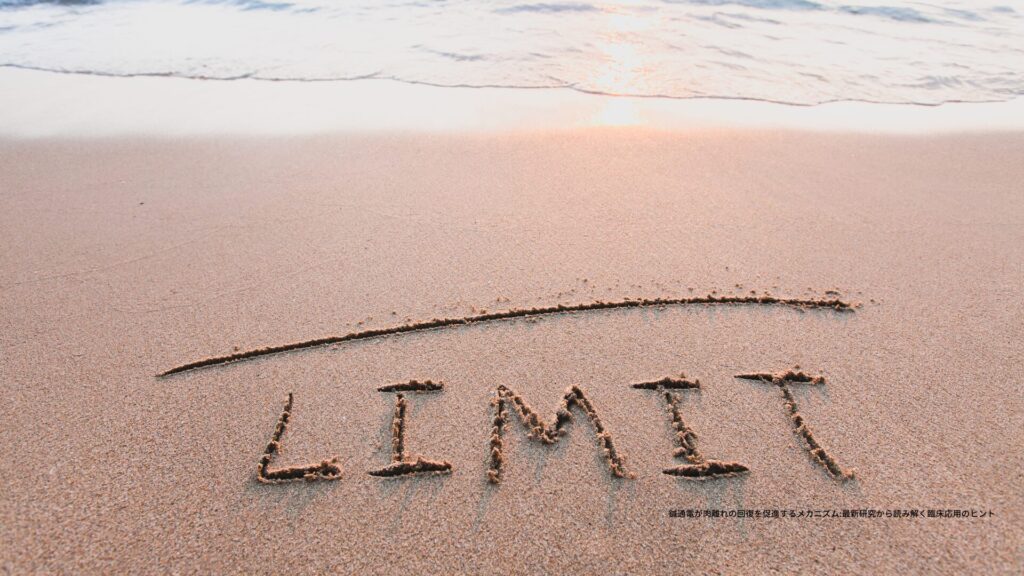
著者らも認めているように、この研究にはいくつかの限界があります:
- TGF-β経路の阻害剤を併用した実験が行われていないため、鍼通電の効果が完全にこの経路を介したものかは断定できない
- サンプルサイズが比較的小さい(各群n=6)
- 長期的な予後(例えば6ヶ月後、1年後の状態)については検討されていない
これらの点を踏まえた上で、結果を解釈する必要があります。
まとめ鍼灸師としてどう受け止めるか
この研究から、私たち臨床家が学ぶべきことは何でしょうか?
第一に、鍼通電には科学的に検証可能な生物学的メカニズムがあるということです。「なんとなく効く」ではなく、炎症調節、マクロファージの変換、シグナル経路の調整といった具体的なプロセスを介して効果を発揮していることが示されました。
第二に、治療のタイミングと継続性の重要性です。急性期から介入し、一定期間継続することで、線維化という不可逆的な変化を予防できる可能性があります。
第三に、作用機序の理解が治療の最適化につながるということです。どのような生物学的プロセスを調整しているのかを理解することで、より効果的な刺激条件や併用療法を考案できるでしょう。
肉離れからの完全回復が難しいとされてきたこれまでの常識を、鍼通電が変える可能性を秘めています。もちろん、動物実験の結果をそのまま臨床に適用することはできませんが、今後のヒトでの研究に大きな期待が持てる内容でした。
私たち鍼灸師や他の職種である理学療法士、スポーツトレーナーなど、筋骨格系の治療に携わる専門家にとって、この研究は重要な示唆を与えてくれています。
エビデンスに基づきながら、個々の患者さんに最適な治療を提供していく姿勢が、ますます重要になってくるでしょう。
参考文献
主要論文: Han H, Li M, Liu H, Liu H. Electroacupuncture regulates inflammation, collagen deposition and macrophage function in skeletal muscle through the TGF-β1/Smad3/p38/ERK1/2 pathway. Experimental and Therapeutic Medicine. 2021;22(6):1089. doi: 10.3892/etm.2021.10523
関連文献:
- Liao CH, et al. Ibuprofen inhibited migration of skeletal muscle cells in association with downregulation of p130cas and CrkII expressions. Skeletal Muscle. 2019;9:23.
- Mahdy MAA. Skeletal muscle fibrosis: An overview. Cell and Tissue Research. 2019;375:575-588.
- Delaney K, et al. The role of TGF-β1 during skeletal muscle regeneration. Cell Biology International. 2017;41:706-715.
- Tidball JG. Mechanisms of muscle injury, repair, and regeneration. Comprehensive Physiology. 2011;1:2029-2062.
- Wehling-Henricks M, et al. Arginine metabolism by macrophages promotes cardiac and muscle fibrosis in mdx muscular dystrophy. PLoS One. 2010;5:e10763.
- Chen X, Li Y. Role of matrix metalloproteinases in skeletal muscle: Migration, differentiation, regeneration and fibrosis. Cell Adhesion & Migration. 2009;3:337-341.
Note: 本記事は、査読済みの科学論文に基づいて作成されていますが、実際の臨床応用にあたっては、個々の患者さんの状態を十分に評価し、適切な判断のもとで実施してください。

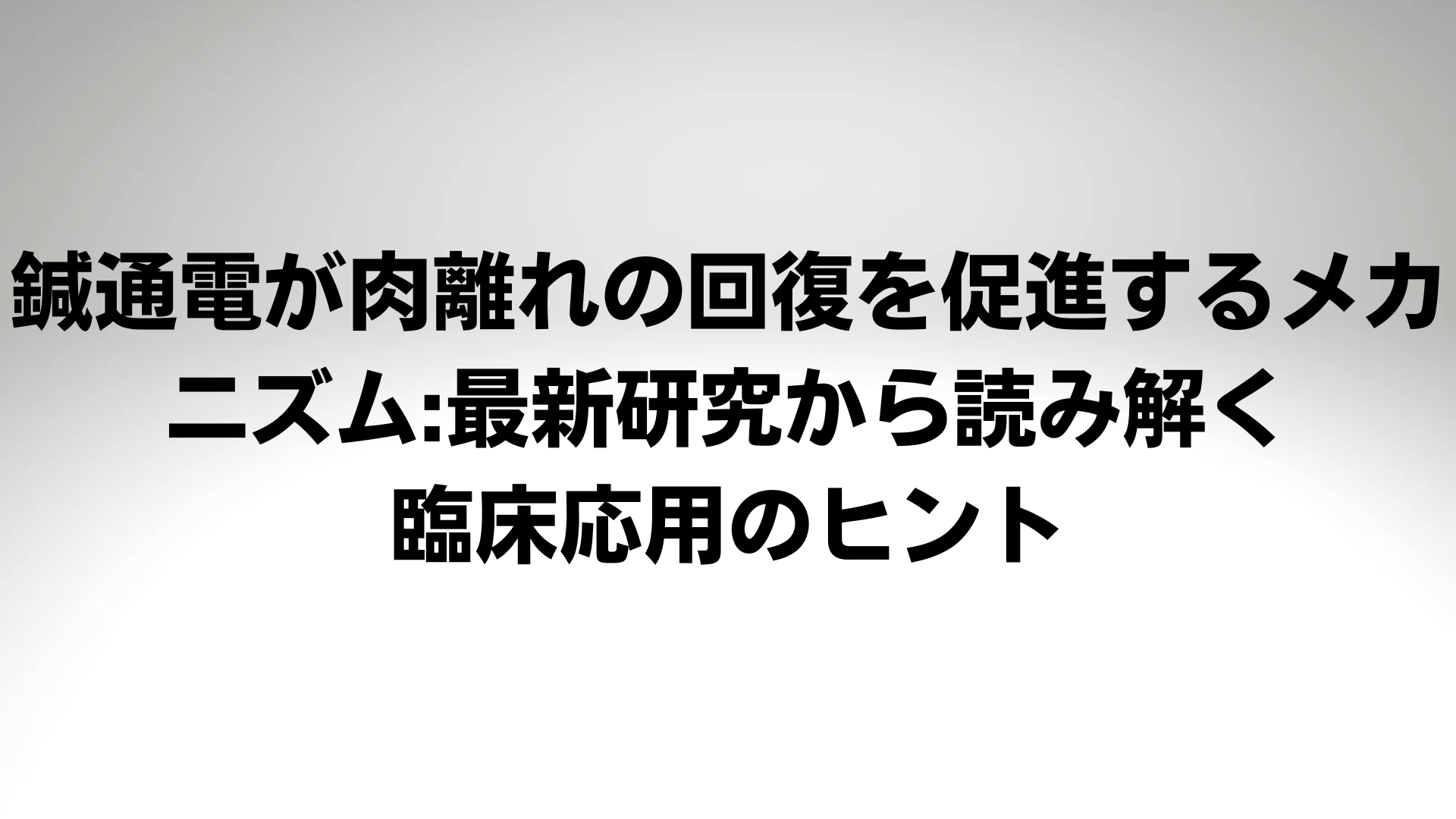
コメント