※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
今回は鍼灸医学における経絡現象の科学的基盤について、最新の研究成果をご紹介したいと思います。
Ma博士らの研究は、経絡に沿ったトレーサー移動という興味深い現象の背後にある生理学的メカニズムを明らかにしています。特に、軸索反射と一酸化窒素(NO)、そして神経ペプチドが果たす役割について、わかりやすく解説していこうと思います。
実際のリンクはこちら
ぶっちゃけ経絡現象とかはめちゃくちゃ苦手ですw
私の中ではキムボンハン学説で止まっていますw
いつの時代やねんってツッコミきそうですが経絡の解明に軸索反射がどうかかわってくるかが非常に興味深いです。ちなみにこの論文にぶち当たったのは軸索反射の論文を探していたところでした。
さて内容に入っていきましょう♪
経絡現象とは何か

伝統的な東洋医学では、経絡という「気」の流れる道が存在すると考えられてきました。しかし、私たち現代医学に携わる者にとって、この「見えない経路」をどう理解すべきか、長年の課題でしたよね。
興味深いことに、国際的な複数の研究グループが、放射性トレーサーや蛍光色素を経穴(ツボ)に注入すると、体表面の線状経路に沿って移動する現象を確認しています。これは単なる血管やリンパ管の流れとは異なる、独特のパターンを示すのです。
トレーサー溶液とは?
ここで使われている「トレーサー溶液」について、少し詳しく説明しておきましょう。
トレーサーとは、文字通り「追跡できる物質」のことです。経絡研究では、主に以下の2種類が使用されてきました:
1. 放射性トレーサー
- テクネチウム99m(99mTc):最も頻繁に使用される核医学用トレーサー
- 過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc-pertechnetate)として使用
- 投与量:300-500 μCi、溶液量:約0.05-0.125 ml
- ガンマカメラで体表面の移動を可視化できる
- 移動速度:約2.5 cm/分で、約11 cmの距離を移動
- 他の放射性同位体(研究比較用)
- タリウム201(201Tl-塩化タリウス):0.3 ml
- ヨウ素131(131I-ヨウ化ナトリウム):0.05 ml
- レニウム硫化物(99mTc標識):0.125 ml
興味深いことに、これらの中で99mTc-pertechnetateのみが、経穴注入後に明確な線状移動パターンを示したのです。他のトレーサーは主にリンパ節に集積し、線状の経路を形成しませんでした。
2. 蛍光トレーサー
- フルオレセインナトリウム(fluorescein sodium)
- 投与量:0.1-1.0 mlの溶液として注入
- 可視光で直接観察可能(黄緑色の蛍光を発する)
- 人間の前腕のPC6(内関)穴に注入した研究では、79%(15/19例)で心包経に沿った線状移動が観察された
- 24時間後でも蛍光ラインが観察可能
- インドシアニングリーン(indocyanine green)
- フルオレセインと比較研究されたが、線状移動パターンは示さなかった
- アルシアンブルー
- 組織染色用トレーサー
- 低水圧抵抗チャネルの可視化に使用
トレーサー溶液が教えてくれること
なぜ特定のトレーサーだけが経絡様の移動を示すのでしょうか?これは非常に重要な手がかりです。
血管に直接注入した場合、トレーサーは瞬時に広がり、10秒以内に消失します。しかし、経穴の皮下に注入すると、ゆっくりと(2.5 cm/分)線状に移動するのです。これは、血管内の血流でもリンパ流でもない、別のメカニズムが働いていることを示しています。
また、レニウム硫化物(リンパ管に親和性が高い)は、注入90分後に腋窩リンパ節で検出されましたが、線状の皮膚経路は形成しませんでした。このことから、研究者たちは、経絡様のトレーサー移動は「静脈でもリンパ管でもない経路」を通っていると結論づけたのです。
注入方法と刺激の重要性
ここで極めて重要な点があります。すべてのトレーサー実験では、0.05 mlから1.0 mlという、比較的大きな容積の溶液を経穴に注入しています。
この溶液注入は:
- 針刺入による機械的刺激
- 溶液の圧力による追加刺激
という二重の刺激となり、通常の鍼刺激よりもはるかに強力な機械的刺激を組織に与えます。この強い刺激が、軸索反射を強力に誘発する鍵となっているのです。
実際、皮内注射による高張食塩水の注入でも、軸索反射による血管拡張反応が観察されており、その反応はヒスタミンやサブスタンスPに対する反応と同様に、局所麻酔薬(リグノカイン)によって抑制されることが確認されています。これは、神経および血管メカニズムが関与していることを示しています。
軸索反射という鍵

ここで重要なのが「軸索反射」という概念です。これを理解するために、身近な例え話をさせてください。
道路の分岐点を想像してみてください。通常、情報は「末梢→本社(脊髄・脳)→末梢」という経路で伝わります。これは、地方の営業所から本社に報告が上がり、本社が指示を出して、別の営業所が動く、というプロセスに似ています。
しかし、軸索反射では、同じ神経線維の分岐点で信号が直接分かれて伝わるのです。道路で言えば、Y字路で「本社に向かう道」と「隣町に向かう道」に分岐している状態です。刺激という「配達物」が分岐点に来ると、配達員は荷物を二つに分けて、一つは本社(中枢)へ、もう一つは直接隣町(周辺組織)へ届けるのです。
つまり、刺激を受けた神経の枝が、脊髄に情報を送ると同時に、その近くの別の枝にも信号を送り、血管拡張や神経ペプチドの放出を引き起こすわけです。これが「反射」と呼ばれながらも、中枢神経を経由しない「軸索反射」の特徴なのです。
Ma博士らの研究によれば、経穴にトレーサー溶液を注射すると、注射による機械的刺激と溶液による追加刺激が組み合わさって、通常の鍼刺激よりもはるかに強力な軸索反射が誘発されるとのことです。
軸索反射のメカニズム:NOと神経ペプチドの役割

さて、ここからが本題です。軸索反射が起きると、何が起こるのでしょうか?
一酸化窒素(NO)の中心的役割
研究によると、経穴/経絡領域には、非経穴領域と比較して、神経線維、血管、毛包、汗腺が豊富に存在しています。そして、これらの組織には、内皮型および神経型のNO合成酵素(NOS)が高濃度で発現しているのです。
手技鍼、電気鍼(EA)、経皮的電気神経刺激(TENS)、電熱刺激などが経穴に加えられると、NO放出が一貫して増加することが確認されています。特に電気鍼では、ラットの経穴/経絡においてNOレベルの上昇と、TRPV1(侵害受容に関わる受容体)を伴うNOS発現の増強が観察されています。
人間を対象とした皮膚マイクロダイアリシス研究でも、電気鍼により経穴の皮下組織でNO-cGMP放出が増加することが報告されています。
神経ペプチドの協奏作用
NOだけではありません。軸索反射には、複数の神経ペプチドが関与しています。
**カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)**は、特に重要な役割を果たします。CGRPはTRPV1受容体の活性化を介して放出され、強力な血管拡張作用を持っています。
他にも、**サブスタンスP(SP)やニューロペプチドY(NPY)**といった神経伝達物質が、刺激誘発性の軸索反射に関与していることが示されています。
これらの生体分子は、まるでオーケストラのように協調して働き、局所の血流を増加させるのです。
トレーサー移動の真相
ここで全体像が見えてきましたね。経穴にトレーサー溶液を注射すると:
- 機械的刺激により軸索反射が誘発される
- NOと神経ペプチドのレベルが上昇する
- 血管拡張と局所血流の増加が起こる
- 経穴/経絡では特に高レベルの血流増加が生じる
- この血流の「フレア(広がり)」に乗って、トレーサーが皮膚・皮下組織内を線状経路に沿って移動する
つまり、経絡に沿ったトレーサーの移動は、軸索反射によって引き起こされた血流の変化を可視化したものと考えられるのです。
解剖学的基盤

では、なぜ経穴/経絡で特にこのような現象が起きやすいのでしょうか?
解剖学的研究により、経穴/経絡領域には以下の特徴があることが明らかになっています:
- 小径神経線維の高密度分布:無髄C線維と薄髄Aδ線維が豊富
- 血管の高密度分布:NOSや神経ペプチドに富む
- 毛包と汗腺の集積
これらの構造が、NOシグナル分子や神経ペプチドを介した軸索反射の「構造的基盤」として機能しているのです。
実際、NADPH diaphorase陽性ニューロン(NOを産生する神経細胞のマーカー)が、足三里(ST36)穴に分布しており、その一部は脊髄L4からS1のlamina IXから投射されていることが示されています。
電気的特性との関連
経穴の低電気抵抗という特性も、同じメカニズムで説明できます。
皮膚の電気抵抗は交感神経系の活動に依存しており、交感神経機能の遮断により皮膚抵抗が増加することが知られています。
Ma博士らのレビューでは、L-アルギニン由来のNO合成とノルアドレナリン作動性伝達が皮膚電気伝導度を調節し、経穴/経絡の低抵抗特性に寄与していることが示唆されています。
実験的に、経穴での3H-ノルエピネフリン(NE)の合成・放出は、外因性NOドナーの存在により促進され、NO合成阻害剤により抑制されることが確認されています。
電気鍼による効果増強
ここで、電気鍼(EA)の特別な効果について触れておきましょう。
研究では、EAが経穴でプレプロエンケファリン(PPE)mRNAの発現を増加させることが示されています。これは脳幹の吻側腹外側延髄(rVLM)という、血圧調節に重要な領域で観察されました。
2Hz、1-2mAの低頻度・低強度のEAを30分間適用すると、正常血圧のラットでもPPE mRNAが増加しました。これは、EA刺激が体性神経を活性化し、血圧変化がなくてもPPE mRNA合成を誘導できることを示しています。
オピオイド系とGABA系の両方が、EAによる心血管反射の調節に関与していることも明らかになっています。
TRPV1受容体の重要性

TRPV1(transient receptor potential vanilloid type-1)受容体は、鍼刺激の応答チャンネルとして機能することが複数の研究で示されています。
マウスの末梢および中枢神経系において、TRPV1が鍼刺激に応答することが確認されており、EAは経穴/経絡のTRPV1を伴うNOS発現を増強します。
この受容体は、侵害受容性C線維に主に発現しており、熱刺激や機械的刺激、さらには炎症性メディエーターによって活性化されます。TRPV1の活性化がCGRP放出を引き起こし、血管拡張と軸索反射に寄与するというわけです。
臨床的意義
これらの知見は、私たちの臨床実践にとって何を意味するのでしょうか?
1. 刺激強度の最適化
軸索反射を効果的に誘発するには、適切な刺激強度が必要です。あまりに弱い刺激では効果が限定的で、強すぎると不快感や有害反応のリスクが高まります。
2. 電気鍼のパラメータ選択
研究では、2-10Hzの低周波電気刺激が、100Hzの高周波刺激よりも炎症性疼痛や神経障害性疼痛の抑制に効果的であることが示されています。これは、低周波刺激がオピオイド系やセロトニン系の活性化に優れているためと考えられます。
3. 経穴選択の科学的根拠
経穴が単なる「伝統的な概念」ではなく、神経線維、血管、NOSが豊富な解剖学的実体を持つことが示されました。これは、経穴選択に科学的根拠があることを支持しています。
今後の展望と課題
Ma博士らの研究は、経絡現象の理解に大きく貢献していますが、まだ解明すべき点も多く残されています。
さらなる研究が必要な領域
- 経穴間の連絡機構:経穴が線状につながる「経絡」の形成メカニズムは、まだ完全には解明されていません
- 個体差と病態による変化:健常者と疾患患者で、軸索反射の応答がどう異なるのか
- 長期効果のメカニズム:EAが60分以上持続する効果を示すのはなぜか
- 最適刺激プロトコル:疾患や治療目的に応じた、最適な刺激パラメータの確立
臨床応用への期待
これらの基礎研究の成果が、より効果的な鍼灸治療プロトコルの開発につながることが期待されます。特に:
- 慢性疼痛管理における鍼灸の位置づけの明確化
- 自律神経調節を目的とした治療戦略の最適化
- 鍼灸と従来治療の効果的な併用法の確立
まとめ
経絡に沿ったトレーサー移動という興味深い現象の背後には、軸索反射という明確な生理学的メカニズムが存在します。経穴への刺激により:
- 軸索反射が誘発され
- NOと神経ペプチドが放出され
- 局所血流が増加し
- その血流の変化が経絡様の線状パターンを形成する
経穴/経絡領域は、小径神経線維、血管、NOSが豊富という解剖学的特徴を持ち、これが低電気抵抗や伝播感覚、トレーサー移動といった経絡現象の構造的基盤となっています。
鍼灸医学の伝統的概念と現代の神経科学が融合することで、より科学的根拠に基づいた治療法の発展が期待されます。私たち鍼灸師は、この知識を活かして、患者さんにより良い医療を提供できるよう、引き続き学びを深めていきたいものですね。
参照論文
Ma, S. X. (2024). Stimuli-induced nitric oxide and neuropeptides mediated axon reflexes contribute to tracers along meridian pathways. Current Topics in Medicinal Chemistry, 24(5), 393-400. DOI: 10.2174/0115680266260220240108114337. PMCID: PMC11111350
関連重要文献
- Chen, J. X., & Ma, S. X. (2005). Effects of nitric oxide and noradrenergic function on skin electric resistance of acupoints and meridians. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11, 423-431.
- Ibrahim, T. S., Chen, M. L., & Ma, S. X. (2011). TRPV1 expression in acupuncture points: Response to electroacupuncture stimulation. Journal of Chemical Neuroanatomy, 41, 129-136.
- Lim, N., & Ma, S. X. (2009). Responses of nitric oxide-cGMP releases in acupuncture point to electroacupuncture in human skin in vivo using dermal microdialysis. Microcirculation, 16, 434-443.
- Li, T., Tang, B. Q., Zhang, W. B., Zhao, M. Y., Hu, Q. C., & Ahn, A. (2021). In-vivo visualization of pericardium meridian with fluorescent dyes. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2021, 5581227.

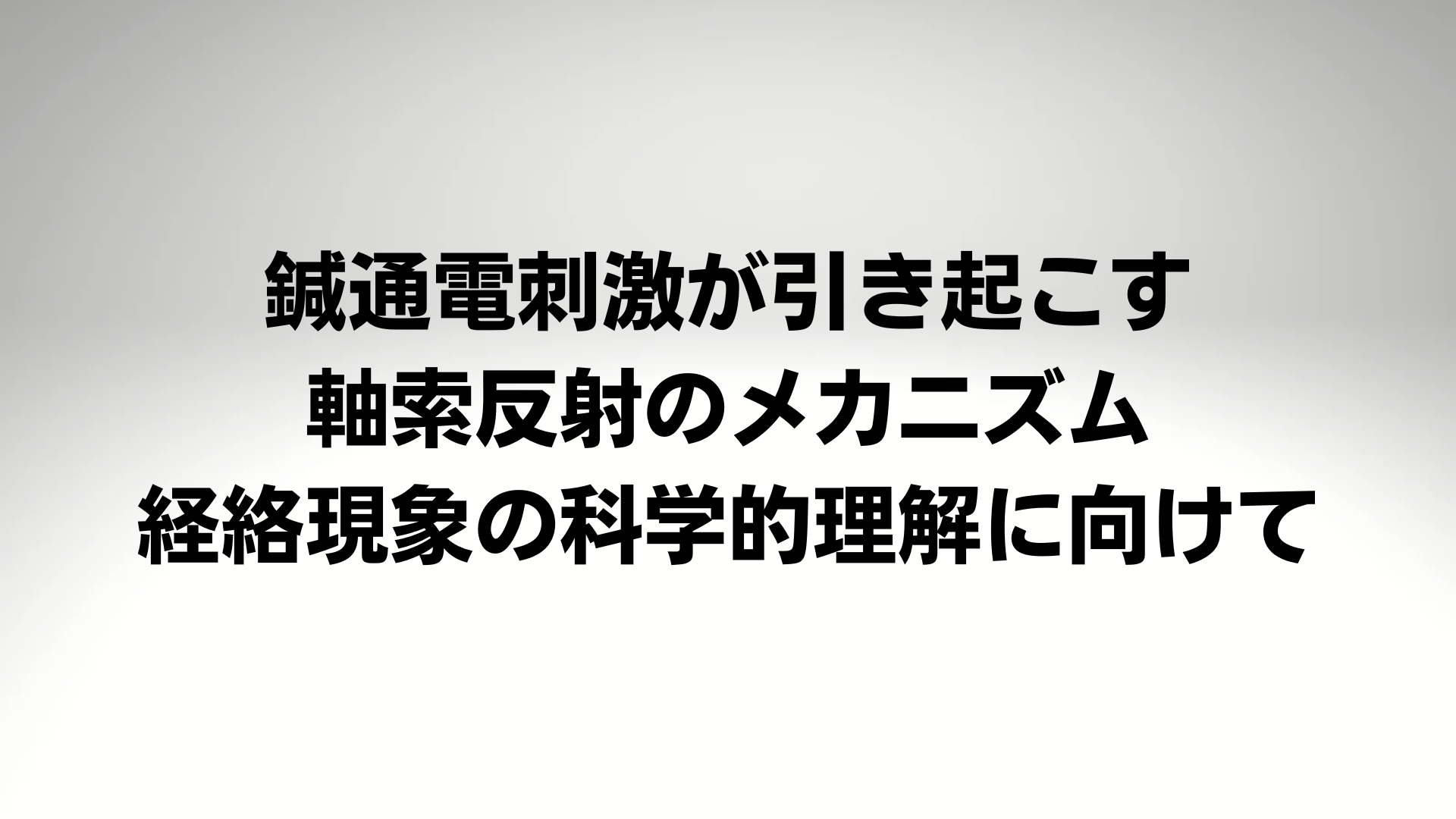
コメント