※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
参考文献はこちら
前回の経絡現象の記事が思いのほかみられていたのと私自身も気になったので少し深掘り目的で調べてみました。
今回も内容をすべて鵜吞みにするのはやめてくださいね!
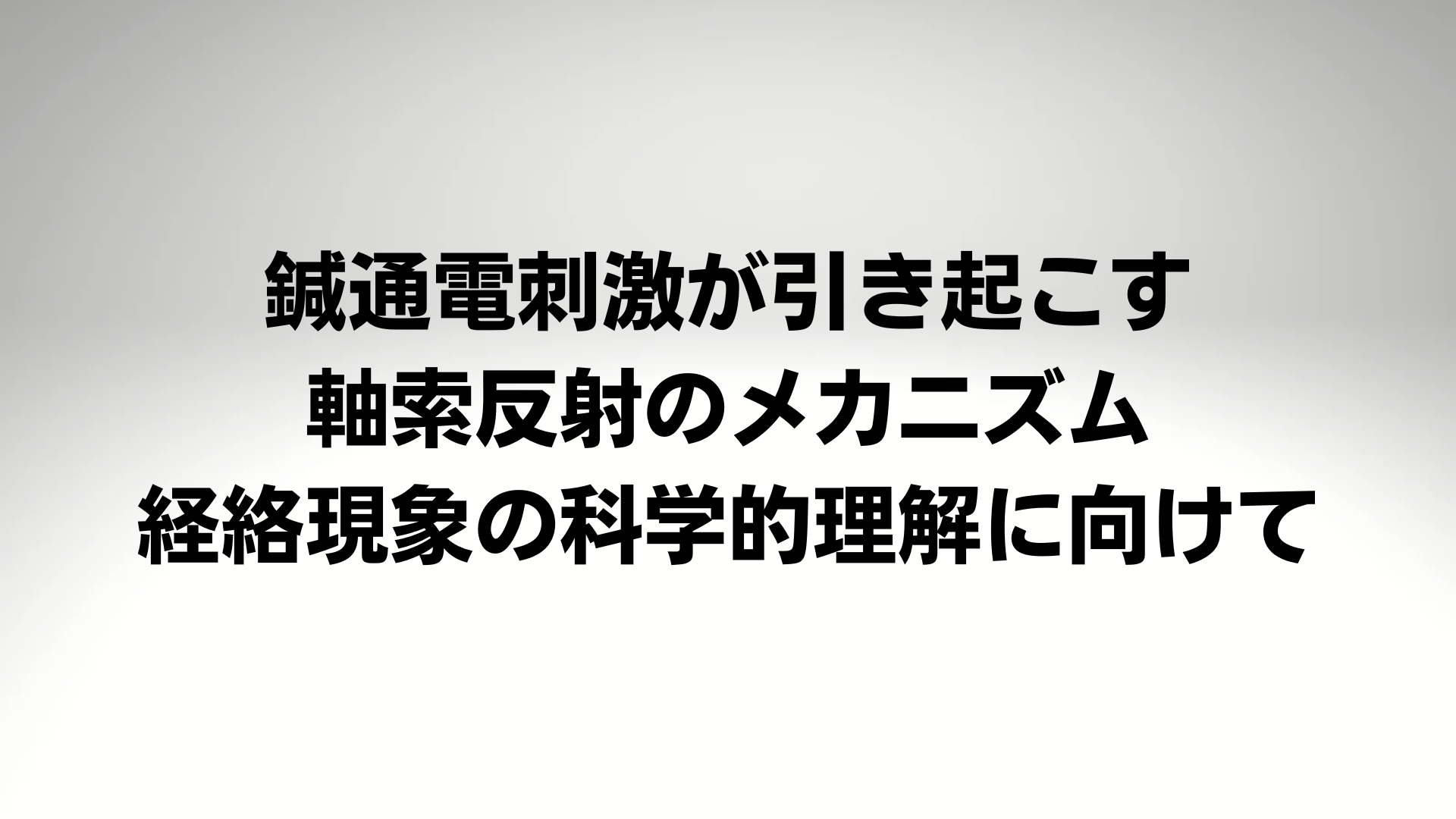
宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼
お金持っている人は新品買ってね!
はじめに

鍼灸医学における「経絡」という概念は、何千年もの間、東洋医学の治療体系の根幹の一つを成してきました。
しかし、その実体や作用機序については、現代科学においても完全には解明されていない領域です。
近年、分子生物学や神経科学の進歩により、経絡に沿った感覚伝播現象のメカニズムに関する興味深い知見が蓄積されてきています。
本稿では、2024年にJournal of Integrative Medicineに掲載されたMa博士らの総説論文を中心に、経絡に沿った感覚伝播現象(PSCP: Propagated Sensation along Channel Pathways)の神経生物学的基盤について考察していきます。
経絡感覚伝播現象(PSCP)とは

PSCPの臨床的特徴
鍼灸治療を受けたことがある方なら、鍼を刺した局所だけでなく、そこから線状に広がっていく独特な感覚を経験されたことがあるかもしれません。
この現象は「経絡感覚伝播(PSCP)」と呼ばれ、国際的にも多くの研究者によって報告されています。
PSCPは、主に以下のような特徴を持つと考えられています:
- 手足の末端にある遠位経穴(井穴)への刺激で誘発されやすい
- しびれ感、圧迫感、重さ、温かさ、放散する感覚などとして感じられる
- 伝統的な経絡の経路に沿って進行する
- 神経の走行とは必ずしも一致しない
- パルス電気刺激を受けた63,228名の被験者のうち、12〜24%でPSCPが報告された
(実際おきますよね!)
興味深いことに、この感覚は古代中国の医学書『黄帝内経』にも「鍼を刺すと、針が街(経絡)に沿って動くように感じる」と記述されているそうです。
数千年の時を経て、現代の研究者たちがこの現象の科学的基盤を探求しているのは、医学史における一つの大きなロマンと言えるでしょう。
PSCPと「得気」感覚の関連
臨床において重要な「得気(De Qi)」という感覚も、PSCPと密接に関連していると考えられています。得気は鍼灸治療の効果を左右する重要な要素とされており、より強い得気感覚が得られることが、治療効果の向上につながる可能性が示唆されています。
経穴の生理学的特性

経穴の解剖学的特徴
経穴が他の皮膚領域と何か異なる特性を持つのかという問いは、長年にわたって研究されてきました。近年の形態学的研究により、経穴および経絡には以下のような解剖学的特徴があることが示されています:
- 神経線維および神経幹の密度が高い
- 血管の分布が豊富である
- 毛包の数が多い
- 汗腺の密度が高い
これらの構造的特徴は、経穴が単なる抽象的概念ではなく、実際に組織学的な特性を持つ領域であることを示唆しています。
経穴における電気的特性
さらに興味深いのは、経穴が低電気抵抗という物理的特性を示すことです。これは1950年代から知られており、日本の研究者である中谷義雄博士による「良導絡」理論の基礎となりました。
経穴における低電気抵抗は、その部位の神経活動や血流、そして後述する一酸化窒素(NO)などの生理活性物質の濃度と関連している可能性が考えられています。
一酸化窒素(NO)系分子の役割

経穴におけるNOの分布と機能
ここからが本論文の核心部分です。Ma博士らの研究グループは、長年にわたり経穴におけるNO系分子の動態を研究してきました。彼らの研究により、以下のような知見が明らかになっています:
経穴におけるNO濃度の特性
無侵襲的なバイオキャプチャー法を用いた測定により、経穴上の皮膚表面では、経絡上ではあるが経穴ではない部位や、経絡外の対照領域と比較して、総亜硝酸塩・硝酸塩(NOx-)および環状グアノシン一リン酸(cGMP)の濃度が高いことが示されました。
これは、経穴が単に解剖学的に特殊なだけでなく、生化学的にも独特の環境を持つことを意味しています。NOは血管拡張作用を持つ重要な分子であり、組織への酸素や栄養の供給を調節しています。
鍼刺激によるNO産生の増加
さらに重要なのは、様々な刺激によってこのNO産生が増強されるという点です:
- 低頻度の経皮的電気神経刺激(TENS)
- 電気鍼(EA)
- 手技鍼(MA)
- 温熱刺激
これらの刺激は、いずれもPSCPを誘発することが知られている刺激方法です。つまり、NO産生の増加とPSCPの発生には、何らかの因果関係がある可能性が示唆されるのです。
NOの作用機序
NOは様々な生理作用を持ちますが、経穴における主な役割として以下が考えられています:
血管拡張作用
NOは血管平滑筋を弛緩させ、局所の血流を増加させます。鍼刺激後に観察される皮膚の発赤は、この血管拡張の結果と考えられています。
軸索反射の媒介
NOは神経終末から放出され、近傍の神経線維を興奮させることで、中枢神経を介さない局所的な反射(軸索反射)を引き起こす可能性があります。
cGMPを介したシグナル伝達
NOは細胞内でcGMPの産生を促進し、様々な細胞応答を引き起こします。
ニューロペプチドの関与

CGRPとその役割
NO単独では説明できない現象も多く、他の神経伝達物質やニューロペプチドの関与も重要です。特に注目されているのが、カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)です。
CGRPはC線維という細い神経線維から放出されるペプチドで、以下のような作用を持っています:
- 強力な血管拡張作用
- 神経原性炎症の媒介
- 痛覚調節への関与
研究によれば、手技鍼による筋肉血流の増加には、軸索反射を介したCGRPの放出が関与していることが示されています。
その他のニューロペプチド
CGRP以外にも、以下のニューロペプチドの関与が示唆されています:
- ニューロペプチドY(NPY):血管収縮作用と血流調節
- サブスタンスP:痛覚伝達と炎症反応の媒介
これらの分子は相互に作用し合い、複雑なネットワークを形成していると考えられます。まるでオーケストラの楽器が協調して美しい音楽を奏でるように、これらの分子が協調して経絡現象を生み出している可能性があるのです。
TRPV1受容体の役割

TRPV1とは
TRPV1(Transient Receptor Potential Vanilloid type 1)は、侵害刺激や温度刺激を感知する非選択的陽イオンチャネルです。カプサイシン(唐辛子の辛味成分)の受容体としても知られています。
経穴におけるTRPV1の発現
興味深いことに、TRPV1は経穴の表皮下神経線維において高い発現を示すことが明らかになっています。さらに、電気鍼刺激によってこの発現がさらに増強されることも示されています。
TRPV1とNO合成酵素(nNOS)の共局在も確認されており、これらの分子が協調して鍼刺激の信号を中枢神経系に伝達している可能性が示唆されています。
軸索反射のメカニズム

軸索反射とは
ここで重要な概念である「軸索反射」について説明しましょう。通常の神経反射では、刺激が脊髄や脳などの中枢神経を経由して応答が生じます。しかし、軸索反射は末梢神経の分岐点で直接反射が起こる現象です。
例えるなら、通常の反射が「本社を経由した指示」であるのに対し、軸索反射は「現場判断での即座の対応」のようなものです。
経絡現象における軸索反射の役割
鍼刺激によって以下のようなカスケードが起こると考えられています:
- 鍼刺激が末梢神経を興奮させる
- 興奮が神経線維に沿って伝わる
- 神経線維の分岐点で逆行性にも興奮が伝わる
- 神経終末からNOやCGRPなどが放出される
- 局所の血管拡張と血流増加が起こる
- この現象が経絡に沿って次々と伝播していく
この「連鎖反応」のようなメカニズムが、PSCPの基盤となっている可能性があります。
延髄-視床経路:中枢における情報処理

薄束核の役割
ここまで末梢でのメカニズムを見てきましたが、中枢神経系での情報処理も同様に重要です。特に注目されているのが、延髄にある薄束核(gracile nucleus)という構造です。
薄束核は後肢からの体性感覚情報を受け取る中継核で、以下のような特徴があります:
- 主に同側(刺激と同じ側)からの入力を受ける
- 足の経穴(ST36など)への電気鍼刺激により、薄束核でのNO産生とnNOS発現が増加する
- 薄束核は視床を経由して大脳皮質へ情報を伝える
PSCPと神経経路の関係
従来、鍼刺激の感覚伝達には脊髄視床路が関与すると考えられていました。しかし、脊髄視床路では神経線維が脊髄内で交差するため、対側(刺激と反対側)に感覚が伝わるはずです。
ところが、PSCPの研究によれば、57症例の分析で85%が同側に感覚伝播が起こり、対側はわずか14%だったという報告があります。この事実は、PSCPの主な経路が脊髄視床路ではなく、後索を上行して薄束核を経由する背側経路である可能性を示唆しています。
延髄におけるNOの役割
薄束核でのNO産生には、以下のような意義があると考えられます:
- 感覚情報の増強と調節
- 視床への情報伝達の調節
- 自律神経系への影響を介した循環調節
実際、足三里(ST36)への電気鍼刺激による降圧作用は、薄束核へのL-アルギニン(NOの前駆物質)投与で増強され、nNOSの阻害で減弱することが示されています。
経絡の本態に関する統合的理解

間質液と筋膜の役割
最近の研究では、経絡の実体として「間質液の流れ」や「筋膜ネットワーク」の関与が提唱されています。
中国のZhangらの研究グループは、経絡が「低い液体抵抗の間質空間」であり、そこを流れる間質液が「気」の正体であるという仮説を提唱しています。実際、健常者の前腕にある心包経の経穴(内関 PC6)に蛍光色素を注入すると、約8割の被験者で色素が経絡経路に沿って線状に移動することが観察されました。
この現象は、筋肉間の結合組織(筋膜)に沿って色素が移動していることが、超音波画像などで確認されています。つまり、経絡は筋膜という実在する構造と深く関連している可能性があるのです。
多層的なネットワークとしての経絡
現在の知見を統合すると、経絡は以下のような多層的なネットワークとして理解できるかもしれません:
構造的基盤
- 筋膜および結合組織のネットワーク
- 神経線維と血管の豊富な分布
- 間質液の流れる経路
機能的側面
- NOやニューロペプチドによる局所的情報伝達
- 軸索反射による神経性調節
- 血流変化による代謝調節
- 薄束核-視床経路を介した中枢への情報伝達
このように、経絡は単一のメカニズムではなく、様々な生理学的システムが統合された複合的な機能ネットワークとして捉えることができるでしょう。
臨床的意義と今後の展望

鍼灸治療への示唆
これらの研究知見は、臨床実践にも重要な示唆を与えてくれます:
刺激方法の選択
- 低頻度・低強度の刺激がNO産生を促進する
- 高頻度・高強度の刺激では効果が異なる可能性がある
- 温熱刺激もNO産生を増加させる
経穴選択の重要性
- 経穴は生化学的にも特殊な領域である
- 遠位経穴(井穴)への刺激がPSCPを誘発しやすい
- 同側の経穴刺激が重要である可能性
得気の意義
- 得気感覚はNO媒介性の軸索反射と関連している可能性
- より強い得気がより良い治療効果につながる可能性
未解明の課題
一方で、まだ多くの疑問が残されています:
- NOやニューロペプチドが実際にどのように経絡に沿って伝播するのか?
- なぜ12本の経絡という特定の配置になっているのか?
- 経絡と内臓との関連はどのように説明できるのか?
- 個人差はどのような要因によって生じるのか?
これらの問いに答えるには、さらなる精密な研究が必要です。特に、ヒトにおけるリアルタイムでの分子動態の観察や、より大規模な臨床研究が求められています。
おわりに
経絡に沿った感覚伝播現象(PSCP)のメカニズムは、徐々にではありますが、現代科学の手法によって解明されつつあります。一酸化窒素(NO)やカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)などの生理活性物質、TRPV1受容体、軸索反射、そして薄束核を経由する背側経路など、様々な要素が複雑に絡み合いながら、この現象を生み出していると考えられます。
重要なのは、これらの知見が経絡の存在を「証明」したというよりも、経絡という概念が表現してきた生体の統合的な調節機構の一端を、現代科学の言葉で記述しつつあるということです。
古代中国の医師たちが経験的に見出した経絡という概念と、最先端の分子生物学や神経科学の知見が交差する点に、医学の未来を切り開く鍵があるのかもしれません。今後も、伝統的な知恵と現代科学の対話を通じて、新たな発見が生まれることを期待したいと思います。
参考文献
- Ma SX. Stimuli-evoked NOergic molecules and neuropeptides at acupuncture points and the gracile nucleus contribute to signal transduction of propagated sensation along the meridian through the dorsal medulla-thalamic pathways. J Integr Med. 2024;22(5):515-522.
- Wang GJ, Ayati MH, Zhang WB. Meridian studies in China: a systematic review. J Acupunct Meridian Stud. 2010;3(1):1-9.
- Ma SX, Li XY, Sakurai T, Pandjaitan M. Evidence of enhanced non-enzymatic nitric oxide generation on the skin surface of acupuncture points: An innovative approach in humans. Nitric Oxide. 2007;17(2):60-8.
- Lim NT, Ma SX. Responses of nitric oxide-cGMP releases in acupuncture point to electroacupuncture in human skin in vivo using dermal microdialysis. Microcirculation. 2009;16(5):434-43.
- Ibrahim TS, Chen ML, Ma SX. TRPV1 expression in acupuncture points: response to electroacupuncture stimulation. J Chem Neuroanat. 2011;41(3):129-36.
- Shinbara H, et al. Participation of calcitonin gene related peptide released via axon reflex in the local increase in muscle blood flow following manual acupuncture. Acupunct Med. 2013;31(1):81-7.
- Ma SX. Low electrical resistance properties of acupoints: roles of NOergic signaling molecules and neuropeptides in skin electrical conductance. Chin J Integr Med. 2021;27(8):563-9.
- Zhang WB, et al. A discovery of low hydraulic resistance channel along meridians. J Acupunct Meridian Stud. 2008;1(1):20-8.
- Al-Chaer ED, Westlund KN, Willis WD. Nucleus gracilis: an integrator for visceral and somatic information. J Neurophysiol. 1997;78(1):521-7.
- Xu JS, et al. The existence of propagated sensation along the meridian proved by neuroelectrophysiology. Neural Regen Res. 2013;8(28):2633-40.

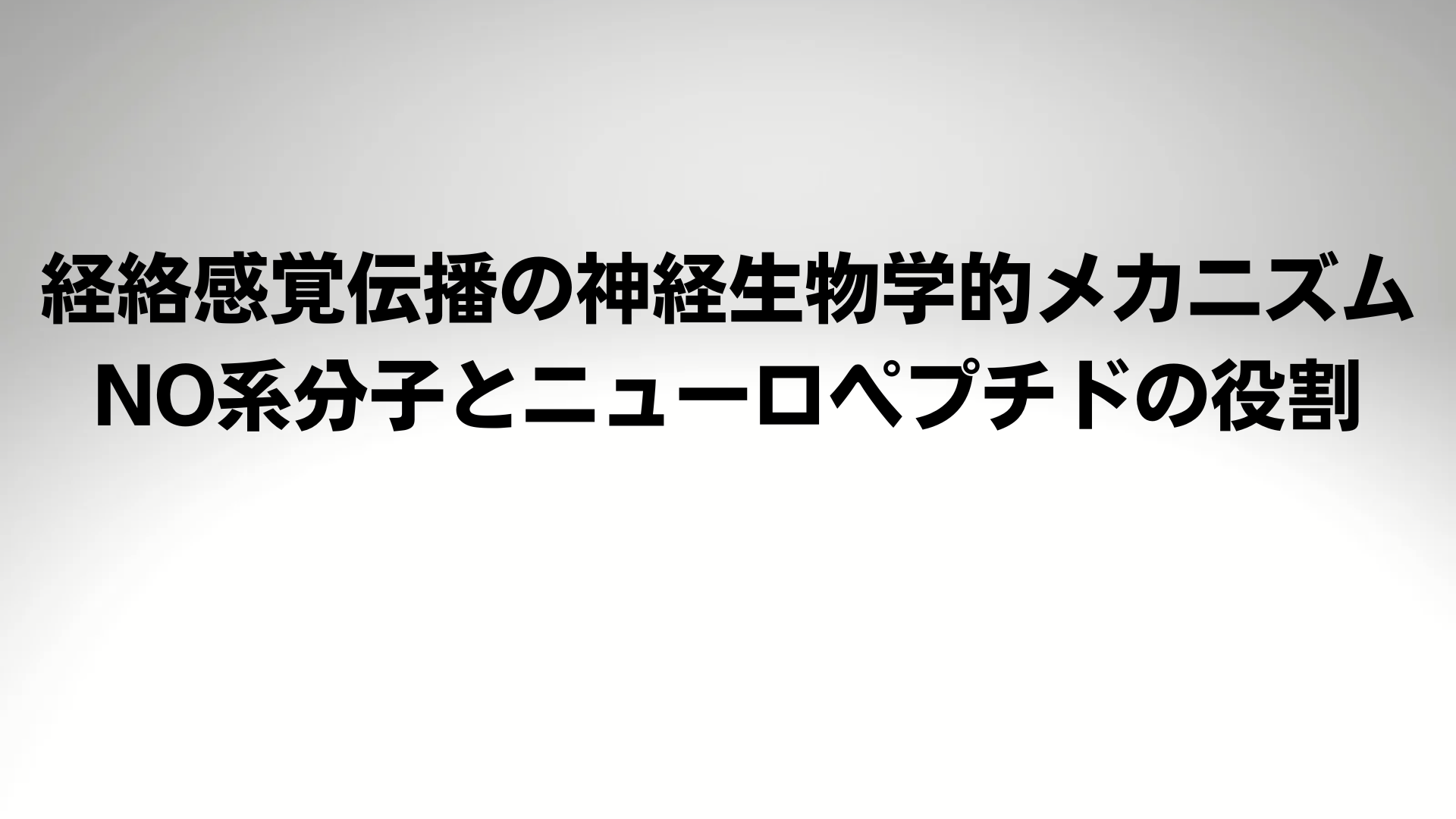
コメント