※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
参考文献はこちら
すべてを鵜呑みにしないでくださいね!
宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼

お金持っている人は新品買ってね!
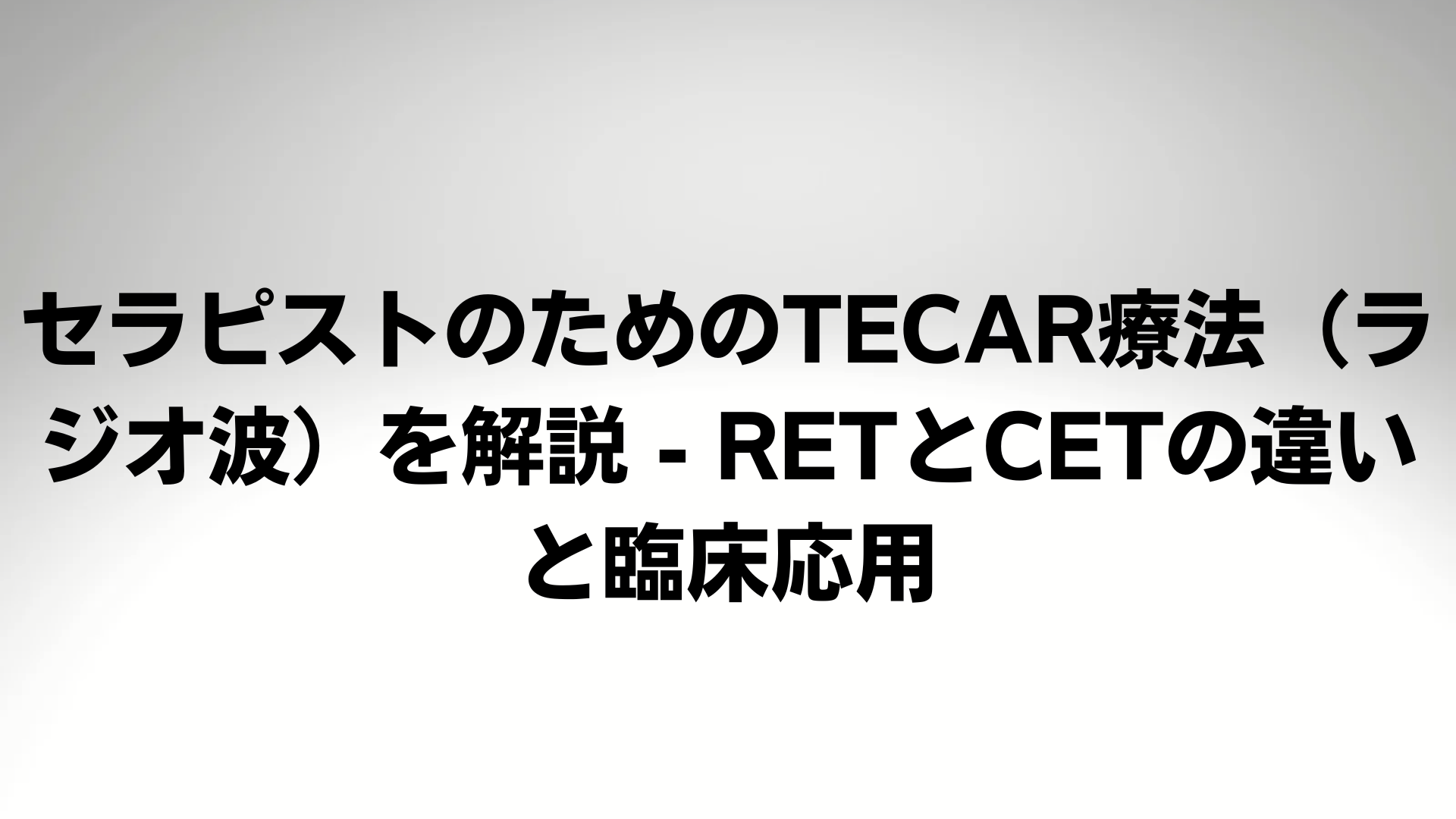
それでは内容に入っていきましょう‼
はじめに

アキレス腱障害は、スポーツ医療の現場において頻繁に遭遇する疾患の一つです。特に慢性化した症例では、長期にわたる疼痛やパフォーマンスの低下により、選手たちの競技生活に大きな影響を及ぼすことが知られています。近年、このような難治性のアキレス腱障害に対して、ラジオ波療法(Tecar療法、または抵抗性容量性電気伝達療法:CRet)が注目を集めています。
本稿では、2022年にClinicalTrials.gov. Effectiveness of Tecar Therapy in Patients With Chronic Achilles Tendinopathy. Identifier: NCT05539586. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05539586をはじめとする複数の研究論文を参考に、ラジオ波療法がアキレス腱障害にどのような効果をもたらす可能性があるのか、その作用機序と臨床的意義について考察していきたいと思います。
アキレス腱障害の病態と治療の課題

アキレス腱障害は、腱組織の疼痛、パフォーマンスの低下、そして腱周囲の腫脹を特徴とする病態です。
文献によりますと、アキレス腱障害を持つ患者さんの最大29%が外科的介入を必要とする可能性があり、部分断裂や完全断裂といった合併症のリスクも懸念されています。
病理組織学的には、アキレス腱障害は次のような特徴を持っているとされています。
細胞の活性化と細胞数の増加、基質の増加、コラーゲンの配列の乱れ、そして新生血管の形成です。これらの変化は、腱の正常な構造と機能を損なう要因となっているようです。
好発部位としては、踵骨付着部から1.5センチから2センチほど頭側の部分が挙げられ、また腓腹筋内側頭と腓腹筋が合流してアキレス腱近位部を形成する筋腱移行部にも、病的な炎症が生じやすいことが報告されています(約66%の患者さんで観察されるとのことです)。
現在、アキレス腱障害に対しては様々な治療法が提案されていますが、エビデンスに基づいて明確な改善効果が示されているのは、遠心性運動(エクセントリックエクササイズ)のプロトコルが中心となっています。
ただし、この治療法には一つの課題があります。それは、効果が現れるまでに長期間を要するという点です。
ラジオ波療法(Tecar療法)の基本原理

ラジオ波療法、別名Tecar療法(Transfer of Energy Capacitive and Resistive)は、非侵襲的な電気温熱療法として分類されており、深部温熱療法の一種と考えられています。この治療法は、300キロヘルツから1.2メガヘルツの範囲内の高周波電流を身体組織に適用することで、治療効果を生み出すものです。
この療法の特徴的な点は、外部からの熱を加えるのではなく、体内で内因性の熱を発生させるという点にあります。電気的なエネルギーが組織内を通過することで、分子レベルでの振動が起こり、その結果として熱が生成されるわけです。
ラジオ波療法には、容量性(Capacitive)モードと抵抗性(Resistive)モードという二つの異なる適用方法があります。容量性モードでは、絶縁された電極を使用し、水分含有量の多い筋肉や皮下組織などの軟部組織に主に作用します。一方、抵抗性モードでは、電気抵抗の高い組織、つまり腱や靭帯、骨といったより深部の構造物に対して、より効果的に働きかけることができるとされています。
ラジオ波療法の生理学的効果
ラジオ波療法が組織に及ぼす影響については、複数の研究で検討されています。López-de-Celisらの研究グループが2020年に発表した献体を用いた研究では、アキレス腱と腓腹筋の筋腱移行部における温度変化と電流の流れについて、詳細な分析が行われました。
この研究によりますと、低出力の抵抗性プロトコルでは、5分間の適用後に、表面温度がわずか1.14%の上昇にとどまる一方で、アキレス腱では28.13%、筋腱移行部では11.67%の温度上昇が観察されたとのことです。同時に、0.063アンペアの電流が流れていることも確認されました。
興味深いのは、高出力の抵抗性プロトコルを用いた場合で、アキレス腱の温度が109.70%も上昇し、筋腱移行部では81.49%の上昇が見られました。この場合の電流は0.120アンペアに達していました。
重要な点として、温度上昇が比較的軽微な低出力プロトコルにおいても、電流の流れは確実に観察されているということです。これは何を意味するのでしょうか。
研究者たちは、この電流の流れが細胞の増殖と関連している可能性を指摘しています。つまり、ラジオ波療法の効果は、単純な温熱効果だけではなく、電流が組織を通過することによる非温熱効果も重要な役割を果たしている可能性があるということです。
治療効果の多面性

ラジオ波療法に期待される効果は、多岐にわたります。まず、深部および表層の血液循環の増加が挙げられます。組織の温度が上昇することで血管が拡張し、血流量が増えることが示唆されています。実際に、健常者を対象とした研究では、ラジオ波療法の適用により、皮膚の微小循環における灌流が改善される傾向が報告されています。
血流の改善は、栄養素の供給と老廃物の除去を促進し、組織の修復プロセスを加速させる可能性があります。特にアキレス腱のような血流が豊富とは言えない組織において、このような循環の改善は臨床的に意義深いものと考えられます。
また、過剰な体液の排出を促進する効果も報告されています。腱障害では、しばしば腱周囲の浮腫が見られますが、ラジオ波療法によってリンパ系の機能が改善され、浮腫の軽減につながる可能性が示唆されています。
細胞増殖の促進という点も見逃せません。
先ほど述べた電流の効果として、組織修復に必要な細胞の増殖が刺激される可能性があります。これは、損傷した腱組織の再生において、重要な役割を果たすかもしれません。
遠心性運動との併用の可能性

今回の臨床試験の背景として注目されるのは、遠心性運動プロトコルにラジオ波療法を追加することで、短期および中期的に、機能的変数と構造的変数の両方において、どのような相乗効果が得られるかという点です。
遠心性運動は、アキレス腱障害に対する標準的な治療法として確立されていますが、いくつかの研究では、その効果に疑問を呈する声もあります。例えば、遠心性運動単独では、特に付着部型のアキレス腱障害において、患者さんの満足度が必ずしも高くないという報告もあります。
一方で、遠心性運動には明確な利点も存在します。
腱の容積を減少させる効果が磁気共鳴画像法(MRI)を用いた研究で示されており、この容積の変化が疼痛の軽減と関連している可能性が指摘されています。
また、遠心性運動は、圧痛閾値を改善する、つまり痛みに対する感受性を低下させる効果があることも報告されています。
ラジオ波療法の特性である組織の粘弾性の変化を促す効果と、遠心性運動による腱への機械的刺激を組み合わせることで、より包括的な治療効果が期待できるのではないかという仮説が立てられています。
実際に、電流の通過と温熱変化は、関節包や筋組織における粘弾性の変化と直接的に関連していることが示されており、これがスポーツ選手の機能的能力の改善につながる可能性があると考えられています。
他の治療法との比較
アキレス腱障害の治療法は、ラジオ波療法や遠心性運動だけに限りません。体外衝撃波療法(ESWT)も、効果的な選択肢の一つとして認識されています。
Wiegerinckらによる系統的レビューでは、付着部型アキレス腱障害に対する様々な治療法が比較検討されました。その結果、体外衝撃波療法は、経過観察のみの群や遠心性トレーニング群と比較して、優れた効果を示したと報告されています。特に、石灰化を伴わない付着部型アキレス腱障害において、効果的である可能性が示唆されました。
興味深いことに、同じレビューにおいて、ラジオ波療法も言及されています。
Costantinoらの研究では、炭酸ガスレーザー、ラジオ波療法、そしてクライオ超音波療法(!?)という三つの治療法が比較されました。
その結果、すべての介入において視覚的アナログスケール(VAS)の有意な減少が認められたとのことです。
患者さんの満足度という観点から見ると、クライオ超音波療法群では5名全員が「非常に満足」と回答し、ラジオ波療法群では5名中2名が「非常に満足」、3名が「満足」と回答しました。炭酸ガスレーザー群では、5名全員が「満足」という結果でした。
これらの結果は、ラジオ波療法が他の理学療法と同等かそれ以上の効果を持つ可能性を示唆していますが、各治療法の適応や患者さんの個別性を考慮した選択が重要であることも示しています。
作用機序についての考察

ラジオ波療法がなぜ効果を発揮するのか、その作用機序については、まだ完全には解明されていません。しかし、現在までの研究から、いくつかの可能性が浮かび上がってきています。
第一に、熱効果による血流改善です。組織温度の上昇により、血管が拡張し、酸素飽和度が向上することが示されています。これにより、組織の代謝が活性化され、修復プロセスが促進される可能性があります。
第二に、非熱効果として、電流の通過そのものが細胞レベルでの変化を引き起こす可能性です。電流が組織を流れることで、イオンや電解質の移動が誘発され、これが細胞の増殖や分化に影響を与えるのではないかと考えられています。
第三に、組織の粘弾性の改善です。慢性的な腱障害では、腱の硬さが増し、柔軟性が失われることがあります。ラジオ波療法によって、コラーゲン線維の配列が改善されたり、基質の状態が変化したりすることで、組織の機械的特性が改善される可能性があります。
第四に、疼痛緩和のメカニズムです。温熱刺激がエンドルフィンの産生を促進することが知られており、これが鎮痛効果に寄与している可能性があります。また、神経伝達のブロックや、痛みの閾値を上昇させる効果も報告されています。
臨床応用における考慮点
ラジオ波療法を臨床で使用する際には、いくつかの重要なポイントがあります。
まず、急性期と慢性期で、適用するプロトコルを変える必要があるかもしれません。López-de-Celisらの研究では、低出力プロトコルは、温度上昇を最小限に抑えながら電流の効果を得られるため、急性期の炎症性アキレス腱障害や急性の筋損傷に適している可能性が示唆されています。
一方、高出力プロトコルは、より大きな温熱効果と高い電流を生み出すため、慢性期の症例において、組織の粘弾性を改善する目的で使用することが考えられます。特に、慢性腱障害や捻挫後の線維性瘢痕(テニスレッグなど)の治療に有用かもしれません。
治療の頻度と期間については、現在進行中の臨床試験や今後の研究結果を待つ必要がありますが、既存の文献では、週に2回程度の治療を数週間継続するプロトコルが多く見られます。
また、ラジオ波療法は単独で使用されることは比較的少なく、遠心性運動や徒手療法、体外衝撃波療法などと組み合わせて使用されることが多いようです。このような多角的なアプローチが、より良い治療成績につながる可能性があります。
安全性と禁忌
ラジオ波療法は、一般的に安全な治療法とされていますが、いくつかの禁忌や注意事項があります。
絶対的禁忌としては、心臓ペースメーカーや植込み型除細動器などの植込み型電子機器を使用している患者さん、妊娠中の方、悪性腫瘍のある部位、感染症や発熱がある場合などが挙げられます。また、治療部位に金属製のインプラントやピアスがある場合も、避ける必要があります。
相対的禁忌としては、糖尿病患者さんへの適用時には十分な注意が必要です。また、美容医療処置(ヒアルロン酸注入やリフトアップ糸など)を受けた部位への適用も、慎重に判断する必要があります。
治療中は、患者さんの感覚のフィードバックが重要です。適度な温かさを感じる程度が適切とされており、熱すぎる場合や不快感がある場合は、すぐに出力を調整する必要があります。
エビデンスの限界と今後の展望

ここまで、ラジオ波療法の可能性について述べてきましたが、現時点でのエビデンスにはいくつかの限界があることも認識しておく必要があります。
まず、高品質なランダム化比較試験の数がまだ限られているという点です。NCT05539586のような臨床試験が進行中ですが、その結果が待たれるところです。また、既存の研究の多くはサンプルサイズが小さく、フォローアップ期間も比較的短いものが多いという課題があります。
治療プロトコルの標準化も、今後の課題です。出力設定、治療時間、治療頻度、容量性モードと抵抗性モードの使い分けなど、最適な条件についてはまだコンセンサスが得られていません。
また、どのような患者さんに最も効果的なのか、つまり患者選択の基準についても、さらなる研究が必要です。症状の程度、罹病期間、年齢、活動レベルなど、様々な要因が治療効果に影響を与える可能性があります。
コスト効果の分析も重要な視点です。ラジオ波療法の機器は比較的高価であり、医療経済的な観点からも、その費用対効果を検証することが求められます。
今後、メカニズムの解明を目指した基礎研究と、効果を実証する臨床研究の両方が進展することで、ラジオ波療法の位置づけがより明確になっていくものと期待されます。
おわりに
ラジオ波療法は、慢性アキレス腱障害に対する治療法として、その可能性が注目されている新しいアプローチです。温熱効果と非温熱効果の両方を通じて、組織の修復を促進し、疼痛を軽減する可能性が示唆されています。
López-de-Celisらの基礎研究によって、アキレス腱と筋腱移行部における温度変化と電流の流れが実証され、その作用機序の理解が深まってきました。また、遠心性運動との併用によって、より包括的な治療効果が得られる可能性も期待されています。
しかしながら、現時点でのエビデンスには限界があり、NCT05539586をはじめとする進行中の臨床試験の結果を待つ必要があります。治療プロトコルの標準化、適切な患者選択、そしてコスト効果の検証など、解決すべき課題も残されています。
臨床家としては、現在のエビデンスを批判的に吟味しながら、個々の患者さんに最適な治療法を選択していくことが求められます。ラジオ波療法は万能ではありませんが、適切に使用すれば、難治性のアキレス腱障害に悩む患者さんの助けとなる可能性を秘めた、有望な治療選択肢の一つであると言えるでしょう。
今後、さらなる研究の蓄積によって、この治療法の真価が明らかになることを期待しつつ、日々の臨床に活かしていきたいと思います。
参考文献
- ClinicalTrials.gov. Effectiveness of Tecar Therapy in Patients With Chronic Achilles Tendinopathy. Identifier: NCT05539586. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05539586
- López-de-Celis C, Hidalgo-García C, Pérez-Bellmunt A, et al. Thermal and non-thermal effects off capacitive-resistive electric transfer application on the Achilles tendon and musculotendinous junction of the gastrocnemius muscle: a cadaveric study. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):46.
- Wiegerinck JI, Kerkhoffs GM, van Sterkenburg MN, et al. Treatment for insertional Achilles tendinopathy: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(6):1345-1355.
- Costantino C, Pogliacomi F, Vaienti E. Cryoultrasound therapy and tendonitis in athletes: a comparative evaluation versus laser CO2 and t.e.ca.r. therapy. Acta Biomed. 2005;76(1):37-41.
- Clijsen R, Taeymans J, Baeyans JP, et al. Does the application of tecar therapy affect temperature and perfusion of skin and muscle microcirculation? A pilot feasibility study on healthy subjects. J Altern Complement Med. 2020;26(2):147-153.
- Ribeiro G, Coda A, Nardini R, et al. TECAR Therapy: A Clinical Commentary on its Evolution, Application, and Future in Rehabilitation. Sports Med Open. 2024;10(1):Article number not specified.
- Stania M, Juras G, Chmielewska D, et al. Extracorporeal Shockwave Therapy for Achilles Tendinopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int. 2019;2019:3086910.
- Malliaras P, Barton CJ, Reeves ND, Langberg H. Achilles and patellar tendinopathy loading programmes: a systematic review comparing clinical outcomes and identifying potential mechanisms for effectiveness. Sports Med. 2013;43(4):267-286.
- Alfredson H, Pietilä T, Jonsson P, Lorentzon R. Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis. Am J Sports Med. 1998;26(3):360-366.
- Silbernagel KG, Thomeé R, Thomeé P, Karlsson J. Eccentric overload training for patients with chronic Achilles tendon pain–a randomised controlled study with reliability testing of the evaluation methods. Scand J Med Sci Sports. 2001;11(4):197-206.
- De Jonge S, de Vos RJ, Weir A, et al. One-year follow-up of platelet-rich plasma treatment in chronic Achilles tendinopathy: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Sports Med. 2011;39(8):1623-1629.
- Notarnicola A, Maccagnano G, Gallone MF, et al. Short term efficacy of capacitive-resistive diathermy therapy in patients with low back pain: A prospective randomized controlled trial. J Biol Regul Homeost Agents. 2017;31(2):509-515.
- Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shock wave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy. A randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am. 2008;90(1):52-61.
- Murphy MC, Travers MJ, Chivers P, et al. Eccentric Exercise for Achilles Tendinopathy: A Narrative Review and Clinical Decision-Making Considerations. J Funct Morphol Kinesiol. 2019;4(2):34.
- Murtaugh B, Ihm JM. Eccentric training for the treatment of tendinopathies. Curr Sports Med Rep. 2013;12(3):175-182.
- Kumar V, Millar A. Eccentric or Concentric Exercises for the Treatment of Tendinopathies? J Orthop Sports Phys Ther. 2015;45(11):853-863.
- Santos HH, Ávila MA, Hanashiro DN, et al. The Brazilian consensus on insertional and mid-portion Achilles tendinopathy (Active Esporte Club/SBRATE). BMJ Open Sport Exerc Med. 2023;9(2):e001506.
- Canet-Vintró M, Rodríguez-Sanz J, Bosh-Donate E, et al. Acute Effects of Tecar Therapy on Skin Temperature, Ankle Mobility and Hyperalgesia in Myofascial Pain Syndrome in Professional Basketball Players: A Pilot Study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(16):8756.
- Kumaran B, Watson T. Thermal build-up, decay and retention responses to local therapeutic application of 448 kHz capacitive resistive monopolar radiofrequency: A prospective randomised crossover study in healthy adults. Int J Hyperthermia. 2015;31(8):883-895.
- Tashiro Y, Hasegawa S, Yokota Y, et al. Effect of capacitive and resistive electric transfer on haemoglobin saturation and tissue temperature. Int J Hyperthermia. 2017;33(6):696-702.

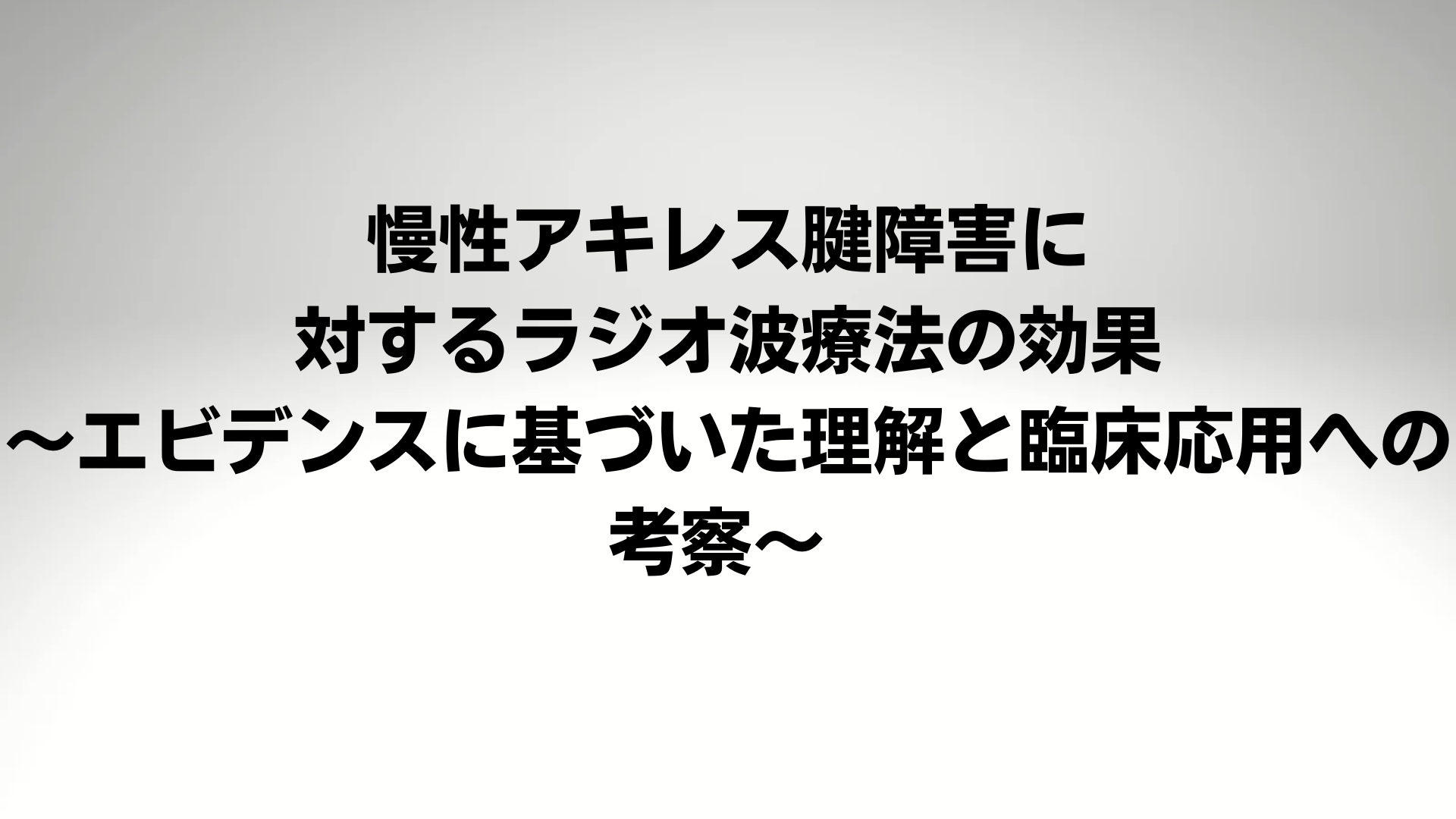
コメント