こんにちは!
陣内です。
今回も論文をご紹介していきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
前回同様「The Analgesic Effect of NLRP3 Inflammasome in the Relief of Inflammatory Pain by Electroacupuncture」)に記載されている 電気鍼の刺激条件(frequency/intensity/duration/施術回数/取穴など) を中心に、鍼灸師の先生向けに向けに詳しく解説します。
臨床応用のヒントも添えていますので何か参考になればかと思います。
まあぶっちゃけ自分の備忘録です。
前回の記事
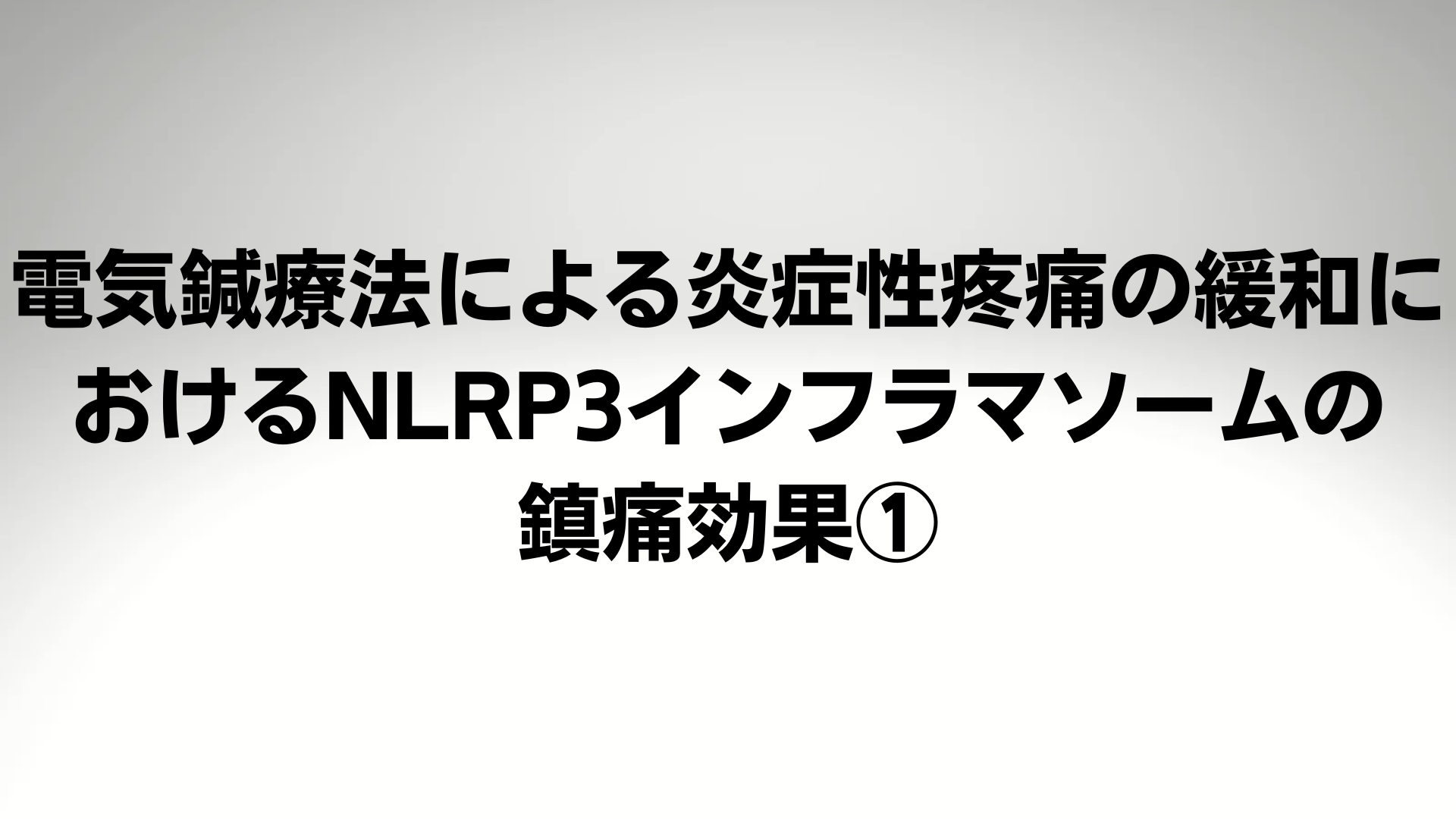
1. 電気鍼の刺激条件:研究で使われた設定の概要
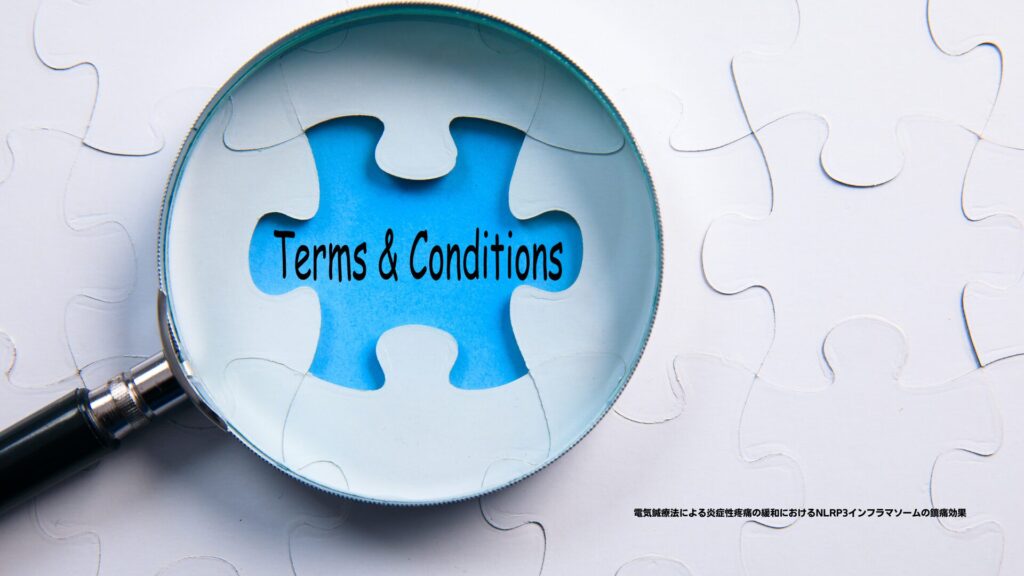
このメタ解析では、10 件の動物実験研究が対象となっており、鍼刺激条件にある程度の共通点がありました。
以下は、解析で確認された代表的なパラメータのまとめです。
| 項目 | 主な設定(平均的条件) | 備考 |
|---|---|---|
| 刺激周波数(frequency) | 2 Hz または 2/100 Hz の交互波 | 低頻度(2 Hz)が最も多く、次いで2/100 Hz ミックス |
| 電流強度(intensity) | 0.5~2.0 mA (動物が軽く筋収縮する程度) | 強刺激ではなく、可視的筋収縮を目安に設定 |
| 通電時間(duration) | 20~30 分/回 | 1 回の施術時間は30 分未満が多い |
| 施術頻度(frequency per day/week) | 1 回/日、週5~7 回 | 多くは連日または隔日施術 |
| 治療期間(total sessions) | 7~14 日間 | 慢性炎症モデルでは2 週間前後が多い |
| 刺鍼部位(acupoints) | ST36 (足三里)+ SP6 (三陰交) or LI4 (合谷) or ST34 (梁丘)など | 炎症部位近傍と遠隔経穴の併用が多い |
| 鍼の材質・サイズ | ステンレス鍼 (0.25 mm × 13–25 mm 程度) | 標準的な動物用寸法。ヒトでは0.18–0.25 mm相当が適当 |
| 通電波形 | 双方向対称矩形波(biphasic square wave) | 皮膚刺激痛を防ぎ、神経刺激を安定化 |
2. 各パラメータの意味と臨床応用のヒント
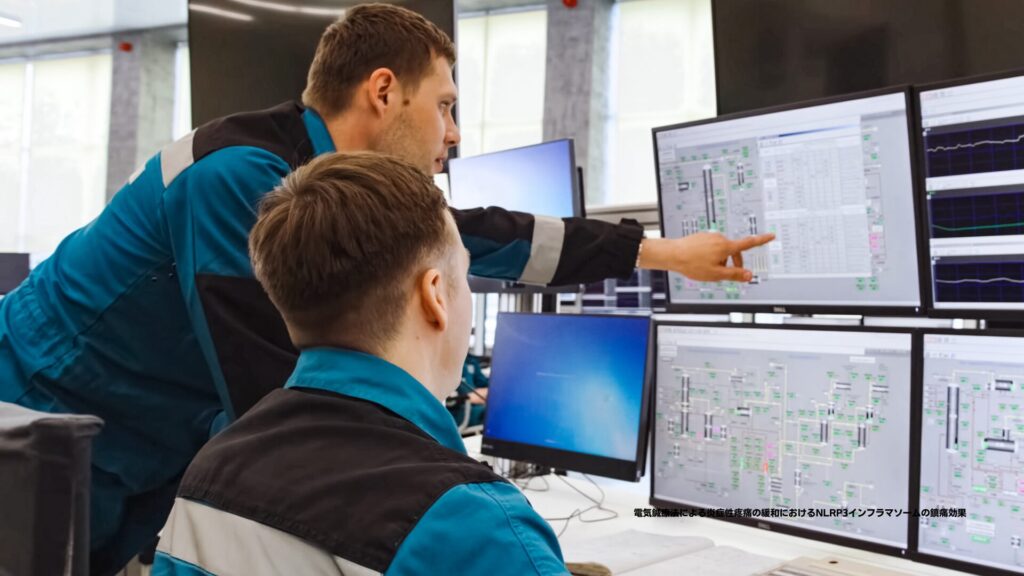
(1)周波数:低頻度 vs 変調波
- 2 Hz(低頻度) はエンドルフィン系(μ受容体・βエンドルフィンなど)を介した鎮痛作用が中心。
- 2/100 Hz 変調波 は、低頻度+高頻度刺激の併用により、複数のオピオイド受容体系(μ, δ, κ)を同時活性化できる可能性。
- 本論文では 2 Hz 刺激が最も多く使われており、炎症性疼痛では「低頻度の持続刺激」が有効とされています。
👉 臨床では 2 Hz または 2/100 Hz で20–30 分間 の通電を目安に設定すると良いでしょう。
(2)電流強度:筋収縮を目安に
- 動物実験では0.5–2.0 mAで設定され、動物が軽く筋収縮する程度を目安にしています。
- 強すぎると組織損傷や疼痛ストレスが強まり、逆効果になる場合も。
- 臨床でも、患者が「筋肉が軽くピクッと動く」程度の刺激が適度です。
- 炎症部位が過敏な場合は0.5 mA程度から開始
- 慢性化している場合や深部痛では1.0~1.5 mA程度まで上げることも可
(3)施術時間・頻度
- 研究では「20–30 分×毎日または隔日施術×1–2 週間」が多い。
- 炎症制御には「刺激を繰り返すこと」が重要で、単回刺激より連日刺激でNLRP3抑制が強まる傾向があります。
👉 臨床では 週2–3 回以上の頻度で1–2 週間連続施術 を目安に考えてよいでしょう。
(4)取穴パターン:ST36 (足三里)を中心に
電気鍼の取穴は次のような傾向がありました:
| 目的 | 使用穴 | 臨床応用のポイント |
|---|---|---|
| 全身性抗炎症・免疫調整 | ST36(足三里)+ SP6(三陰交) | 経絡的にも「脾胃」調整・免疫調整に関与 |
| 局所炎症・疼痛抑制 | 炎症部近傍の筋・経穴(例:ST34 梁丘・GB34 陽陵泉 など) | 筋骨格系炎症に効果的 |
| 遠隔鎮痛・全身鎮静 | LI4 (合谷)+ ST36 (足三里) | 中枢性鎮痛経路の活性化を狙う |
| 慢性化例 | BL60 (崑崙)・GB39 (懸鐘)など下肢経穴追加 | 血流改善・抗炎症に寄与 |
👉 基本軸:ST36 + SP6 + 局所1–2 穴
これがもっとも汎用的かつエビデンスが多い組み合わせです。
3. 研究で示された刺激条件とNLRP3抑制の関係

論文では、刺激条件によってNLRP3 インフラマソーム抑制効果の強弱が若干異なりました。
主な傾向は以下の通りです:
| 刺激条件 | NLRP3抑制効果 | 解釈 |
|---|---|---|
| 2 Hz 低頻度刺激 | 最も安定した抑制効果 | ROS低下・NF-κB抑制との関連が強い |
| 2/100 Hz 混合波 | やや強い抗炎症効果(IL-10上昇が顕著) | 多系統オピオイド経路+免疫調整が関与 |
| 高頻度(100 Hz)単独 | 効果は限定的(急性痛には有効) | 炎症性疼痛では低頻度優位 |
結論として、慢性炎症性疼痛の免疫・炎症制御を狙う場合は、低頻度(2 Hz)電気鍼が最も理想的 とされています。
一方、急性期で痛みが強い場合は、2/100 Hz 混合波で鎮痛+抗炎症を両立する選択も可能です。
4. 臨床実践への落とし込み(例)
✅ 炎症性膝関節痛の例
- 主訴:膝内側部の熱感・腫脹・圧痛
- 取穴:ST36 (足三里)、SP9 (陰陵泉)、SP10 (血海)、膝周囲の阿是穴
- 設定:2 Hz ・ 1.0 mA ・ 25 分間
- 頻度:週3 回 × 2 週
- 期待効果:IL-1β・IL-6 低下、NF-κB 抑制 → 熱感・腫脹減少、疼痛緩和
✅ 肩関節周囲炎(五十肩)の例
- 取穴:LI15 (肩髃)、TE14 (肩髎)、LI4 (合谷)、ST36 (足三里)
- 設定:2/100 Hz 混合波 ・ 0.8~1.2 mA ・ 30 分
- 頻度:週2~3 回
- 期待効果:筋緊張緩和+局所血流改善+NLRP3経路抑制による炎症軽減
5. 鍼灸師が注意すべき臨床ポイント
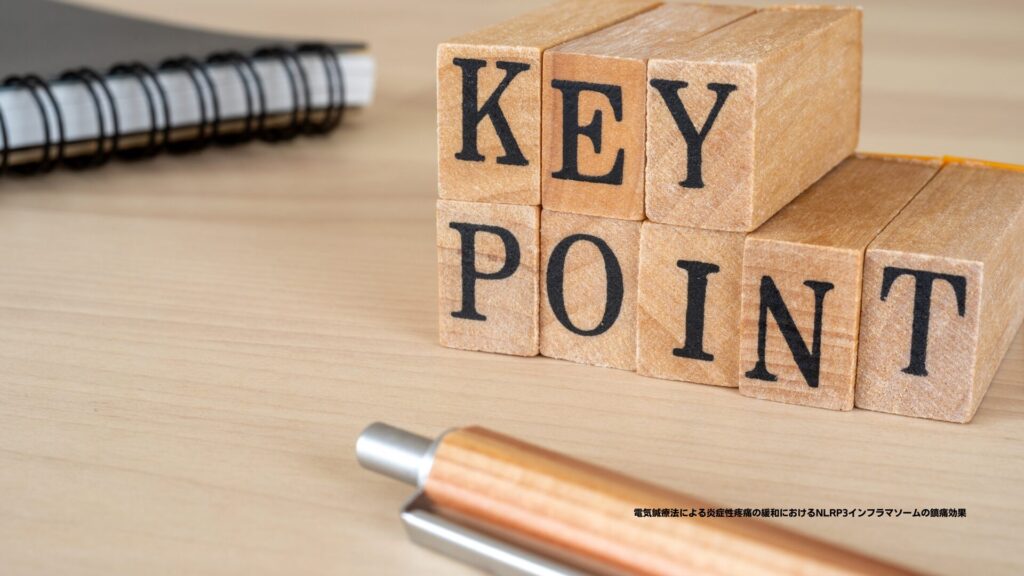
- 刺激強度は「快刺激」を維持
- 強すぎる刺激はストレス反応を誘発し、逆にROS増加・炎症促進の可能性も。
- 「気持ちよい程度」「軽く筋肉が動く程度」が理想。
- 電極配置をシンプルに
- ST36–SP6 間または 局所2穴 間 の通電で十分。複数経穴に接続すると電流分布が不均一になります。
- 通電時間は20–30 分を超えない
- 長時間刺激では皮膚刺激や筋疲労が生じる場合があります。
- 論文上も30 分以上の効果増強は見られていません。
- 炎症反応が強い初期には、軽刺激から導入
- 急性炎症(腫脹・熱感)のある部位では、最初は0.5 mA × 15 分程度から。
- 炎症反応が落ち着いたら刺激時間・強度を徐々に増加。
6. まとめ:臨床応用の指針
| 要素 | 研究からの推奨設定 | 臨床応用の目安 |
|---|---|---|
| 周波数 | 2 Hz (低頻度)または 2/100 Hz 混合波 | 炎症性疼痛→2 Hz、急性痛→混合波 |
| 強度 | 0.5–2.0 mA (軽い筋収縮) | 「快刺激」~「軽収縮」 |
| 時間 | 20–30 分/回 | 25 分前後が最適 |
| 頻度 | 1 回/日 (週5–7 回) | 臨床では週2–3 回以上推奨 |
| 取穴 | ST36 + SP6 + 局所1–2 穴 | 免疫+局所循環を両立 |
| 波形 | 双方向矩形波 | 皮膚刺激少なく安定 |
このように、本論文から読み取れる電気鍼条件は、
👉 「低頻度・軽刺激・連続刺激」
が炎症性疼痛の抑制に最も効果的であるという結果です。
これは経験上納得いく結果かなと思います
何か参考になれば幸いです。

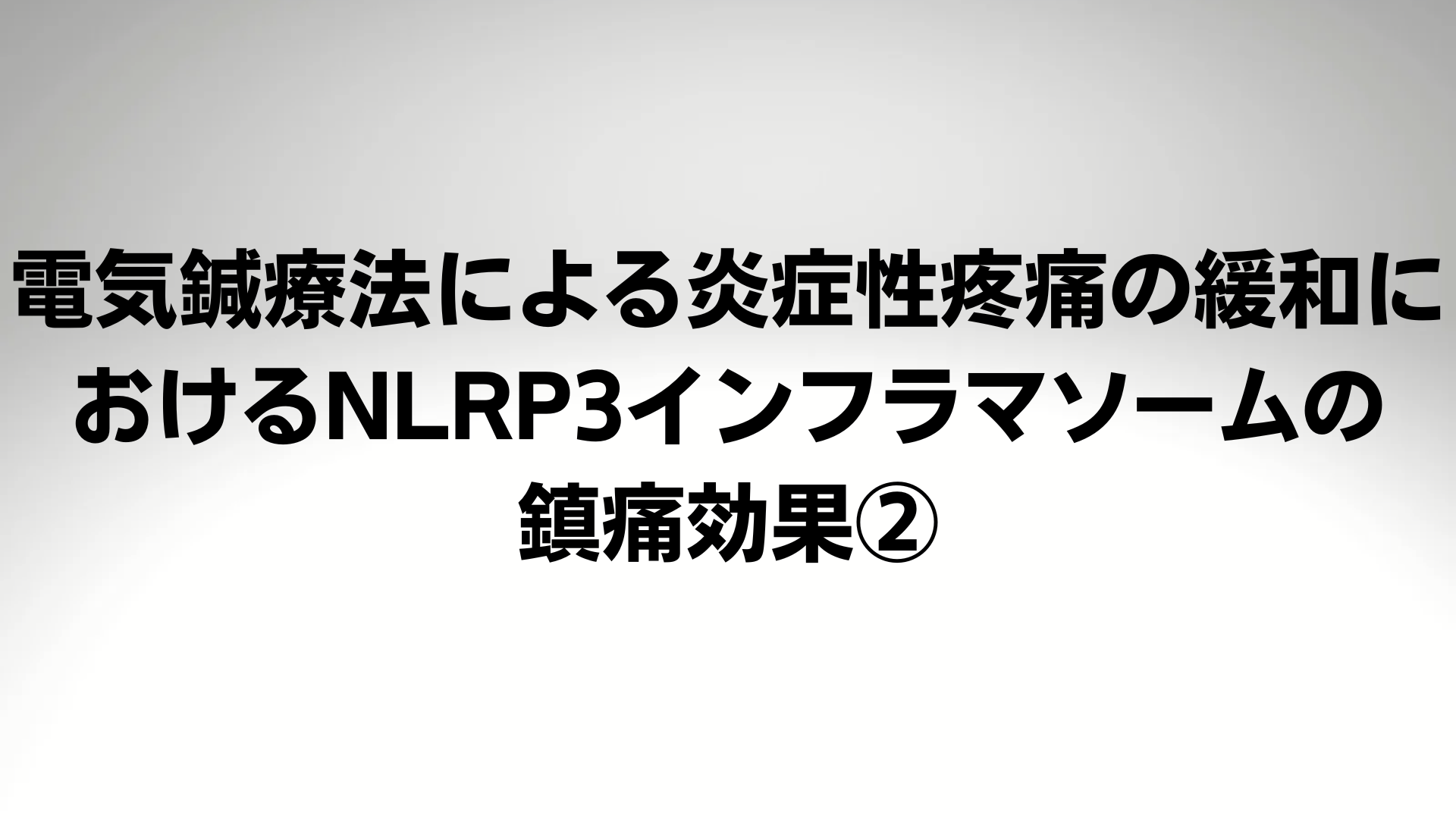
コメント