こんにちは!
陣内です。
今回も論文をご紹介していきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
「The Analgesic Effect of NLRP3 Inflammasome in the Relief of Inflammatory Pain by Electroacupuncture: A Systematic Review and Meta‑Analysis of Animal Studies(Su ら, 2025)について書いていきます。論文中の内容は基礎・動物実験研究にもとづいていますので、臨床応用時にはヒトへの転帰・個別性・安全面なども必ずご留意ください。
こちらの記事と一緒に読んでいただければ幸いです。
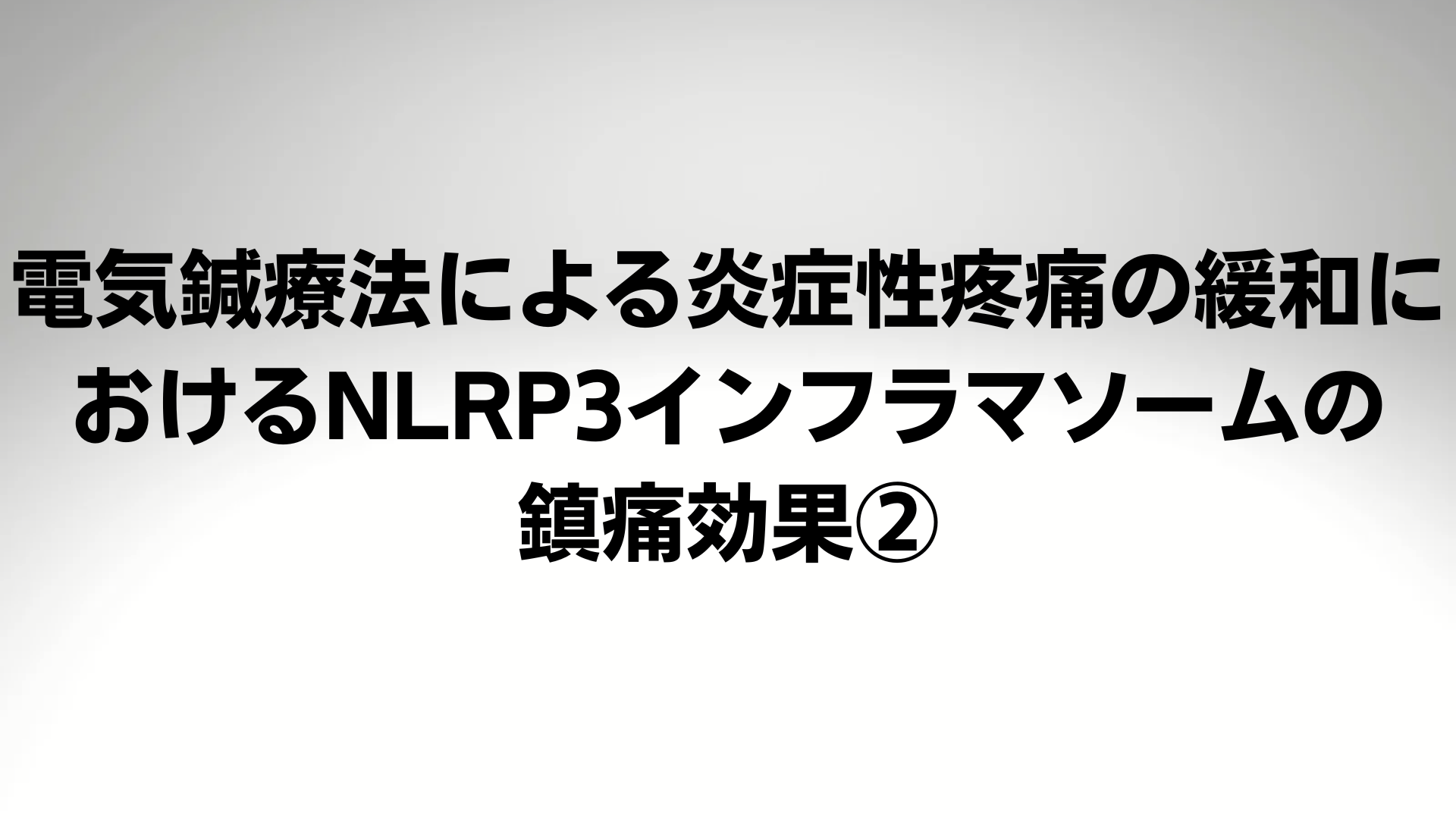
はじめに
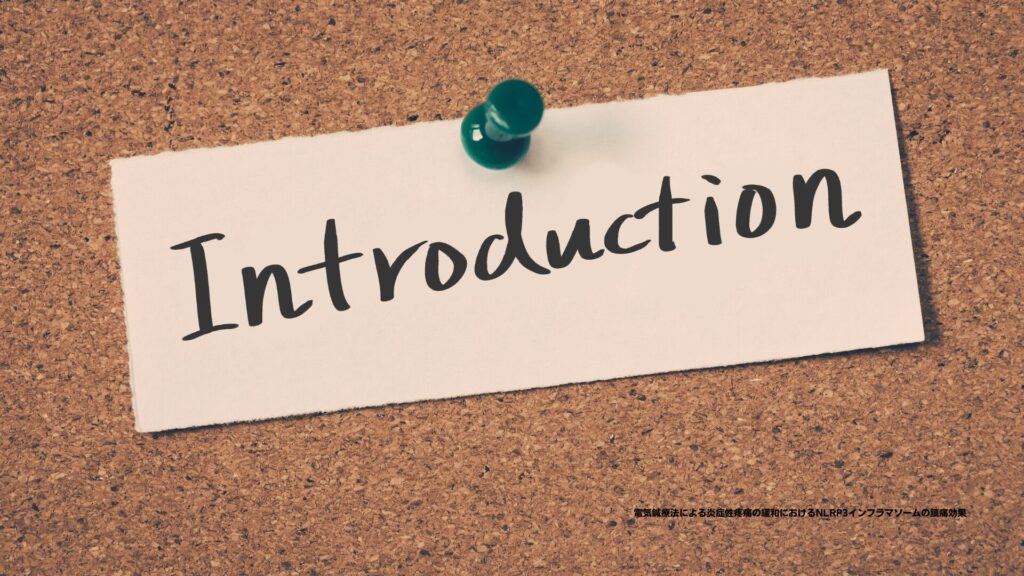
炎症性疼痛(たとえば、関節炎・筋・腱の炎症・術後/外傷後の疼痛など)は、鍼灸臨床でもよく遭遇する分野です。疼痛改善だけでなく、炎症反応の制御が「痛みを長引かせない」ためには重要であるという認識も広がっています。
本論文は、鍼灸の一手法である「電気鍼(electroacupuncture:EA)」が、炎症性疼痛において、特に免疫・炎症メカニズムの一つである「NLRP3 インフラマソーム(NLRP3 inflammasome)」を介して疼痛を軽減しうるかを、動物実験を対象にメタ解析したものです。 (PMC)
鍼灸師として、鍼・電気鍼が「ただ痛みを取る」だけでなく「炎症のプロセスに働きかけるかもしれない」という理解を深めるには、非常に興味深い論文と言えます。
NLRP3インフラマソームとは細胞内のタンパク質複合体で、細菌感染や細胞の損傷といった「危険信号」を感知して炎症反応を開始する自然免疫系の重要な防御機構です。
この記事では、
- 論文の目的・背景
- 方法・対象(動物実験)
- 主な結果
- 鍼灸師として押さえておきたいメカニズム解説
- 臨床への示唆・注意点
- 今後の展望
の順で解説します。
1. 背景と目的

背景
まず、炎症性疼痛とは何か。
- 組織の損傷や刺激(外傷・炎症性疾患・化学的刺激など)によって、免疫反応が起こり、炎症性サイトカイン(例:IL-1β, IL-6, TNF-α など)が放出され、痛みを感じやすい状態(過敏性)が生じることがあります。 (PubMed)
- この過程で、神経(求心路・末梢神経)と免疫(マクロファージ・ミクログリアなど)との相互作用、また酸化ストレス(ROS:活性酸素種)やP2X7受容体などの細胞外ATP受容体、さらに転写因子NF-κB(核内因子κB)経路などが関与することが知られています。 (PMC)
- 特に近年注目されているのがNLRP3インフラマソーム。これは、細胞内において危険信号(DAMPs/PAMPs, ROS, ATP など)を感知して活性化し、カスパーゼ1(caspase-1)を介してIL-1βやIL-18を活性化・分泌させる複合体です。これが「炎症性疼痛」におけるキープレーヤーとして機能する可能性があります。 (PMC)
- 鍼灸・電鍼は、末梢刺激(鍼刺入・電刺激)を通して神経系・免疫系・循環系に影響を与えることが報告されており、「神経-免疫相互作用」の調整、促炎/抗炎サイトカインバランスの改善、NF-κB経路の抑制などがそのメカニズムとして挙げられています。 (PubMed)
- しかし、「電気鍼が具体的にNLRP3インフラマソームの活性化を抑制して、炎症性疼痛を軽減するか」という問いには、明確な整理・統合がなされていなかったのが現状です。
目的
本論文の目的は、動物実験を対象としたシステマティックレビューおよびメタ解析を通じて、電気鍼が炎症性疼痛をどの程度改善するか、またその際にNLRP3関連シグナル(および促炎/抗炎サイトカイン)にどのように働くかを定量的に評価することです。 (PMC)
つまり、私たち鍼灸師にとっては、
「電気鍼が痛みに加えて、炎症・免疫プロセスに作用しうる可能性」
という視点を学ぶ良い機会となります。
2. 方法・対象

この研究の方法を鍼灸師向けにわかりやすく整理します。
対象研究の選定
- データベースとして、PubMed, EMBASE, Cochrane, Web of Science を用いて、「電気鍼/炎症性疼痛/NLRP3」「electroacupuncture/inflammatory pain/NLRP3」などのキーワードで検索を実施。 (PMC)
- 動物実験を対象とし、炎症性疼痛モデル(例:CFA=完全フレンドアジュバント誘導モデルなど)を用いた研究を含む。 (PubMed)
- 研究の品質評価として、改変された10項目チェックリスト(動物実験のメタ解析促進のための機構)を使用。 (PubMed)
データ抽出・統合
- 熱痛閾値(heat pain threshold)および機械的痛閾値(mechanical pain threshold)への電鍼の効果を、標準平均差(SMD)などで統合。 (PMC)
- 血清または組織レベルでの促炎サイトカイン(IL-1β, IL-18, IL-6, IL-12, IL-17, TNF-α, PGE₂ など)および抗炎サイトカイン(IL-10)を評価。 (PMC)
- NLRP3インフラマソーム関連シグナル(例:ROS, P2X7R, NF-κB, 差次的関連蛋白)に関する報告の整理。 (PubMed)
統計手法
- データが得られた10研究を対象にメタ解析を実施。解析ソフトは RevMan を使用。 (PMC)
- アウトカムとして、痛閾値の改善(電鍼 vs 対照)およびサイトカイン変動を評価。
3. 主な結果
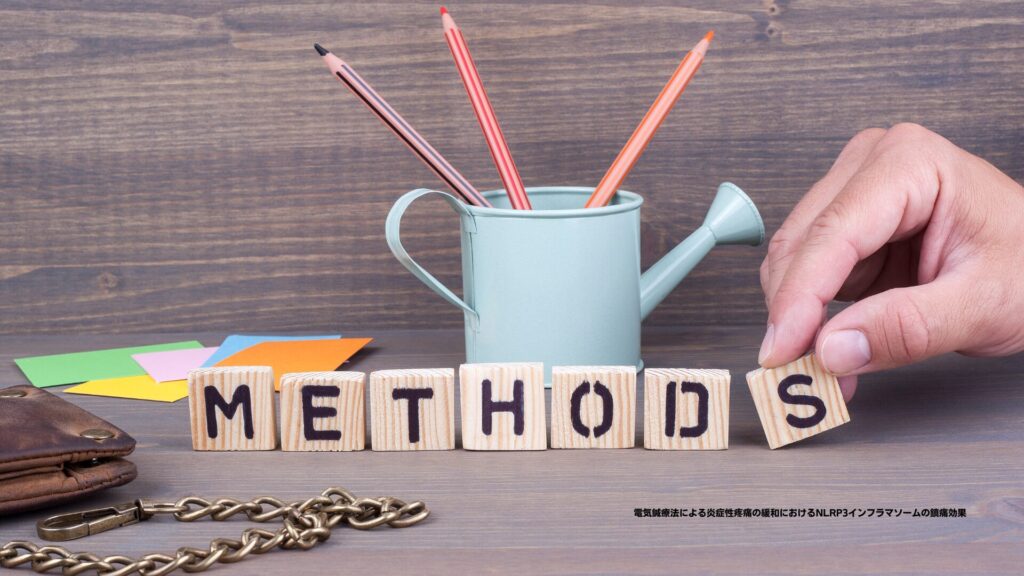
私としては「電気鍼で何が変わったか」「炎症・免疫のどこに働いたか」という観点で整理します。
痛み(痛閾値)への効果
- 熱痛閾値:電鍼により有意に改善された(SMD ≒ −2.74;95 %CI −3.50~−1.98)という結果。 (PMC)
- 機械的痛閾値:同様に改善(SMD ≒ −2.89;95 %CI −3.59~−2.20)という報告。 (PMC)
→ つまり、動物モデル上では「電鍼を行うと熱・機械刺激に対する痛み感受性が低下した」というデータが出ています。
サイトカイン・炎症マーカーの変化
- 促炎サイトカイン(IL-1β, IL-18, IL-6, IL-12, IL-17, TNF-α, PGE₂)について、電気鍼群で有意な低下が確認されています。 (PMC)
- 抗炎サイトカイン(IL-10)は、電鍼群で有意に上昇。 (PMC)
→ これは「電気鍼がただ痛みを和らげただけでなく、促炎と抗炎のバランスを改善させる可能性」を示唆します。
NLRP3インフラマソーム関連シグナルへの作用
- 電気鍼がROS(活性酸素種)を抑制すること、P2X7R(ATP受容体)を介した刺激を抑えること、さらにNF-κB経路を抑制すること等を通じて、NLRP3インフラマソームの発現を低下させるという報告が複数あります。 (PubMed)
- サブグループ解析では、特にCFA誘導モデル(慢性炎症モデル)において、「電気鍼がNLRP3インフラマソームを介して炎症性疼痛を軽減する」という傾向が明らかになりました。 (PMC)
総合的評価
論文は、動物実験の範囲では「電気鍼は炎症性疼痛を軽減しうる」という定量的なエビデンスを示しており、またそのメカニズムとしてNLRP3インフラマソームおよび関連炎症シグナルを介する可能性を支持しています。鍼灸臨床において、炎症に対して「神経-免疫調整効果」があるという仮説に対して、実験的根拠が加わったと言えます。
4. 鍼灸師として押さえておきたいメカニズム解説

ここでは少し私見ですが、鍼灸師として臨床上「なぜ電気鍼が効くかもしれないのか」を理解するための補足です。
NLRP3インフラマソームとは?
- インフラマソームとは、細胞質内に形成される多蛋白複合体で、感染・損傷・ストレス刺激(DAMPs/PAMPs)を受けて活性化されます。
- NLRP3はその中でももっとも研究が進んだタイプで、NLRP3蛋白、ASC(アポプトーシス関連スポンジング蛋白)、カスパーゼ1前駆体などが関与。
- 活性化されると、カスパーゼ1が活性化→IL-1β, IL-18が成熟分泌→炎症反応・細胞死(例えばピロトーシス)を誘導します。 (PMC)
- また、ROS(活性酸素種)、ATPの放出(eATP)、P2X7受容体、NF-κB転写因子などが「NLRP3活性化の起点」として関与していることが報告されています。 (PubMed)
- 炎症性疼痛モデルでは、NLRP3を介したIL-1β/IL-18分泌が痛みの感受性亢進(過敏化)に寄与する可能性が提唱されています。
電気鍼がこの機構にどう働くか?
電気鍼は、末梢神経・求心路・中枢神経・免疫細胞・血液循環などに影響を及ぼします。論文では以下のようなメカニズムが示唆されています:
- 電気鍼によって、ROSの産生が減少する。ROSはNLRP3活性化のトリガーの一つ。これにより、インフラマソームの誘導が減少。 (PMC)
- また、電気鍼がP2X7受容体(eATPを介した刺激の受容体)の発現/活性を低下させるというデータあり。eATP/P2X7RもNLRP3活性化の鍵。 (PMC)
- 電鍼がNF-κB経路を抑制することで、NLRP3やプロ-IL-1β/プロ-IL-18の前段階の転写が低下する可能性あり。 (PubMed)
- 以上の調整により、NLRP3インフラマソームおよびそれに起因する炎症性サイトカイン(IL-1β, IL-18 等)が減少し、結果として痛みの感受性(熱・機械刺激)も低下したと考えられます。
鍼灸師として覚えておきたいポイント
- 神経刺激(鍼・電気鍼)=末梢だけでなく、「神経→免疫」の流れに介入する可能性あり。つまり、鍼を刺入・刺激することで、局所/全身の免疫応答にも影響を与えられる。
- 炎症性疼痛では「痛み=単なる神経刺激の結果」ではなく、「免疫・サイトカイン・インフラマソーム」が痛みを増強・持続させている」場合がある。これを念頭におくと、治療計画も変わってきます。
- 具体的には、炎症マーカーが高い、疼痛が長引いている、通常の鎮痛処置/物理療法で効果が薄いといったケースでは、「電気鍼+炎症制御(神経-免疫アプローチ)」という視点を検討しやすくなる。
- ただし本研究は動物実験であるため、ヒト臨床にそのまま当てはまるわけではありません。臨床応用には、体質・疾病背景・併用療法・安全性・効果判定など慎重に検討する必要があります。
5. 臨床への示唆・注意点

私たち鍼灸師が日常臨床でこの論文から意識できるポイントを整理します。
臨床での示唆
- 電気鍼の適応を考える時に「炎症性疼痛モデル」かどうかを確認する
- たとえば、関節リウマチ・変形性関節症・腱・筋膜炎・術後炎症後疼痛・神経損傷後の炎症成分が残存しているケースなど。
- 炎症マーカー(CRP, ESR 等)や画像所見(MRI・エコーでの滑膜肥厚・腱周囲浮腫など)があれば、炎症成分が強いと仮定できます。
- そのような場合、「電気鍼+炎症制御的アプローチ(免疫調整的視点)」を検討しやすいと言えそうです。
- 鍼/電鍼の刺激量・頻度・部位選択に工夫を加える余地あり
- 本研究では「電気鍼(鍼+電刺激)」を対象としています。刺入だけの鍼と比べて電気刺激を併用することで、神経・免疫への刺激が強く、インフラマソーム抑制に結びつった可能性があります。
- よって、通常の手技鍼でも良いですが、炎症性疼痛には「電気鍼」で刺激強度を少し高める選択肢を考えてもよいでしょう。
- 刺入部位として、末梢痛部だけでなく、求心路/背部/関連神経支配領域のアプローチも併用することで神経-免疫経路に介入しやすくなります。
- 経過観察・効果判定指標を明確にする
- 痛みスケール(VRS, NRS 等)、痛みの質(刺すような/鈍い/灼熱感など)、可動域、腫れ・熱感・動作痛の有無など。
- 炎症性マーカー(臨床に出ていればCRP, ESR等)や超音波所見(滑膜の厚さ・エコーでの腱周囲浮腫)を併用できれば、施術効果の“炎症制御”という視点でも評価できます。
- 本論文のように「痛閾値(熱・機械刺激)変化」という指標は臨床では直接計りにくいですが、痛み軽減・機能改善・炎症徴候減少という形で捉えられます。
- 他療法・薬物療法との併用を視野に入れる
- 電気鍼だけで解決できるとは言えません。抗炎症薬・理学療法・運動療法などと組み合わせて「炎症→疼痛→機能障害」という悪循環を断つことが理想です。(これは絶対)
- 特に、薬物鎮痛だけでは炎症・免疫プロセスが残存している場合、鍼灸+電気鍼が“補助的”に働ける可能性があります。論文でも「鎮痛薬使用量を減らしうる可能性あり」と結論しています。 (PMC)
注意点・限界
- ヒト応用のエビデンスが限定的:本論文は全て「動物実験(主にラット/マウス)」を対象としています。ヒト臨床で同様の効果がどの程度出るかは、さらなる臨床試験が必要です。 (PubMed)
- モデル・条件の差異:炎症誘導法、鍼・電鍼の刺激条件(強度・周波数・点数・時間)・動物種・部位などは研究ごとに異なります。臨床にそのまま転用するのは慎重に。
- 安全性・個別対応:電鍼を行う際の刺激強度・頻度・患者の全身状態(心疾患・ペースメーカー・出血傾向など)を考慮する必要があります。
- “炎症性”か“神経性”かの見極め:炎症が主因の痛みなのか、あるいは慢性痛として神経変性・感作が主因となっているのかで、鍼灸アプローチは変わってきます。本研究は「炎症性疼痛モデル」であり、純粋な神経障害性疼痛ではないことに注意。
- 治療継続・反応の個人差:動物実験では比較的コントロールされた条件で施術効果が出ていますが、臨床では個人差・併存疾患・生活習慣・心理的要因などが関与します。
6. 今後の展望・鍼灸師としての取組み
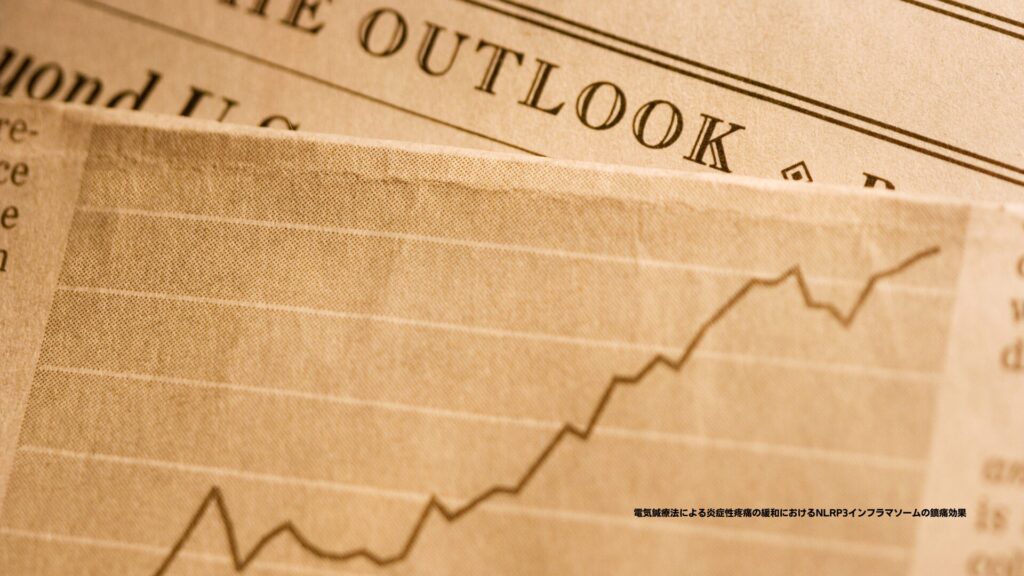
この論文を契機として、鍼灸師が今後どう取り組んでいくか、方向性を考えてみます。
臨床研究・症例報告の拡充
- 鍼灸・電気鍼を用いた“炎症性疼痛患者”を対象に、痛み改善に加えて「炎症マーカー」「超音波所見(腱・滑膜浮腫)」「機能改善」なども併せて記録することが有益です。
- 鍼灸院・接骨院・整形クリニックとの協働で、炎症性疾患(例:変形性関節症・腱付着部炎・滑液包炎など)に対する電気鍼+標準ケアという臨床デザインを検討する価値があります。
- 刺激条件(周波数、電流強度、施術回数・頻度・部位)を変えて(例:低頻度 vs 高頻度電鍼)どの条件が炎症制御・痛み制御に有効かを探る“臨床的パラメータ探索”も興味深いです。
臨床実践における応用ビュー
- 炎症が明らかな疼痛患者に対して、鍼ではなく「電気鍼」を第一選択または併用と考えるケースを検討してみましょう。ただし、患者の安全性・耐性を踏まえて刺激量を調整することが重要。
- 鍼灸師として、炎症-免疫という視点を持つことで、「痛みの根本原因を探る」姿勢が強化されます。単なる“コリをほぐす”“ツボを使う”ではなく、“炎症・免疫–神経系連関”という視点も加えることで、患者説明や治療設計が深まります。
- 患者説明の際、「この電気鍼は痛みを取るだけでなく、炎症を鎮め、免疫の働きを整える方向にも働く可能性があります」といった言葉を用いることで、患者の納得・治療継続率アップにもつながるかもしれません。
将来的な課題
- ヒトを対象としたランダム化比較試験(RCT)および長期フォローアップ研究を待つ必要があります。
- “どの種類の炎症性疼痛”(急性 or慢性、関節/筋/腱/神経)に電鍼が最も有効か、エビデンスを積む必要あり。
- 安全性・刺激パラメータ・コスト対効果・併用療法との最適化(例えば、運動療法・物理療法・薬物療法とのシナジー)を検討すべきです。
- 鍼灸臨床において「炎症マーカーを測る」「超音波で腱・滑膜浮腫を観察する」などの手法が一般化していません。こういった“可視化できる炎症指標”と鍼灸との連動を進めることで、鍼灸の効果証明・説明力が強まるでしょう。
まとめ
本論文は、鍼灸・電鍼の臨床応用に対して次のような示唆されます。
- 電気鍼は、炎症性疼痛モデルにおいて、痛み(熱・機械刺激に対する閾値)を有意に改善する動物実験データが存在する。
- そのメカニズムとして、促炎サイトカインの低下・抗炎サイトカインの上昇、さらにはNLRP3インフラマソーム関連シグナルの抑制という“神経-免疫”の観点が示唆されており、鍼灸師が持つ「経絡・ツボ・気血」視点と“免疫・炎症”視点の架け橋になりうる。
- 臨床においては、「炎症成分が比較的強い疼痛」「通常の鍼で反応不十分なケース」「鍼灸+他療法併用を検討すべきケース」などで、電気鍼を含む治療プランを考える価値があります。
- ただし、ヒト臨床への転帰・個別対応・安全性・併用療法などには慎重さが必要であり、さらなる臨床研究の蓄積が望まれます。
鍼灸師として、今後ますます重要となる「神経–免疫–炎症」の視点を治療デザインに取り入れ、“痛みだけでなく、炎症の痕跡・免疫の働き”にも働きかけるアプローチを磨いていきましょう。

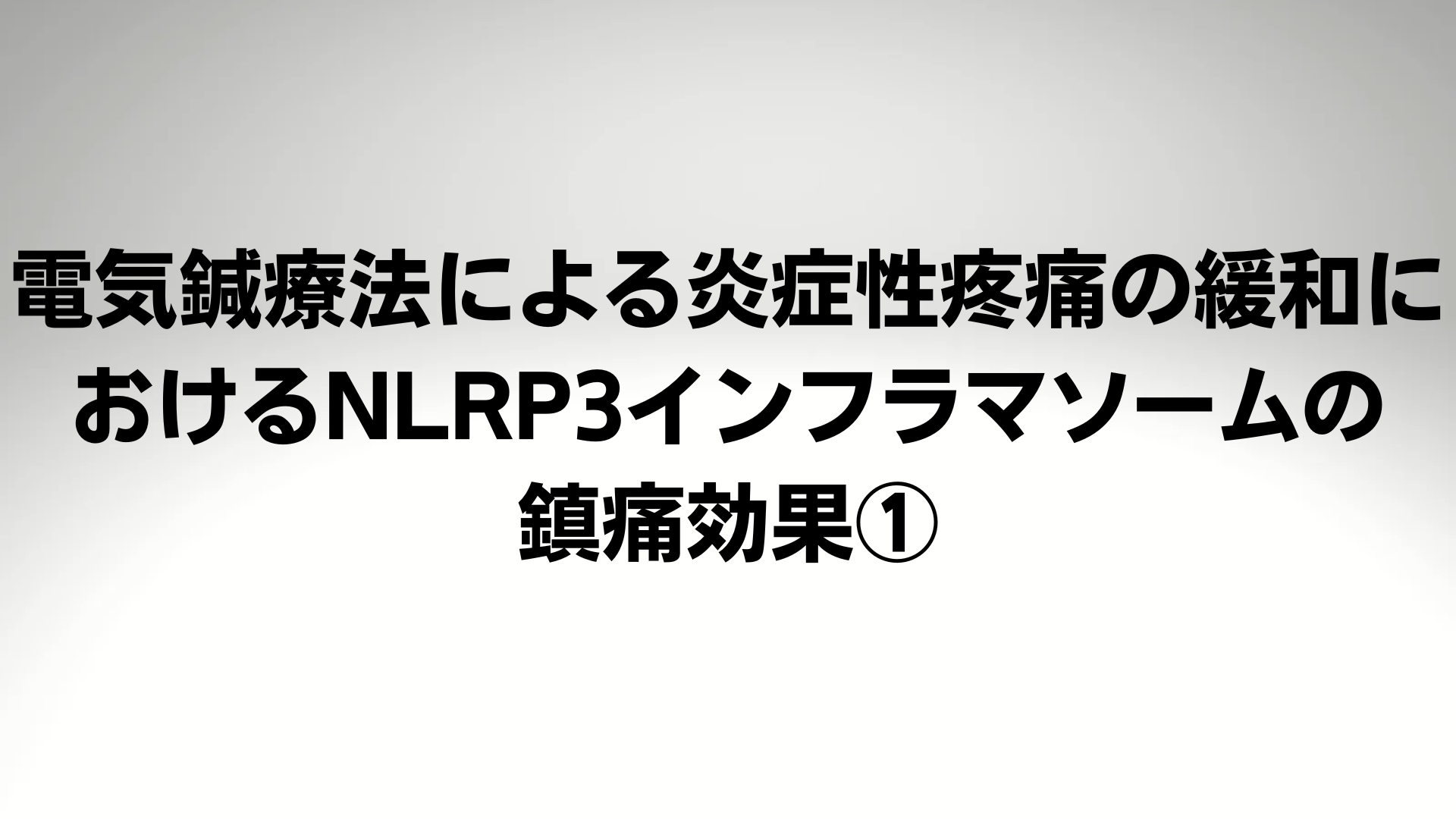
コメント