こんにちは!
陣内です。
今回も論文をご紹介していきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
今回は、Manual Therapy, Posturology & Rehabilitation Journal に掲載された
「ラジオ波が筋肉再生に与える影響」に関する興味深い研究を私の視点からわかりやすくご紹介します。
元のリンクはこちらです。
近年リハビリ、手技療法、トレーニング指導の現場で「ラジオ波(RF)」を使う機会が増えていますよね。
「深部の温熱効果で血流を上げる」「治癒を促進する」といった説明はよく聞きますが、実際に筋線維の再生にどんな変化をもたらすのか?――その点を、科学的に検証した貴重な論文です。
■ 研究の概要:ラットの筋損傷モデルでRFの影響を観察

この研究では、ラットの腓腹筋に意図的な損傷を与え、
ラジオ波(0.5 MHz)を用いた施術が組織再生にどんな影響を及ぼすかを観察しています。
40匹のラットを4グループに分けました。
| グループ | 条件 |
|---|---|
| G1 | 正常筋(損傷・RFなし) |
| G2 | 損傷のみ(RFなし) |
| G3 | 損傷+72時間後にRF施術 |
| G4 | 損傷+7日後にRF施術 |
RFは、パワー45%・2分間の照射という設定。
損傷後21日目に筋組織を採取し、**顕微鏡レベルでの変化(筋線維・炎症・線維化など)**と、**生体力学的強度(引っ張り試験)**を評価しました。
■ 結果:RF施術のタイミングで再生プロセスが変化

研究の結果、もっとも特徴的だったのは「施術タイミングの違い」です。
① 損傷72時間後にRFを行ったグループ(G3)
・炎症の進行が抑えられ、筋線維が再生方向に整列する傾向が観察されました。
・肉芽組織の形成も適度で、治癒がスムーズに進む印象。
・組織の見た目(形態学的回復)は対照群(G2)よりも良好でした。
② 損傷7日後にRFを行ったグループ(G4)
・炎症が強く残存し、線維化(瘢痕化)傾向が確認されました。
・筋線維が不規則で、再生よりも「固まってしまう」方向へ進行。
③ 力学的強度に関しては…
全グループ間で統計的な差はなし。
つまり、見た目(組織の構造)では改善傾向があるものの、
実際の「筋力」や「耐久性」まで改善したとは言い切れないという結果でした。
■ 臨床への示唆:RFの「使いどき」がカギ

セラピストとしてこの研究から得られる最大のポイントは、
「いつ施術を行うか」=タイミングが重要ということです。
● 炎症期へのアプローチをどう考えるか
筋損傷直後の数日は、身体の中で「炎症」「浮腫」「細胞修復のスイッチ」が同時進行しています。
RFによる深部加温は血流や代謝を上げますが、早すぎるタイミングでは炎症を助長するリスクもあります。
この研究では「損傷72時間後」――つまり急性期を少し過ぎたタイミングでのRFが有効でした。
この時期は、炎症が収まりつつ修復プロセスに入る段階。
深部温熱で血流・酸素供給を促すことが、再生細胞の働きを助けたと考えられます。
一方、7日後ではすでに瘢痕化が進み始めるため、線維化を助長してしまう可能性があります。
つまり「炎症が落ち着きはじめた段階での適度な熱刺激」が、理想的な使い方と言えそうです。
■ ラジオ波施術のメカニズムを整理しておこう

ラジオ波(RF)は、1秒間に数十万〜数百万回の高周波電流を体内に通し、
組織の抵抗によって深部から発熱を起こします。
- 皮下2〜10cmの筋層まで温めることが可能
- 血管拡張 → 酸素・栄養供給の増加
- 老廃物排出の促進(リンパ循環改善)
- 組織の柔軟性向上・疼痛緩和
セラピストが使う意義は、「表面を温める」よりもむしろ、
“深部の代謝を整える”ことにあります。
今回の研究では、この生理的変化が損傷筋の修復プロセスに良い影響を与える可能性を裏づけた形です。
■ ただし注意したいポイント

ラット実験の結果をそのまま人間に当てはめるのは早計です。
以下の点は臨床応用時に考慮が必要です。
- 出力・照射時間・部位が異なる
人の筋肉は厚さ・血流量が違うため、温度上昇の仕方も変わります。
機器設定は動物モデルより低出力でも十分効果が出る場合があります。 - 損傷の種類によって反応が違う
軽度の筋膜炎と、肉離れのような線維断裂では回復メカニズムが異なります。
損傷のステージを見極め、RFを使うタイミングを慎重に判断する必要があります。 - 深部過熱によるリスク
過剰な加温は組織を逆に壊す恐れがあります。
痛み・熱感を確認しながら「気持ちよい温かさ」程度を維持するのが安全です。
■ セラピストが実践に活かすためのヒント
① 炎症期〜修復期への移行を見極める
損傷直後(1〜2日)は冷却・安静が原則。
3日目以降、腫れや発赤が引き始めたタイミングで温熱介入を検討するとよいでしょう。
RFだけでなく、超音波温熱や手技療法もこの時期に合わせると効果的です。
② RFは「治す」ではなく「治りを整える」ツール
ラジオ波自体が筋線維を“修復する”わけではありません。
細胞が持つ自然治癒力を後押しする環境づくりが役割です。
血流改善 → 栄養供給 → 修復促進という流れを意識して、他のリハビリと組み合わせると◎。
③ 再生期の運動療法と組み合わせる
温熱刺激のあとに軽い収縮運動やストレッチを入れると、
再生筋のコラーゲン配列が整いやすくなり、線維化を防ぎやすいとされています。
「温めて → 動かす」リズムを治療プランに組み込みましょう。
④ クライアントへの説明を丁寧に
「温めると早く治る」と単純に伝えるのではなく、
「今の段階では熱で血流を促すことが、修復細胞の働きを助けます」など、
科学的な背景をやさしく説明すると、信頼感が高まります。
■ 今後の展望:機能回復まで検証する研究へ

今回の研究は「組織再生」に焦点を当てていますが、
臨床で大切なのは“見た目が治ること”よりも“動けるようになること”です。
今後は、
- 筋収縮力・柔軟性への影響
- 他の物理療法(超音波・電気刺激)との併用効果
- 実際のリハビリ期間短縮の有無
など、機能的回復を含めた臨床研究が期待されます。
■ まとめ
- ラジオ波(RF)療法は、筋損傷後72時間以内の適用で組織再生を助ける可能性が示唆された。
- 7日以降の遅い時期では、逆に線維化を助長するリスクがある。
- 組織の形態改善は見られたが、力学的強度の改善は明確ではない。
- 臨床では、炎症期を過ぎて修復期に入る「ちょうどよいタイミング」で温熱刺激を行うことが鍵。
- RFは「治す道具」ではなく、「治癒を助ける環境を整えるツール」として活用する。
筋肉損傷の治療は、「いつ」「どのように」介入するかで結果が大きく変わります。
今回の研究は、私たちセラピストが施術のタイミングと目的を再確認する良いきっかけを与えてくれました。
ラジオ波を使う方も、これから導入を検討している方も、
「炎症が落ち着き始めた頃こそベストタイミング」という視点を、
ぜひ日々の臨床に活かしてみてください。

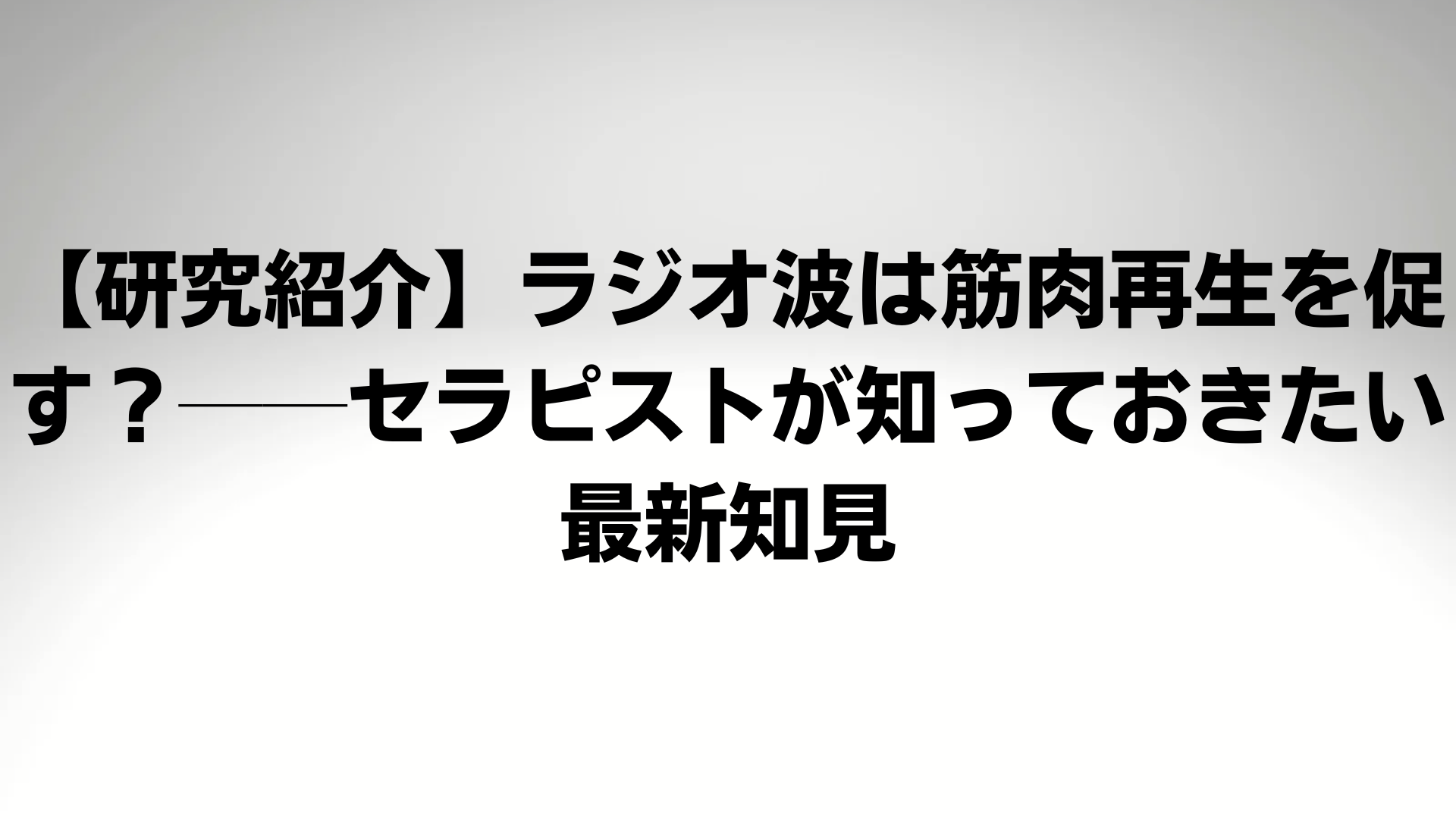
コメント