こんにちは!
陣内です。
今回は論文について書いていきたいなって思います。
もちろん私は研究者などではなく臨床しかしていない人間なので専門分野の方は生暖かい目で見ていてくれたら幸いです。
リンクはこちらから
自律神経系の学びにおすすめな本はこちら!
はじめに
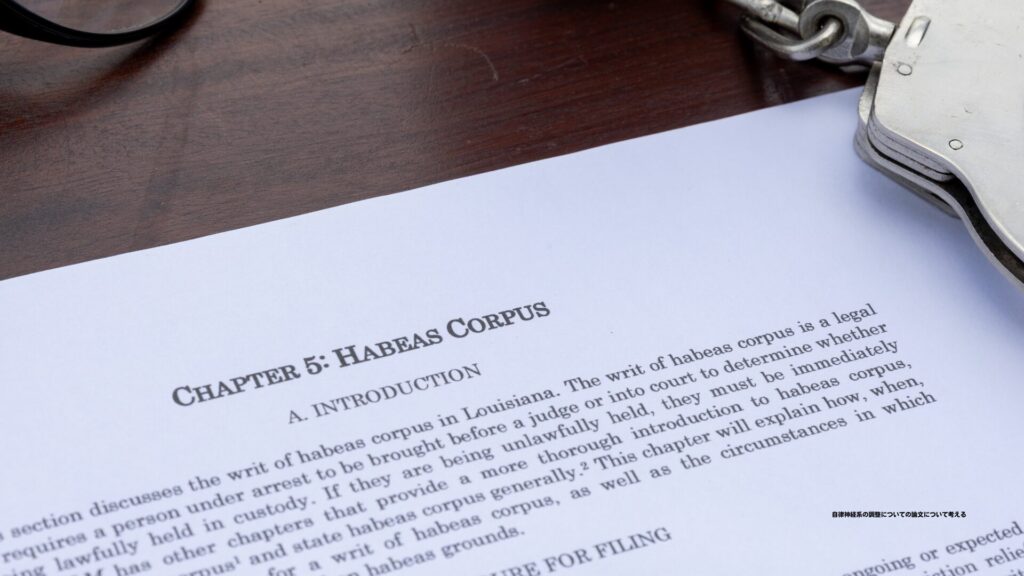
最近、鍼灸を含めた東洋的/統合医療の領域でも、自律神経系や循環器・心拍などに着目した研究が増えています。今回ご紹介する論文は、 Does electroacupuncture reducing heart rate rebalance autonomic nervous activities JN 00132.2024)(著者:S.C. Tjen-A-Looi ら、2024年)です。 タイトルから示唆されるように、「電気鍼(あるいは電気刺激付き鍼/電鍼)による心拍数低下効果が、自律神経活動の再バランス(リバランス)にどうつながるか」を動物実験で探ったものです。
鍼灸師として日々の臨床に活かせる「ヒント」が詰まっていますので、ポイントを分かりやすく整理し、臨床応用も含めて考えてみましょう。
研究の背景

まず、なぜこの研究が行われたかを整理します。
- 自律神経系(例えば交感神経・副交感神経)は、心拍数・血圧・血管抵抗などを通じて、体の内環境(恒常性)を維持しています。
- 鍼や電鍼が、自律神経活動を調整し、結果として「心拍数を下げる」「血圧を下げる」などの効果を報告する研究があります。
- しかし、「なぜ/どのように」自律神経が変化し、その結果として心拍数低下に至るのか、メカニズムは十分には明らかではありません。
- そこで、本研究では電鍼が心拍数低下を引き起こす際に、自律神経(特に交感/副交感のバランス)をどう調整しているかを、実験モデルで検証しようとしたわけです。
臨床において「心拍が高め」「交感過剰と考えられる状況」「ストレス状態」「血圧が若干高め」などの患者さんに対し、鍼灸・電鍼でどう対応できるかを考える上で、こうしたメカニズム理解は非常に有用です。
研究の目的と方法

本研究の目的は、「電鍼/電気刺激付き鍼によって心拍数が低下する際、自律神経活動はどう変化しているか」を明らかにすることです。特に、交感神経活性の低下、副交感神経活性の増加、あるいはその両方の可能性を検討しています。
方法としては、動物実験モデル(論文ではラット・ウサギ等が用いられている)において、特定の神経反射・循環反射を誘発し、それに対して電鍼刺激を加え、心拍・血圧・神経活動(交感神経・副交感神経マーカー)を記録しています。例えば、興奮性循環反射(心拍数・血圧を上げるような刺激)を与えた後、電気鍼を加えた群と未刺激群を比較するといった設計です。
このような実験により、「心拍数低下」のみならず「自律神経のリバランス(自律神経活動がどちらかに偏っている状態から、よりバランスのとれた状態へ移行する)」という観点が評価されています。
主な結果

論文から読み取れる主要な結果を、かみ砕いて整理します。
- 電鍼刺激を加えた群では、興奮性循環反射により上がっていた心拍数・血圧が、有意に低下しました。つまり、電鍼が「反射で上がった心拍数・血圧を抑える」効果を持つことが確認されました。
- 自律神経活動を示す指標(例えば交感神経出力、副交感神経マーカー)において、交感優位の状態からより穏やかな活動へ変化しており、電鍼が自律神経のバランスを改善する可能性が示されました。具体的には、交感神経活性が抑制され、副交感神経活性が相対的に高まる傾向が見られたようです。
- また、刺激を与えた特定の脳幹部位(例:延髄の rostral ventrolateral medulla=RVLM など)や神経伝達物質(例:アデノシン A2A 受容体、オピオイド系)などが、この反射制御・自律神経制御の鍵となっている可能性が示唆されました。
- 以上の結果から、「電鍼が単に針刺激によって筋肉・経絡・局所神経を刺激するだけでなく、循環反射・自律神経反射系を介して、体全体の自律神経バランスを整える」というモデルが支持されました。
鍼灸臨床への“読み替え”とヒント

では、鍼灸師として日々の臨床において、この研究結果をどう臨床に落とし込むか、どう活かしていけるかを整理してみましょう。
・対象となるケース
この研究で示されたような「心拍数が高め」「交感神経が優位と考えられる」「血圧高め」「ストレス or緊張状態が続いている」などの患者さんが、鍼灸治療の対象として考えやすいでしょう。例えば「寝付きが悪い」「浅い眠り」「手足が冷える・末梢血流が弱い」「肩こり・頭痛・自律神経の乱れが気になる」なども含まれます。
・電鍼/低頻度刺激の活用可能性
研究では“電鍼”や“電気刺激付き鍼”を用いており、鍼灸院で扱っている電刺激装置や低周波・中周波の通電刺激を用いたアプローチがこれに近しくなります。つまり、「鍼を打った後、電気刺激を加えることで、自律神経系に対してより強力/明確な調整作用を狙える」というヒントです。
・刺激ポイント・刺激量・頻度の検討
研究では、特定の神経反射を誘発する条件での刺激が用いられています。臨床にそのまま当てはめるならば「どのツボ・どの部位を用いるか」「電流の強さ・周波数」「刺激時間」「頻度(治療の回数や間隔)」を、患者さんの「自律神経負荷」「交感過剰状態」「回復力/睡眠の状態」などを踏まえて慎重に設計する必要があります。
・“リバランス”を狙う観点
鍼灸治療において「交感/副交感の偏りを整える」「オンとオフの切り替えを促す」「体を“鎮める”“休ませる”ように導く」という視点があります。今回の研究はまさにこの視点を裏付けるものであり、「ただ痛みを取る」「ただ筋肉を緩める」だけでなく、「自律神経系を整える」ことが治療の目標になることを示しています。
・臨床でのアドバイスとして
- 初回の問診で「最近、心拍や血圧が高め」「寝つき/眠りが浅い」「動悸・息切れ・手足の冷え」など自律神経過剰を示唆する症状がないかをチェックしておく。
- 電鍼を用いる場合は、まず低めの刺激(電流・周波数とも)から始め、患者さんの反応(リラックス感・眠気・心拍数の変化など)を観察。
- 治療直後・数時間後・翌日の反応(睡眠の質・疲労感・心拍・血圧)をフォローし、「治療によって自律神経系に良い変化が起きているか」を確認。
- 定期的な治療では、患者さんがより“交感優位 → 副交感優位 orバランス”へ移行できるよう、刺激量・頻度・治療間隔を調整。
- 鍼灸以外にも「睡眠環境」「食事」「ストレス・休息の取り方」「軽い運動や呼吸法」など、自律神経に影響を与える生活習慣面を併せてアドバイス。
注意点・今後の展望

もちろん、この研究には「動物実験」であるという制限があります。人で同じような条件・効果が必ず起きるとは限りません。また、鍼灸治療の“効果”を保証するものではなく「可能性」「メカニズムの一端を示すもの」として理解することが大切です。
さらに、以下のような視点も重要です。
- 患者さんの状態(年齢・既往歴・心疾患・薬の使用など)を考慮する。
- 鍼・電鍼は万能ではなく、場合によっては専門医との連携が必要。
- 刺激が強すぎると交感神経を逆に刺激してしまう可能性もあるため、治療前後の変化を丁寧に観察。
- 今後、「鍼灸+電鍼による自律神経調整」に関して、人を対象とした臨床試験がさらに報告されることが期待されます。
このように、現在の知見は「鍼灸による自律神経へのアプローチ」に有望な根拠を与えてくれています。臨床としては、「鍼灸治療=筋・骨格・経絡への刺激」という枠に留まらず、「神経・循環・自律まで広げる視点」を持つことで、治療の幅・深みが増すのではないでしょうか。
まとめ
- 研究「Does electroacupuncture reducing heart rate rebalance autonomic nervous activities」では、電鍼刺激が興奮性循環反射による心拍数・血圧上昇を抑制し、交感神経優位の状態から自律神経のバランスを改善する可能性が示されました。
- 鍼灸師としては、「自律神経過剰」「交感優位」の患者さんに対して、電鍼を含む治療を検討する際、このようなメカニズムを意識すると、より治療設計が明確になります。
- 臨床で効果を高めるためには、刺激量・頻度・患者さんの生活背景を丁寧に把握し、「バランスを整える」視点を持つことが鍵です。
- 今後、人を対象とした臨床研究の報告が待たれますが、現時点でもこの研究は、鍼灸・電鍼治療の自律神経調整効果に関して有益なヒントを提供してくれています。
鍼灸治療は、経絡・ツボ・鍼だけでなく、『体の内側を流れる神経・循環・自律系の流れ』にも働きかける手段です。この研究をきっかけに、ぜひ「自律神経を整える鍼灸」という視点を、日々の臨床に役立てていただけたらうれしいです。

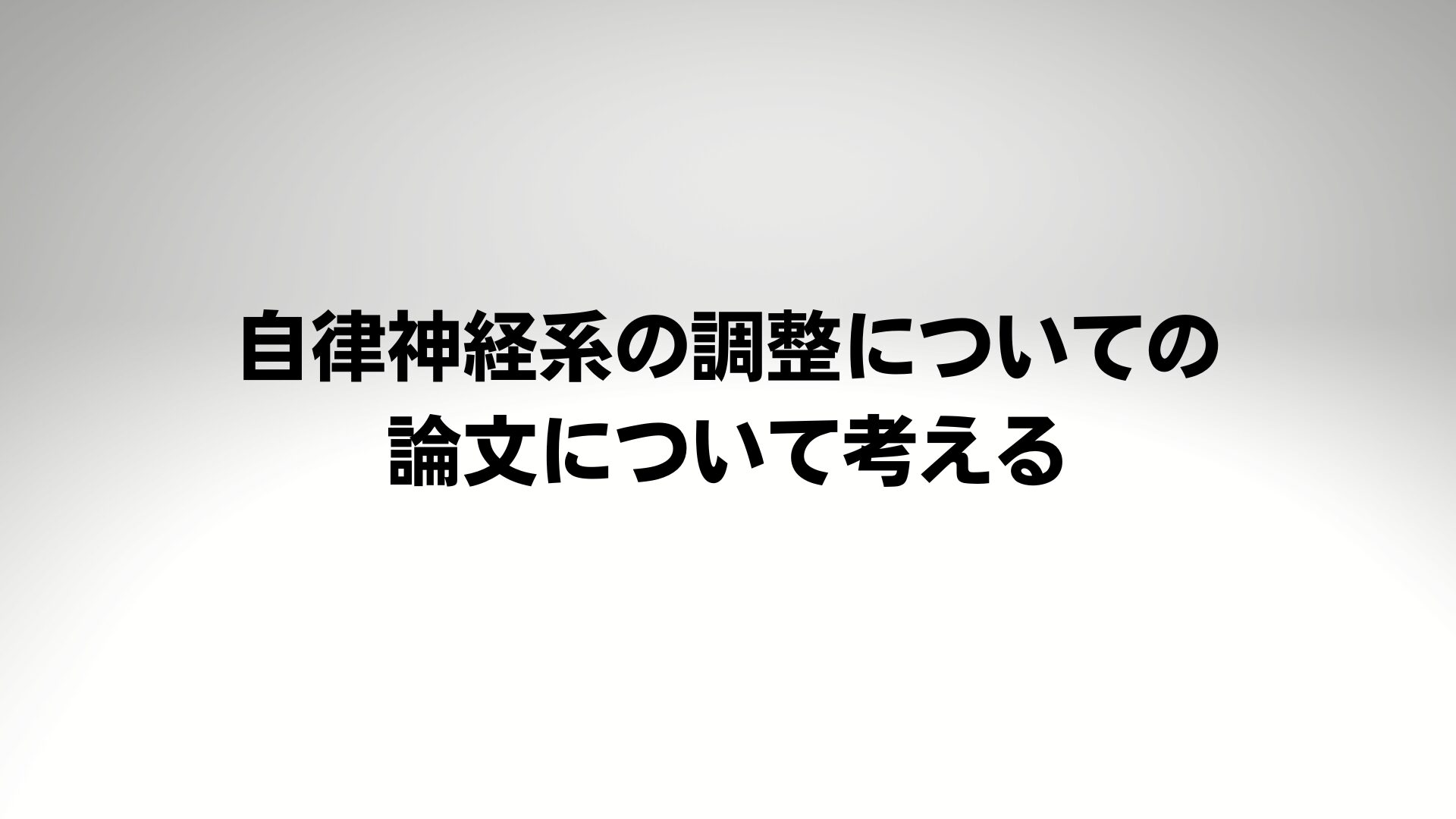

コメント