こんにちは!
陣内です。
今回は動画を簡単な記事にしていきますね!
五十肩・投球肩障害に対する新しい視点からのアプローチ
肩関節疾患の臨床に携わっていると、「可動域は制限されているが、構造的な損傷では説明がつかない」「肩の“奥の重さ”が取れない」というケースにしばしば遭遇します。こうした症例の多くに共通して関わっているのが、棘下筋(infraspinatus)です。
今回の動画「基礎から鍼灸臨床へ~棘下筋刺鍼~徹底解説(五十肩、投球肩障害など)」では、この棘下筋を中心に、解剖学的な理解から実際の刺鍼技術、そして臨床応用までを非常に丁寧に解説しています。
この記事では、動画内容を踏まえながら、臨床に役立つ棘下筋刺鍼の要点を整理してみましょう。
棘下筋の解剖学的理解:肩の動きを支える“裏方”
棘下筋は、肩甲骨の棘下窩から起始し、上腕骨大結節後面に停止する筋肉です。主な作用は肩関節の外旋、補助的に外転動作に関与します。
いわば「腕を外に開く・回す」動きのなかで活躍する、肩関節の安定性を担う重要な筋群です。
臨床上、棘下筋は次のような症状に関与することが多く見られます。
- 五十肩(特に外旋・外転制限を伴うタイプ)
- 投球肩障害(リリース時の後方痛)
- 肩甲骨周囲筋のアンバランスによる筋緊張
- 肩の後方の“だるさ”“重さ”“引っかかり感”
特に、「肩の上がりづらさ」や「外旋の制限」がある場合、棘下筋が過緊張し、筋膜の滑走不全を起こしているケースが少なくありません。
動画の中でも、「肩上部が鉄のように固まる」「肩甲挙筋をほぐしても抜けきらない」という場面で、この棘下筋へのアプローチが鍵になると強調されています。
棘下筋刺鍼の目的:筋緊張の解除と運動連鎖の再構築
棘下筋刺鍼の狙いは、単に局所の硬結をゆるめることではありません。
“肩甲骨-上腕骨リズム”の回復こそが最大の目的です。
五十肩や投球障害の症例では、疼痛や可動域制限により「肩甲骨が動きすぎる」「上腕骨が動かない」といったアンバランスが起こりがちです。結果として、棘下筋が過剰な緊張を強いられ、筋膜が硬くなり、さらに動きが制限される――という悪循環に陥ります。
この循環を断ち切るには、棘下筋の深層に直接アプローチし、滑走を回復させることが重要です。
刺鍼により局所血流が改善されるとともに、固着していた筋膜間の滑りが戻り、神経受容器の過敏化が鎮まります。
その結果、肩関節の“引っかかり”が消え、動きがスムーズになるという臨床変化が期待できます。
触診と評価:まずは“動き”で探る
動画では、施術前に動きの評価を丁寧に行うことが強調されています。
代表的なチェックポイントは以下の通りです。
- 外旋可動域の確認
外旋時に肩の後方(棘下筋部)に張りや抵抗感が出るか。 - 外転動作時の引っかかり
肩を横から上げるとき、中盤で“止まる感覚”や痛みが出るか。 - 圧痛・硬結の触診
肩甲棘を指標に、その下の棘下窩を母指で触診し、深部に硬い索状物や圧痛を探す。
これらを総合して、「この症状には棘下筋が関与している」と仮説を立てることが、刺鍼前の準備として欠かせません。
刺鍼手技のポイント
動画内では、臨床家向けに非常に実践的な刺鍼手順が紹介されています。
以下はその要点をまとめたものです。
- 体位
うつ伏せまたは側臥位で、肩甲骨の動きを妨げない姿勢を取ります。
患者がリラックスできる体勢を優先し、腕を軽く前方に置くと筋が緩みやすくなります。 - 刺入部位と方向
肩甲棘下の外側1~2横指、肩甲骨外縁のやや内側を指標にします。
刺入角度はやや下方・内側に向け、肩甲骨に沿うように刺鍼します。
これは棘下筋の走行(外上方→内下方)に沿っており、筋繊維の緊張を効率的に解放するための角度です。 - 深さ
個人差はありますが、通常20~40mm程度。
骨に当たる手前で止め、筋層の反応を確認します。 - 得気・筋反応
鍼先が硬結に入ると、独特の「響き」や筋のわずかな収縮が生じます。
患者に過度な不快感を与えない範囲で、その反応を確認します。 - 鍼後の動きの誘導
刺鍼後に肩を外旋・外転させる軽い運動を行うことで、解放された筋膜が動きとともに滑走しやすくなります。
これは、動画内でも特に強調されていた“動きの再教育”の要素です。
臨床での応用:こんなケースに有効
① 五十肩(拘縮型)
肩甲骨の動きに頼りすぎて上腕骨が動かなくなっているタイプ。
棘下筋刺鍼で深部の緊張を解除することで、リハビリ動作の初期段階がスムーズになります。
② 投球肩障害(リリース後方痛)
投球動作では、リリース期に棘下筋が急激に伸張されます。
この部位が過緊張・短縮していると、フォロースルーで痛みが残ります。
刺鍼によって滑走性を改善し、可動域と筋の協調性を回復させることが可能です。
③ 肩上部の慢性コリ(肩甲挙筋・僧帽筋上部の過緊張)
上部ばかりほぐしても抜けないケースでは、棘下筋が“根っこ”で張っている場合が多いです。
深層の硬さを解放すると、肩甲挙筋・僧帽筋の緊張も自然に緩むことがしばしばあります。
安全と配慮
棘下筋の刺鍼では、安全管理が何より重要です。
肩後面には、肩甲上神経・肩甲回旋動脈などの重要構造が走行しています。
また、肩甲骨に沿って深く刺すため、角度を誤ると胸腔方向へのリスクもあります。
そのため、以下のポイントを必ず守りましょう。
- 骨に向かって平行に刺す(深く貫通させない)
- 鍼を進める際は、常に抵抗感と深度を確認
- 不快な響きや放散痛が強い場合はただちに抜鍼
安全に留意しながら、「効かせるけど攻めすぎない」絶妙なバランスを取ることが、臨床の腕の見せ所です。
鍼後の指導とセルフケア
刺鍼後の患者指導も非常に大切です。
筋膜が解放された状態を維持するためには、「動かす」ことが欠かせません。
- 肩を小さく回す運動を1日数回
- お風呂上がりに肩甲骨周囲を温める
- デスクワーク中に肩をすくめる姿勢を避ける
これらを意識させることで、施術効果を持続させることができます。
まとめ:肩の“奥”にアプローチできる武器を
棘下筋は、肩の動きを陰で支える“職人”のような筋肉です。
表層の筋肉ばかりをアプローチしていても取れない肩の重さ・だるさの背後、この筋の拘縮が潜んでいることは少なくありません。
動画で解説されているように、棘下筋刺鍼は五十肩や投球肩障害などの難治例にも有効な臨床手技です。
ただし、解剖理解と安全な刺入技術、そして“動きを戻す”という意識が伴ってこそ効果が最大化されます。
肩の刺鍼は「深く刺す」だけではなく、「深く理解する」ことが求められる分野です。
棘下筋刺鍼は、その理解を一段深める絶好のきっかけとなるでしょう。

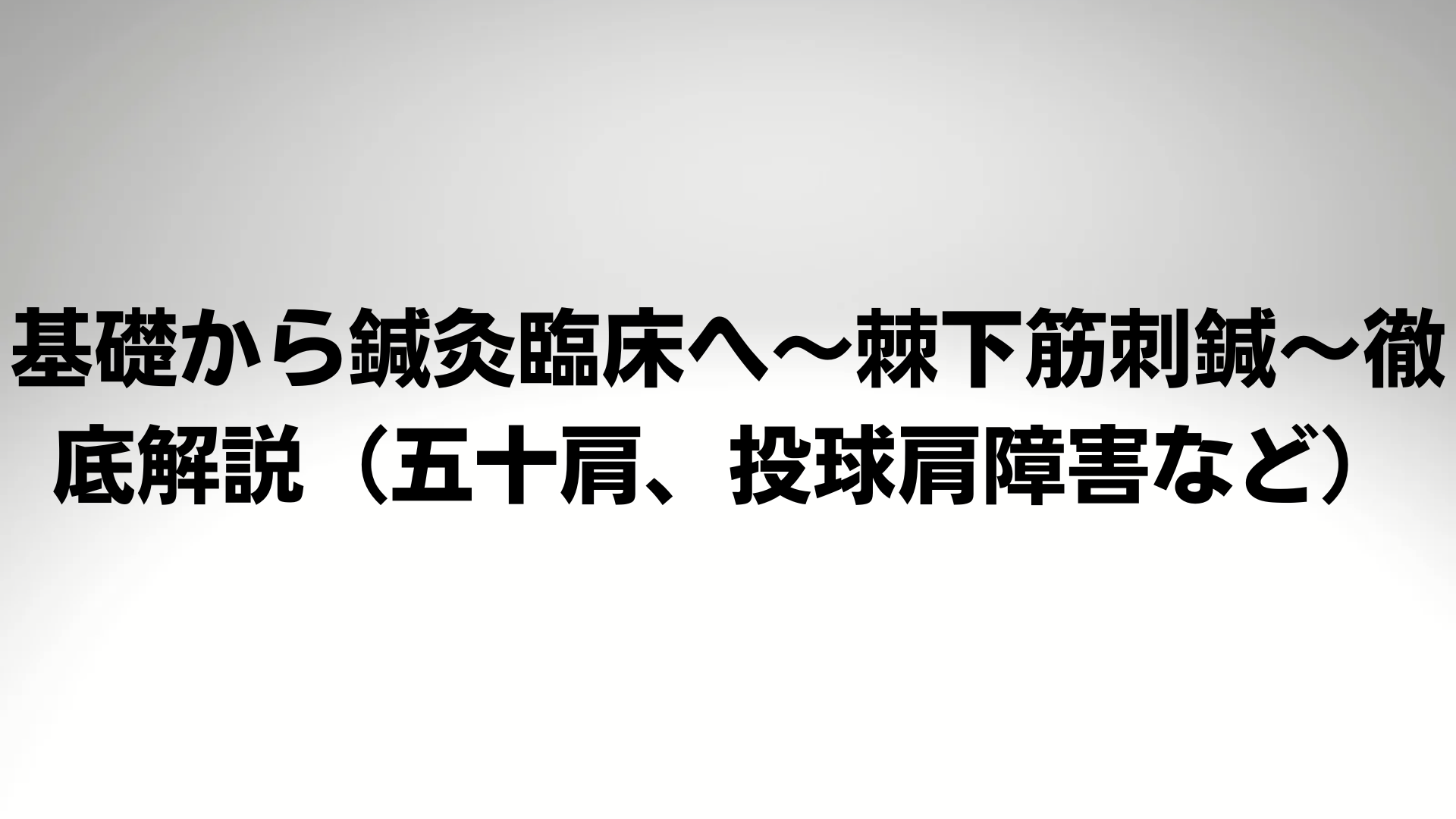
コメント