※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
参考文献はこちら
すべてを鵜呑みにしないでくださいね!
宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼
お金持っている人は新品買ってね!
はじめに

糖尿病性神経障害性疼痛(Diabetic Neuropathic Pain: DNP)は、糖尿病患者さんにとって大きな悩みの一つとなっています。
現代医学における薬物療法も進歩してきていますが、効果が不十分であったり、副作用の問題があったりすることも少なくありません。
そうした中で、東洋医学の伝統的な治療法である鍼灸、特に電気刺激を加える電気鍼(Electroacupuncture: EA)が注目を集めているようです。
本記事では、Ma et al.(2023)が報告した研究を中心に、糖尿病性神経障害性疼痛に対する電気鍼治療の効果と、その背景にあると考えられる分子機序について、できるだけわかりやすくご紹介したいと思います。
鍼灸師として知識を入れることで補完医療の一つとして何かできればいいですよね!
糖尿病性神経障害性疼痛とは

糖尿病性神経障害性疼痛は、糖尿病の合併症として生じる慢性的な痛みです。患者さんによって症状は様々ですが、足のしびれ、灼熱感、ピリピリとした痛み、針で刺されるような痛みなどが典型的な症状として報告されています。
これらの症状は、日常生活の質を大きく低下させる可能性があります。
この痛みの発生には、末梢神経系と中枢神経系の両方が関与していると考えられているそうです。
簡単に言えば、高血糖状態が続くことで神経がダメージを受け、痛みの信号を伝える仕組みが過敏になってしまうというイメージです。
研究の概要

Ma et al.の研究では、ストレプトゾトシン(STZ)というお薬を使って糖尿病モデルラットを作成し、電気鍼治療の効果を検証しています。この研究の興味深い点は、単に「痛みが減った」という結果だけでなく、「なぜ痛みが減ったのか」という分子レベルのメカニズムを追究している点です。
研究チームは、後根神経節(Dorsal Root Ganglion: DRG)と脊髄後角(Spinal Cord Dorsal Horn: SCDH)という、痛みの信号伝達において重要な役割を果たす部位に注目しました。
これらの部位で発現が変化するタンパク質を調べることで、電気鍼がどのように作用しているのかを明らかにしようとしたわけです。
実験デザイン
実験は大きく二つのフェーズに分かれていました:
第一フェーズ: ストレプトゾトシン投与後の変化を時系列で観察し、糖尿病性神経障害性疼痛モデルが適切に作成されていることを確認しました。具体的には、体重の減少、血糖値の上昇、そして痛みに対する感受性の変化(熱刺激に対する足の引っ込め時間の短縮)などが観察されています。
第二フェーズ: 糖尿病モデルラットに対して、2Hzの周波数で電気鍼治療を実施し(ST36とSP6という経穴に1日30分、7日間連続)、その鎮痛効果と分子機序を検討しました。
主要な発見
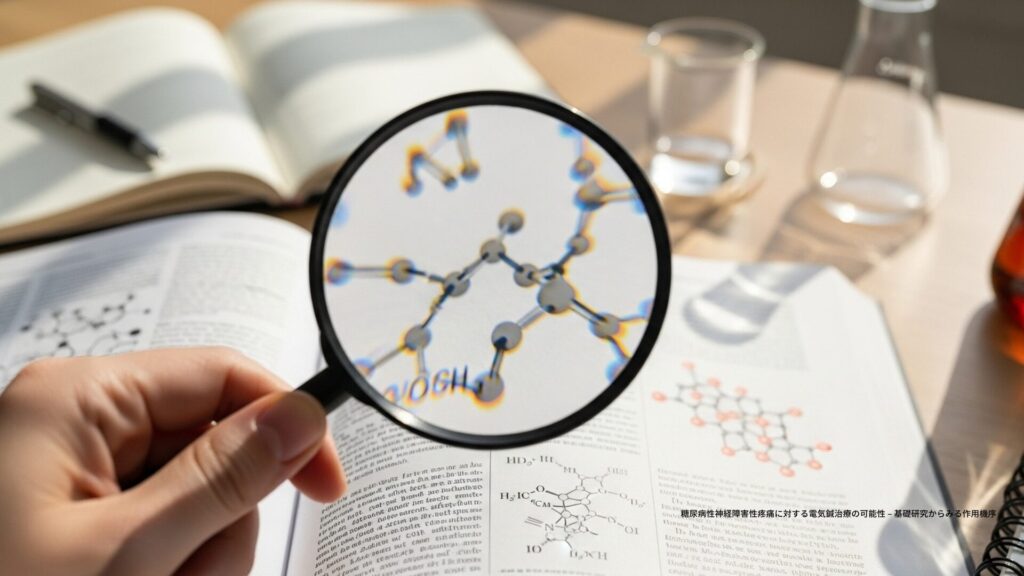
1. 電気鍼の鎮痛効果
研究では、電気鍼治療を受けたグループで、熱刺激に対する痛みの閾値が有意に改善したことが示されています。これは、電気鍼が実際に糖尿病性神経障害性疼痛を和らげる可能性があることを示唆していると言えるでしょう。
2. 分子レベルでの変化
より興味深いのは、電気鍼治療が特定のタンパク質の発現を調節することが明らかになった点です。研究では以下のタンパク質に注目しています:
p-PKC(リン酸化プロテインキナーゼC)
PKCは細胞内のシグナル伝達に関わる重要な酵素です。糖尿病状態では、このPKCが活性化(リン酸化)され、それが痛みの感受性を高めることに関与していると考えられています。研究では、ストレプトゾトシン投与後にp-PKCの発現が増加し、電気鍼治療によってその発現が抑制されることが示されました。
TRPV1(トランジェント・レセプター・ポテンシャル・バニロイド1)
TRPV1は、熱や痛みを感知する受容体として知られています。唐辛子の辛味成分であるカプサイシンが結合する受容体と言えば、少しイメージしやすいかもしれません。糖尿病状態ではこの受容体の発現が増加し、正常では痛みと感じないような刺激でも痛みとして認識されるようになると考えられています。電気鍼治療は、このTRPV1の過剰な発現を抑制する可能性が示されました。
サブスタンスP(SP)とCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)
これらは神経伝達物質として知られており、痛みの信号を伝える役割を果たしています。いわば「痛みのメッセンジャー」のようなものです。研究では、糖尿病状態でこれらの物質の発現が増加し、電気鍼治療によって減少することが確認されています。
電気鍼はどのように作用するのか?

これらの結果を総合すると、電気鍼治療は複数の経路を通じて鎮痛効果を発揮している可能性が考えられます:
シグナル伝達経路の調節
p-PKCとTRPV1の発現を抑制することで、痛みの信号が過剰に増幅されるのを防いでいると考えられます。これは例えるなら、過敏になったアラームシステムの感度を適切なレベルに戻すようなイメージかもしれません。
神経伝達物質の調節
サブスタンスPやCGRPといった痛みを伝える物質の発現を抑えることで、痛みの信号そのものが伝わりにくくなっている可能性があります。
神経保護作用
興味深いことに、他の研究では、電気鍼が神経炎症を抑制したり、神経の変性を防いだりする効果も報告されているようです。これは単に症状を和らげるだけでなく、根本的な神経のダメージを軽減している可能性を示唆しているかもしれません。
臨床への応用の可能性
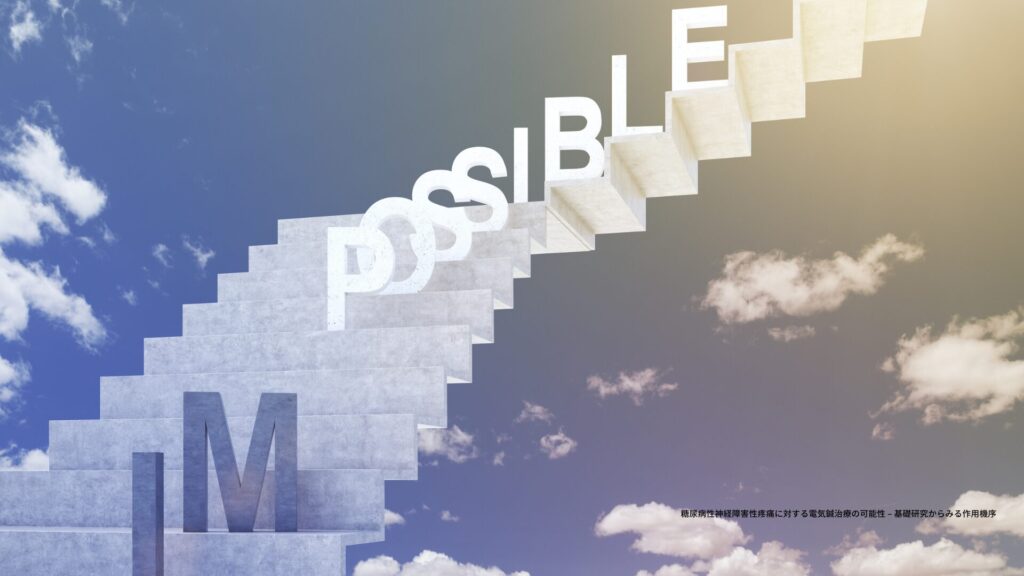
この研究は動物実験であり、結果をそのまま人間に当てはめることはできません。しかし、電気鍼治療の作用機序が明らかになってきたことは、臨床応用への重要な一歩と言えるでしょう。
治療パラメータについて
この研究では2Hzという比較的低い周波数の電気刺激が使用されています。他の研究では、周波数によって効果が異なる可能性も指摘されているようです。例えば、He et al.(2017)の研究では、2Hzと100Hzの両方で鎮痛効果が見られたものの、作用機序に違いがある可能性が示唆されています。
経穴の選択
この研究では足三里(ST36)と三陰交(SP6)という経穴が使用されています。これらは伝統的に糖尿病や神経障害の治療によく用いられる経穴として知られているようです。しかし、どの経穴の組み合わせが最も効果的なのかについては、さらなる研究が必要と思われます。
他の研究との関連

P2X3受容体の役割
Zhou et al.(2018)の研究では、電気鍼が後根神経節におけるP2X3受容体の発現を抑制することで鎮痛効果を発揮する可能性が報告されています。P2X3受容体もTRPV1と同様に痛みの感受性に関与する受容体として知られており、PKCによって調節されていると考えられています。このことは、電気鍼が複数の受容体を介して多角的に作用している可能性を示しているのかもしれません。
P2X4受容体と神経炎症
Qu et al.(2023)の研究では、電気鍼が脊髄のミクログリア(中枢神経系の免疫細胞のようなもの)におけるP2X4受容体の発現を抑制し、それによって神経炎症を抑えることが示されています。これは、電気鍼が痛みの感受性だけでなく、炎症反応も調節している可能性を示唆しているようです。
CaMKII経路との関連
Liu et al.(2024)の研究では、電気鍼がTRPV1を介してCaMKII/CREB経路を調節することで鎮痛効果を発揮する可能性が報告されています。これは、Ma et al.の研究で示されたTRPV1の調節が、さらに下流のシグナル伝達経路にも影響を与えていることを示唆しているのかもしれません。
臨床研究の現状

動物実験での有望な結果を受けて、ヒトを対象とした臨床試験も進められているようです。
例えば、Jiménez-Hernández et al.(2024)は、メキシコで多施設共同ランダム化比較試験を実施中であると報告しています。このような臨床研究の結果が蓄積されることで、電気鍼治療の真の効果と安全性が明らかになっていくことが期待されます。
日本でもどんどん進んでますよね!ありがたい‼
注意すべき点

1. 動物実験の限界
この研究はラットを用いた実験であり、結果がそのまま人間に当てはまるとは限りません。人間の糖尿病性神経障害性疼痛はより複雑で、様々な要因が関与している可能性があります。
2. 作用機序の複雑性
電気鍼の作用機序は、本研究で明らかにされた経路だけではない可能性があります。実際、神経伝達物質や受容体、炎症性サイトカインなど、多くの分子が関与していることが他の研究からも示唆されています。
3. 個人差の問題
人間の場合、糖尿病のタイプ(1型か2型か)、罹病期間、血糖コントロールの状態、併存疾患の有無など、様々な要因が治療効果に影響を与える可能性があります。
今後の展望
メカニズムのさらなる解明
電気鍼がどのようにしてこれらのタンパク質の発現を調節しているのか、その上流のメカニズムについてはまだ十分に解明されていません。経穴への刺激がどのような神経回路を活性化し、最終的に後根神経節や脊髄後角での分子変化につながるのか、そのプロセスの全体像を明らかにすることが今後の課題と言えるでしょう。
最適な治療プロトコルの確立
周波数、刺激強度、治療時間、治療頻度、経穴の選択など、最適な治療パラメータについては、さらなる研究が必要と思われます。また、薬物療法との併用効果についても検討する価値があるかもしれません。
予防効果の可能性
興味深いことに、一部の研究では、電気鍼治療を早期に開始することで、神経障害の進行を遅らせる可能性も示唆されているようです。もしこれが確認されれば、治療だけでなく予防という観点からも重要な意義を持つことになるでしょう。
まとめ
Ma et al.(2023)の研究は、電気鍼治療が糖尿病性神経障害性疼痛に対して鎮痛効果を発揮する可能性と、その背景にある分子機序の一端を明らかにしました。具体的には、p-PKC、TRPV1、サブスタンスP、CGRPといった痛みに関連するタンパク質の発現を調節することで、効果を発揮している可能性が示唆されています。
これらの知見は、電気鍼治療の科学的基盤を強化し、より効果的な治療プロトコルの開発につながる可能性があります。しかし同時に、動物実験の結果をそのまま人間に適用することの限界も認識しておく必要があるでしょう。
糖尿病性神経障害性疼痛に悩む患者さんにとって、薬物療法に加えて電気鍼治療という選択肢が増えることは、大きな意義があると考えられます。今後、さらなる基礎研究と臨床研究の蓄積によって、電気鍼治療の真の価値が明らかになっていくことが期待されます。
慢性的な痛みは、患者さんの日常生活に深刻な影響を与えます。電気鍼治療が、そうした患者さんの生活の質を向上させる一助となる可能性について、私たち医療者は開かれた心で検討していく必要があるのかもしれません。
参考文献
- Ma, Y. Q., Hu, Q. Q., Kang, Y. R., Ma, L. Q., Qu, S. Y., Wang, H. Z., … & He, X. F. (2023). Electroacupuncture alleviates diabetic neuropathic pain and downregulates p-PKC and TRPV1 in dorsal root ganglions and spinal cord dorsal horn. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2023, 3333563. https://doi.org/10.1155/2023/3333563
- He, X. F., Wei, J. J., Shou, S. Y., Xu, S. W., Wang, C. Y., Xie, Y. M., … & Fang, J. Q. (2017). Effects of electroacupuncture at 2 and 100 Hz on rat type 2 diabetic neuropathic pain and hyperalgesia-related protein expression in the dorsal root ganglion. Journal of Zhejiang University-Science B, 18(3), 239-248.
- Zhou, Y. F., Ying, X. M., He, X. F., Shou, S. Y., Wei, J. J., Xie, Y. M., … & Fang, J. Q. (2018). Suppressing PKC-dependent membrane P2X3 receptor upregulation in dorsal root ganglia mediated electroacupuncture analgesia in rat painful diabetic neuropathy. Purinergic Signalling, 14(4), 359-369.
- Qu, S. Y., Wang, H. Z., Hu, Q. Q., Ma, Y. Q., Kang, Y. R., Ma, L. Q., … & He, X. F. (2023). Electroacupuncture may alleviate diabetic neuropathic pain by inhibiting the microglia P2X4R and neuroinflammation. Purinergic Signalling, Published online October 23, 2023.
- Liu, Y., Zhang, Y., Zhu, K., Chi, S., Wang, C., & Xie, A. (2024). Electroacupuncture alleviates streptozotocin-induced diabetic neuropathic pain via the TRPV1-mediated CaMKII/CREB pathway in rats. Journal of Molecular Neuroscience, Published online August 20, 2024.
- Jiménez-Hernández, M. D., Villalobos-Enríquez, M. T., Aguilar-Zavala, H., Hernández-Gutiérrez, S., López-Vázquez, M. A., & Durán-Avelar, M. J. (2024). Electroacupuncture efficacy in diabetic polyneuropathy: Study protocol for a double-blinded randomized controlled multicenter clinical trial. BMC Complementary Medicine and Therapies, 24(1), 84.
- Cho, E., & Kim, W. (2021). Effect of acupuncture on diabetic neuropathy: A narrative review. Journal of Acupuncture Research, 38(3), 187-199.
- Wang, X., Li, Q., Han, X., Gong, M., Yu, Z., & Xu, B. (2021). Electroacupuncture alleviates diabetic peripheral neuropathy by regulating glycolipid-related GLO/AGEs/RAGE axis. Frontiers in Endocrinology, 12, 655591.
- White, A., & Editorial Board of Acupuncture in Medicine. (2009). Western medical acupuncture: a definition. Acupuncture in Medicine, 27(1), 33-35.
- Chen, H., Yang, M., Ning, Z., Lam, W. L., Zhao, Y. K., Yeung, W. F., … & Lao, L. (2019). A guideline for randomized controlled trials of acupuncture. The American Journal of Chinese Medicine, 47(01), 1-18.
文字数: 約5,200字

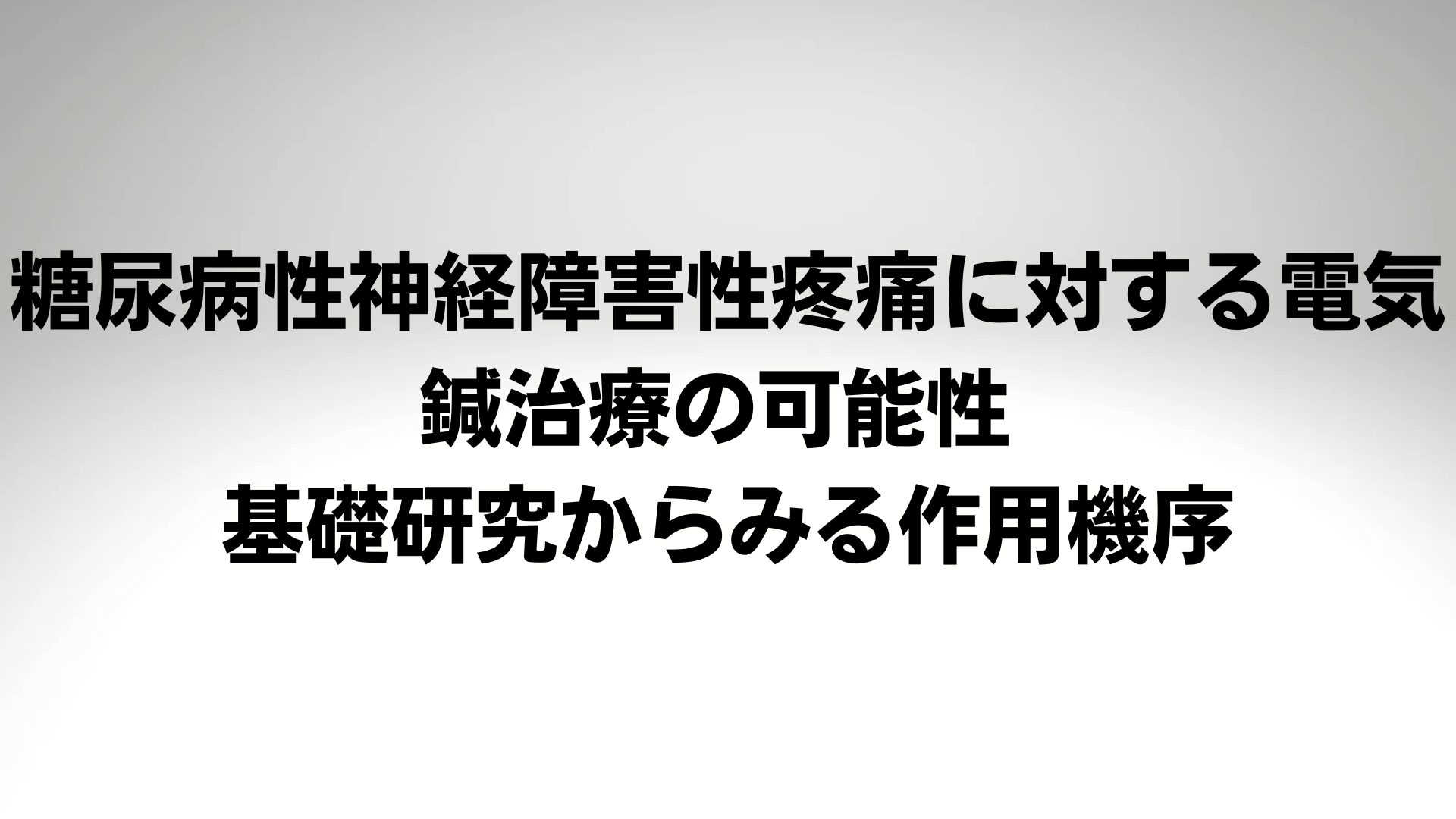
コメント