※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
参考文献はこちら
すべてを鵜呑みにしないでくださいね!
宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼
お金持っている人は新品買ってね!
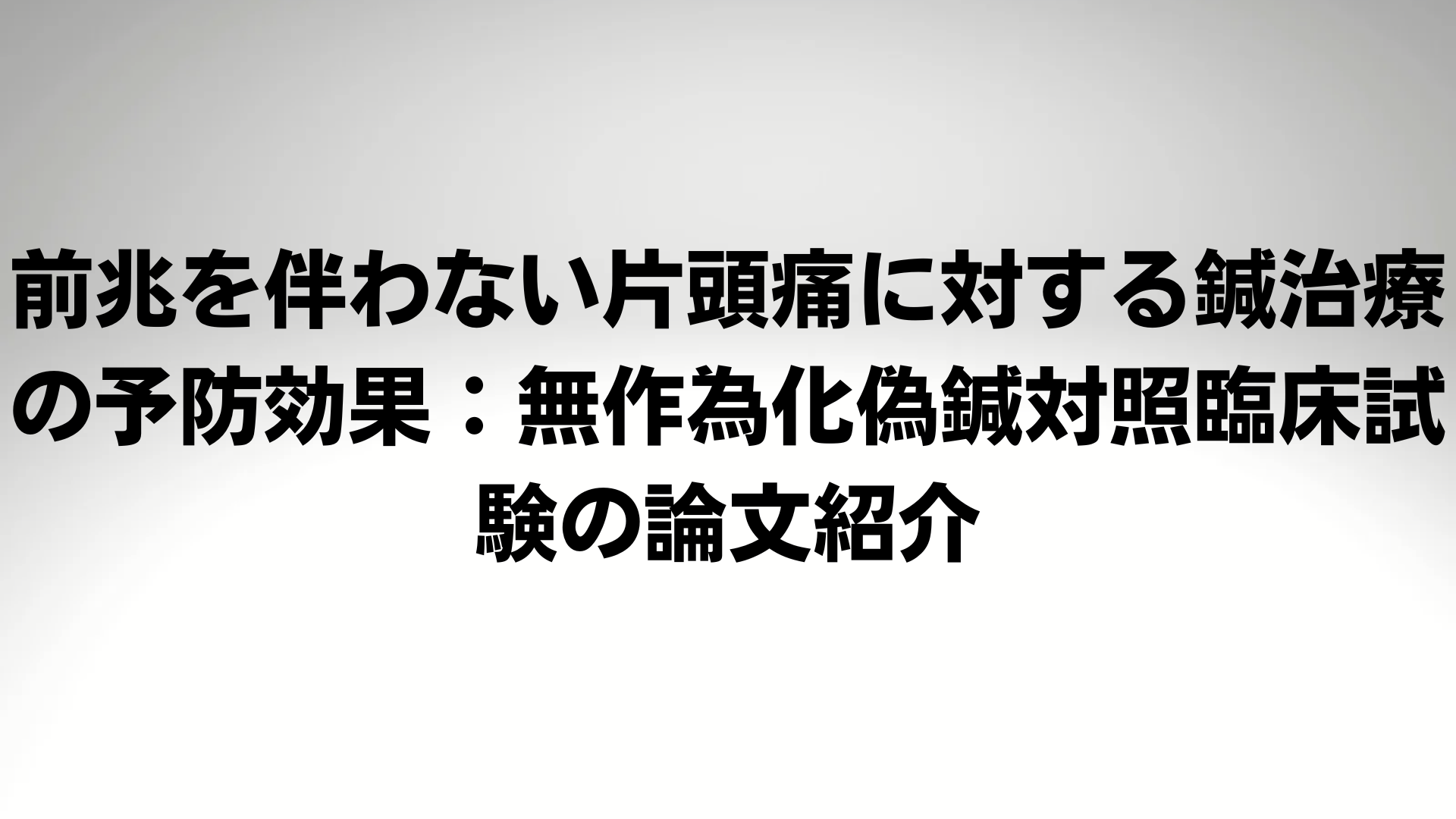
頭痛に対しての鍼灸の論文に対して書いている別記事もどうぞ(^^♪
それでは内容に入っていきましょう‼
はじめに

片頭痛は世界中で多くの方々を悩ませている神経疾患です。最新の世界の疾病負担の研究によりますと、2017年には12億5000万人もの方々が片頭痛を経験されていたとされています。
この疾患は、特に15歳から49歳までの年齢層において、生活の質を低下させる主要な要因となっておると考えられています。
従来の薬物療法には一定の効果が認められるものの、すべての患者さんに対して有効というわけではなく、また副作用の問題も指摘されています。
そのような背景から、非薬物療法としての鍼治療への関心が高まってきました。
今回は、2020年にBMJ誌に掲載された大規模臨床試験を中心に、複数の研究成果をもとに、片頭痛に対する鍼治療の効果とそのメカニズムについて、わかりやすく解説させていただきたいと思います。
主要臨床試験の概要:BMJ研究から見えてきたこと

研究デザインと対象患者
Xuら(2020)によって実施された研究は、中国の7つの医療機関で行われた多施設共同ランダム化比較試験です。この研究では、前兆のない反復性片頭痛を経験されている150名の患者さんが対象となりました。重要な点として、すべての参加者が鍼治療を受けたことがない方々であったということが挙げられます。平均年齢は36.5歳で、参加者の82%が女性でした。
参加者は三つのグループに分けられました。一つ目は真の鍼治療に通常ケアを加えたグループ、二つ目は非侵襲的な偽鍼治療に通常ケアを加えたグループ、そして三つ目は通常ケアのみを受けるグループです。この研究デザインにより、鍼治療の特異的な効果を評価することが可能となりました。
治療プロトコル
真の鍼治療グループでは、伝統的な中医学の診断に基づいて特定のツボが選択されました。具体的には、風池(GB20)、合谷(LI4)、太衝(LV3)、足三里(ST36)といったツボが用いられています。これらのツボは、片頭痛治療において長年使用されてきた実績のあるポイントです。
治療には直径0.25ミリメートル、長さ40ミリメートルの使い捨てステンレス鋼製の鍼が使用され、10から20ミリメートルの深さまで垂直に刺入されました。重要なのは「得気」と呼ばれる特有の感覚を引き出すことで、これは鍼治療が適切に行われている指標とされています。各セッションは30分間で、週5回、8週間にわたり合計20セッションが実施されました。
一方、偽鍼治療グループでは、真のツボではない異なる体節の部位に、皮膚を貫通しない特殊な鍼が使用されました。興味深いことに、患者さんの79%が真の鍼治療で鍼の侵入を感じたと回答し、偽鍼治療でも75%がそう感じたと答えており、両グループ間に統計的な差は見られませんでした。これは、患者さんへの盲検化が成功していたことを示しています。
主要な研究結果
研究の主要評価項目は、ランダム化後1週目から20週目までの4週間あたりの片頭痛日数と発作回数の変化でした。結果は、真の鍼治療の優位性を明確に示すものとなりました。
13週目から16週目の期間において、真の鍼治療グループでは4週間あたりの片頭痛日数が平均3.5日減少したのに対し、偽鍼治療グループでは2.4日の減少にとどまりました。統計的に調整した差は-1.4日(95%信頼区間:-2.4から-0.3、P=0.005)となり、有意な差が認められました。
さらに17週目から20週目になりますと、真の鍼治療グループでは平均3.9日の減少を示したのに対し、偽鍼治療グループでは2.2日の減少でした。調整後の差は-2.1日(95%信頼区間:-2.9から-1.2、P<0.001)と、より大きな差が認められました。
発作回数についても同様の傾向が見られ、17週目から20週目において、真の鍼治療グループでは平均2.3回の減少、偽鍼治療グループでは1.6回の減少となり、調整後の差は-1.0回(95%信頼区間:-1.5から-0.5、P<0.001)と有意な差が示されました。
安全性の面では、重篤な有害事象は報告されておらず、鍼治療の安全性が確認されました。
他の臨床研究からの知見

Cochrane系統的レビューの見解
Lindeら(2016)によるCochraneレビューは、鍼治療と片頭痛に関する研究において非常に重要な位置を占めています。このレビューでは、22の臨床試験、合計4985名の参加者が含まれました。
分析の結果、通常ケアのみを受けたグループでは100人中17人が頭痛頻度を半減させることができたのに対し、鍼治療を追加したグループでは100人中41人が同様の改善を達成したとされています。これは、鍼治療の追加により、より多くの患者さんが臨床的に意味のある改善を経験できる可能性を示唆しています。
また、このレビューでは、鍼治療が予防的薬物療法と少なくとも同等、あるいはそれ以上の効果を持つ可能性があり、かつ副作用が少ないことが指摘されています。
ACUMIGRAN研究:薬物療法との直接比較
Gianniniら(2021)によるACUMIGRAN研究は、鍼治療と最適な薬物療法を直接比較した初めての研究として注目されます。この研究では、反復性片頭痛の患者さんが、12セッションの鍼治療を受けるグループと、各患者さんに最も適した薬物治療を受けるグループに分けられました。
結果として、鍼治療グループは薬物療法グループと同等、あるいはわずかに優れた効果を示し、さらに治療へのコンプライアンス(治療の継続性)と副作用の発生率において鍼治療グループが優位であったことが報告されています。この知見は、臨床実践において鍼治療が実用的な選択肢となりうることを示唆しています。
用量反応関係に関する研究
2024年に発表された系統的レビューとメタ回帰分析では、鍼治療のセッション数、頻度、期間と効果との関係が詳しく調べられました。この研究には32の臨床試験、1562名の参加者が含まれています。
興味深いことに、鍼治療のセッション数と効果の間にはJ字型の用量反応関係が見られたとされています。具体的には、16回のセッション後に片頭痛発作の頻度が有意に減少し、週3回の頻度で治療を行うと効果が高まり、2か月間の治療後に最も大きな改善が見られたものの、それ以降は改善の度合いが緩やかになったとのことです。
この知見は、臨床実践において治療計画を立てる際の重要な指針となる可能性があります。過度に長期間の治療を続けるよりも、適切な期間と頻度で治療を行うことが効率的であることを示唆しています。
鍼治療の神経メカニズム:最新の科学的理解

神経炎症の抑制
動物実験による研究から、鍼治療が片頭痛に関連する神経炎症を抑制することが示されています。具体的には、鍼治療によって神経ペプチド、免疫細胞、炎症性神経伝達物質の減少が観察されています。
特に重要なのは、カルシトニン遺伝関連ペプチド(CGRP)、サブスタンスP(SP)、セロトニン(5-HT)といった神経伝達物質の調節です。これらの物質は片頭痛の病態生理において中心的な役割を果たしており、鍼治療がこれらの物質の放出を抑制することで、痛みの伝達を減少させると考えられています。
また、鍼治療は炎症性サイトカインのレベルを低下させることで、神経性炎症を軽減し、中枢性感作を改善することが報告されています。これらの作用は、片頭痛の予防において重要な役割を果たしていると考えられます。
疼痛調節システムの活性化
鍼治療の鎮痛効果には、下行性疼痛調節システムの活性化が関与していると考えられています。このシステムは、脳から脊髄へと下降する神経経路を通じて、痛みの信号を抑制する働きを持っています。
最近の研究では、鍼治療が広汎性侵害抑制調節(DNIC)と呼ばれるメカニズムを介して作用する可能性が指摘されています。これは、一つの部位に加えられた刺激が、別の部位の痛みを軽減するという現象です。鍼治療は、このDNICを活性化することで、三叉神経頸髄複合体(TCC)における広作動域ニューロンの活動を抑制し、片頭痛の痛みを軽減すると考えられています。
神経画像研究が明らかにした脳の変化
機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いた研究により、鍼治療が脳の機能的活動と結合性に変化をもたらすことが明らかになってきました。
複数の研究において、鍼治療後に上側頭回、紡錘状回、下側頭回、中後頭回などの領域で脳活動の変化が観察されています。これらの領域は、痛みの処理や視覚情報の処理に関与しており、片頭痛患者さんではこれらの領域の活動が異常を示すことが知られています。
また、鍼治療は扁桃体や帯状皮質と側頭葉との間の機能的結合を増強することが報告されています。これらの領域は、感情や痛みの処理に重要な役割を果たしており、鍼治療がこれらのネットワークを正常化することで、片頭痛の症状を改善している可能性があります。
さらに興味深いことに、鍼治療はデフォルトモードネットワーク、前頭頭頂ネットワーク、視覚-側頭ネットワーク、小脳などの異常な機能的活動や結合性を変化させることが示されています。これらのネットワークは、片頭痛の病態において重要な役割を果たしており、鍼治療がこれらのネットワークを調節することで、片頭痛の予防に寄与していると考えられます。
末梢性および中枢性感作の調節
片頭痛の慢性化には、末梢性および中枢性感作と呼ばれる現象が関与しています。これは、痛みの信号を伝える神経系が過敏になり、通常では痛みを引き起こさない刺激に対しても痛みを感じるようになる状態です。
鍼治療は、脳由来神経栄養因子(BDNF)やグルタミン酸といった神経感作関連メディエーターの放出を調節することで、この感作プロセスに介入すると考えられています。
また、エンドカンナビノイドシステムやセロトニンシステムの活性化を通じて、末梢性および中枢性感作の発達を抑制する可能性が示されています。
さらに、鍼治療はミクログリア細胞の活性化を抑制することが報告されています。
ミクログリア細胞は中枢神経系の免疫細胞であり、活性化すると炎症性物質を放出して痛みを増強させます。鍼治療がこれらの細胞の活性化を抑えることで、中枢性感作を軽減し、片頭痛の症状を改善すると考えられています。
臨床実践への示唆
治療対象となる患者さん
現在までの研究成果から、前兆のない反復性片頭痛の患者さんにおいて、鍼治療の効果が比較的よく確立されているといえます。特に、月に4日以上の頭痛日数がある方や、薬物療法に不応または禁忌がある方にとって、鍼治療は有用な選択肢となる可能性があります。
また、薬物療法の副作用に悩まされている方や、非薬物的なアプローチを希望される方にとっても、鍼治療は検討に値する治療法と考えられます。
推奨される治療プロトコル
研究成果に基づきますと、週3回程度、8週間から12週間の治療期間が一つの目安となるかもしれません。
合計16回から20回程度のセッションを行うことで、臨床的に意味のある効果が期待できる可能性があります。
ツボの選択については、風池(GB20)、合谷(LI4)、太衝(LV3)、足三里(ST36)などが基本となりますが、個々の患者さんの症状や体質に応じて、適切なツボを選択することが重要です。
治療セッションの長さは30分程度が標準的と考えられますが、これも患者さんの状態に応じて調整が必要な場合があります。
効果の評価時期
研究結果から、鍼治療の効果は治療開始後13週目以降により明確になる傾向が見られます。したがって、効果判定を行う際には、少なくとも3か月程度の治療期間を経過してから評価することが適切かもしれません。
ただし、個人差も大きいため、治療開始後も定期的に症状を評価し、効果や副作用をモニタリングしながら治療を続けることが推奨されます。
他の治療法との併用
鍼治療は、通常ケアに追加する形で実施することで、より良い効果が得られる可能性が示されています。
急性期の頭痛に対する鎮痛薬の使用を完全に置き換えるものではなく、予防的な介入として位置づけられるべきと考えられます。
薬物による予防療法を受けている患者さんにおいても、鍼治療を併用することで、薬剤の使用量を減らせる可能性があります。ただし、治療計画の変更については、必ず医師と相談しながら進めることが重要です。
まとめ
片頭痛に対する鍼治療の効果について、近年多くの質の高い研究成果が蓄積されてきました。BMJ誌に掲載されたXuらの研究をはじめとする複数の臨床試験から、鍼治療が片頭痛の頻度と重症度を減少させる効果を持つことが示されています。
その効果は、偽鍼治療や通常ケアのみと比較して統計的に有意であり、臨床的にも意味のある改善をもたらす可能性があります。また、薬物療法と同等あるいはそれ以上の効果を示しながら、副作用が少ないという利点も指摘されています。
神経科学的な研究からは、鍼治療が神経炎症の抑制、疼痛調節システムの活性化、脳の機能的変化など、複数のメカニズムを通じて作用していることが明らかになってきました。これらの知見は、鍼治療の効果が単なるプラセボ効果ではなく、実際の生理学的変化に基づいていることを示唆しています。
臨床実践においては、週3回程度、8週間から12週間の治療期間を一つの目安として、患者さんの状態に応じた個別化された治療計画を立てることが推奨されます。鍼治療は、薬物療法に代わる選択肢としてだけでなく、補完的な治療法としても位置づけられる可能性があります。
ただし、研究の限界も認識しておく必要があり、今後さらなる研究の蓄積により、より確実なエビデンスが構築されることが期待されます。
片頭痛は多くの患者さんの生活の質を著しく低下させる疾患ですが、鍼治療は安全で効果的な治療選択肢の一つとして、臨床実践において重要な役割を果たす可能性を持っているといえるでしょう。
参考文献
- Xu S, Yu L, Luo X, et al. Manual acupuncture versus sham acupuncture and usual care for prophylaxis of episodic migraine without aura: multicentre, randomised clinical trial. BMJ. 2020;368:m697.
- Linde K, Allais G, Brinkhaus B, et al. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane Database Syst Rev. 2016;6:CD001218.
- Giannini G, Favoni V, Merli E, et al. A Randomized Clinical Trial on Acupuncture Versus Best Medical Therapy in Episodic Migraine Prophylaxis: The ACUMIGRAN Study. Front Neurol. 2021;11:570335.
- Zhang N, Houle T, Hindiyeh N, Aurora SK. Systematic review: acupuncture vs standard pharmacological therapy for migraine prevention. Headache. 2020;60:309-317.
- Chen Y, Liu Y, Song Y, et al. Therapeutic applications and potential mechanisms of acupuncture in migraine: A literature review and perspectives. Front Neurosci. 2022;16:1022455.
- An Y, Zhang J, Ren Q, et al. The Mechanism of Acupuncture Therapy for Migraine: A Systematic Review. J Pain Res. 2025;18:251-267.
- Liu L, Tian T, Li X, et al. Revealing the Neural Mechanism Underlying the Effects of Acupuncture on Migraine: A Systematic Review. Front Neurosci. 2021;15:674852.
- Song Y, Li T, Ma C, et al. Comparative efficacy of acupuncture-related therapy for migraine: A systematic review and network meta-analysis. Front Neurol. 2022;13:1010410.
- Wang Y, Xue CC, Helme R, et al. Acupuncture for frequent migraine: a randomized, patient/Assessor blinded, controlled trial with one-year follow-up. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:920353.
- Zhao L, Chen J, Li Y, et al. The long-term effect of acupuncture for migraine prophylaxis: a randomized controlled trial from a 24-week to 52-week follow-up. JAMA Intern Med. 2017;177(4):508-515.
- GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392:1789-1858.
- Vickers AJ, Rees RW, Zollman CE, et al. Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial. BMJ. 2004;328:744.
- Diener HC, Kronfeld K, Boewing G, et al. Efficacy of acupuncture for the prophylaxis of migraine: a multicentre randomised controlled clinical trial. Lancet Neurol. 2006;5(4):310-316.
- Zhao L, Liu L, Xu X, et al. Electroacupuncture Inhibits Hyperalgesia by Alleviating Inflammatory Factors in a Rat Model of Migraine. J Pain Res. 2020;13:75-86.
- Ma P, Dong X, Qu Y, et al. A Narrative Review of Neuroimaging Studies in Acupuncture for Migraine. Pain Res Manag. 2021;2021:9460695.

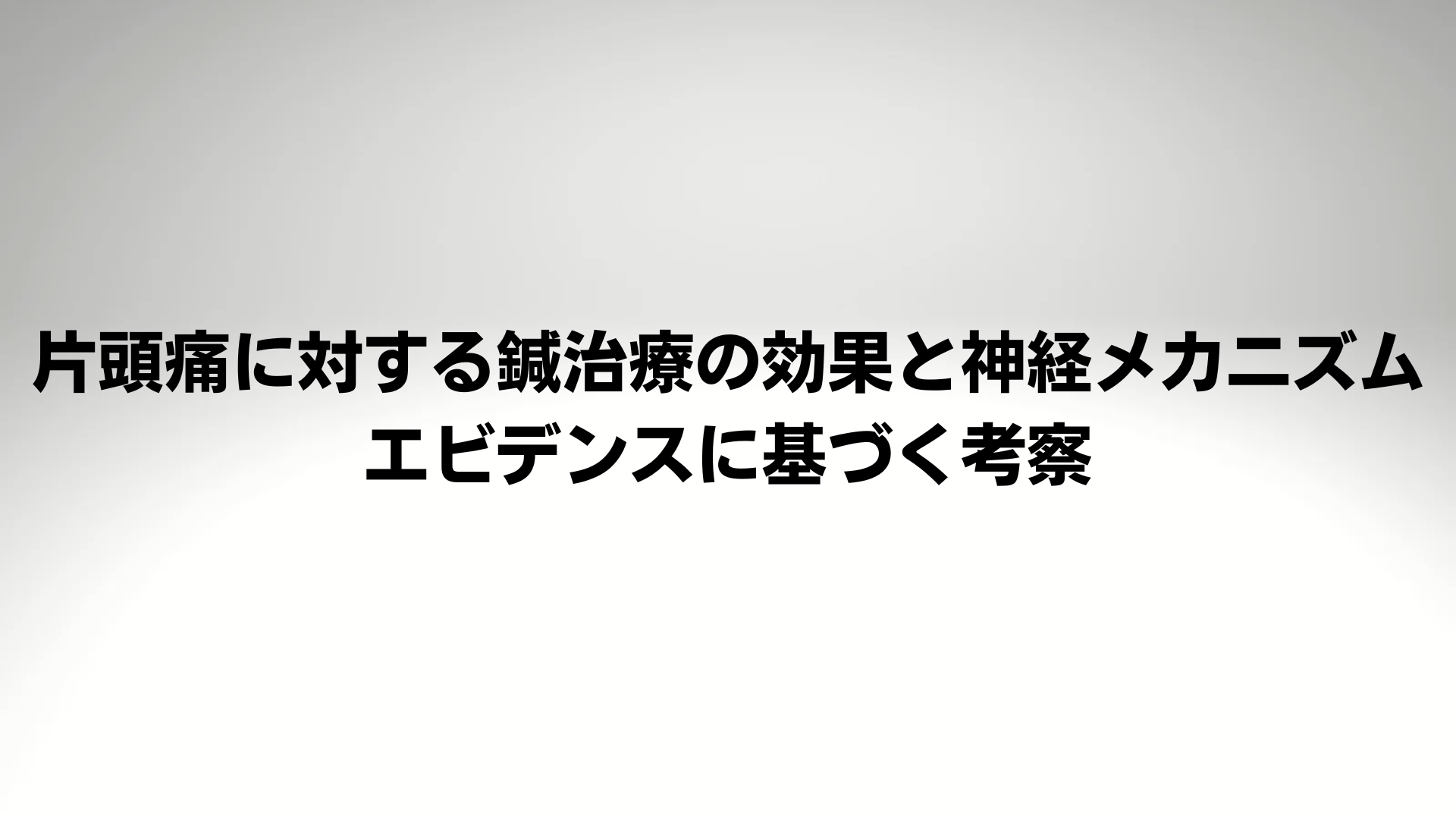
コメント