※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をご紹介していきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
今日は、骨をつくる細胞(=幹細胞)に対してLIPUSという超音波刺激がどんな影響を与えるか、という2025年9月に発表された論文 Low‑Intensity pulsed ultrasound enhances paracrine secretion of IGF and VEGF by BMSCs, promoting osteogenesis and angiogenesis を、なるべくわかりやすく整理してみたいと思います。少し専門的ですが、「骨折・骨再生」や「物理刺激×細胞」あたりに興味がある方には面白い内容です。
あくまで私の個人的なブログなので鵜吞みにしないようにお気を付けください。
実際のリンクはこちら

背景:なぜこの研究が必要だったのか?
が幹細胞を通じて骨をつくる&血管をつくる力を高める?-―-最新研究を解説-1-1024x576.jpg)
私たちの骨がけがをして、骨が折れたり、歯槽骨(あごの骨)などがなくなったりしたとき、骨の“再生・修復”には主に二つのプロセスが大事です。
- 一つは「骨をつくる細胞」がちゃんと働くこと(骨芽細胞が活躍する)。
- もう一つは「血管(=血液を運ぶ管)が新しくできる」こと。骨が修復されるためには、栄養や酸素を運ぶ血管網が不可欠です。
論文でも「骨再生には“造骨(osteogenesis)”と“血管新生(angiogenesis)”の両方が鍵」という説明があります。
この中で「幹細胞(具体的には骨髄由来間葉系幹細胞:BMSCs)」が、骨をつくる細胞になるだけでなく、周りの細胞に有効物質を出して“環境を整える(=パラクリン作用)”役割も持っていることが最近注目されています。
一方で、LIPUS(低出力パルス超音波)という「骨・治療分野で使われてきた物理刺激」が幹細胞の働きをどう変えるか、特に「パラクリン作用(幹細胞が分泌する成長因子など)を変えるかどうか」という点はまだ十分に分かっていませんでした。そこでこの研究が「LIPUS → BMSC の分泌物質が変わるか? → 変わったら造骨&血管新生が促進するか?」という疑問を検証しているわけです。
目的:この研究で何を調べたか?
要するに研究の目的は以下の通りです:
- BMSC(骨髄由来間葉系幹細胞)にLIPUSを与えたら、幹細胞がどんな成長因子を出すか(IGF-1、VEGF、TGF-βなど)を測定する。
- その “幹細胞から出た液(条件培養液:conditioned media)” を使って、他の細胞(血管細胞=RAOECs=ラット大動脈内皮細胞、あるいは別のBMSC)を培養してみて、「造骨」「血管新生」が変わるかどうかを観察する。
- つまり、「LIPUS → 幹細胞の分泌変化 → 造骨&血管新生促進」というメカニズム仮説を検証することです。
方法:どうやって実験したか?
少し詳しく流れを整理しますが、専門用語は軽く流してもらって大丈夫です。
- 幹細胞の準備
ラット(2週間齢のスプラグドーリーラット)から骨髄をとり、BMSC(骨髄由来間葉系幹細胞)を分離・培養。3〜5 代目の細胞を使っています。
細胞が「幹細胞っぽい!?(申し訳ございません。)」かどうか、CD29・CD90(陽性)、CD45(陰性)などのマーカーを用いて確認しています。 - LIPUS刺激+条件培養液の作成
BMSCを2群に分け、片方には LIPUS(30 mW/cm²、1.5 MHz、1 kHz、デューティ20%)を毎日20分、プレート底から超音波プローブを当てて刺激。もう片方は偽刺激(装置だけでも超音波なし)です。
それぞれの群から毎回刺激24時間後に培養上清(=条件培養液、CM)を集めます。→「LIPUS-CM」対「Ctrl-CM(コントロール)」。 - 成長因子の測定
LIPUS-CM と Ctrl-CM をELISA法で測定し、IGF-1、VEGF、TGF-β の濃度を比較。 - 機能検証(他の細胞に対して)
- 血管細胞(RAOEC=ラット大動脈内皮細胞)に、LIPUS-CM/Ctrl-CM を使って培養し、細胞増殖/移動(スクラッチアッセイ)/血管構造(チューブ形成アッセイ)/血管関連遺伝子の発現(Ang, Hif-1α)を調べる。
- BMSC自身にも、LIPUS-CM/Ctrl-CM を使って培養し、細胞移動/造骨誘導(アルカリホスファターゼ染色、Alizarin Red S染色)/造骨関連遺伝子(Bmp-2, Bsp, Ocn, Opn)の発現を比較。
つまり、「刺激した幹細胞から出た液が、他の細胞をどう変えるか」を丁寧に見ているわけです。
結果:どんなことが分かったか?
が幹細胞を通じて骨をつくる&血管をつくる力を高める?-―-最新研究を解説-1-1-1024x576.jpg)
主なポイントをまとめると、次の通りです。
- 成長因子の分泌変化:
LIPUS-CM群のBMSCから、IGF-1 と VEGF の分泌が 有意に増加していました。例えば、IGF-1 は Ctrl-CM 169.6 pg/ml → LIPUS-CM 543.4 pg/ml という大きな差。 VEGF も Ctrl-CM 371.5 pg/ml → LIPUS-CM 541.1 pg/ml。
一方、TGF-β に関しては、ほぼ差が出ませんでした。 - 血管細胞(RAOEC)への影響:
LIPUS-CM を使った群では、細胞増殖が速く、移動能力(スクラッチアッセイの傷のふさがり)が良く、チューブ(血管のような構造)形成も Ctrl 群より優れていました。さらに、Ang/Hif-1α という血管新生関連遺伝子の発現も増えていました。 - 幹細胞自身(BMSC)への影響:
幹細胞に LIPUS-CM を与えると、移動能力が明確に上がっており、造骨誘導実験でも、アルカリホスファターゼ染色・アリザリンレッド染色ともに“骨のような石灰化塊”がより多く見られました。造骨関連遺伝子(Bmp-2, Bsp, Ocn, Opn)も Ctrl 群と比べて有意に上昇。
つまり、「LIPUSが幹細胞を刺激すると、幹細胞がIGF-1/VEGFをたくさん出して、その出されたものが血管細胞や他の幹細胞を活性化し、血管新生・造骨を促す」というメカニズムが、少なくとも in vitro(試験管・培養皿)レベルで確認されたということです。
考察:この研究の意義・どこが新しいか?
が幹細胞を通じて骨をつくる&血管をつくる力を高める?-―-最新研究を解説-2-1024x576.jpg)
この研究の良いところ・注目すべき点を整理します。
- 新しい視点:従来、LIPUSの効き目は「骨芽細胞を直接活性化する」「幹細胞の分化を促す」という観点が中心でした。ところが本研究では「幹細胞が出す“分泌物(秘めたる力)”が変わる」という“パラクリン機構”に注目しています。これは骨修復・再生研究においてかなり興味深いアプローチです。
- “造骨×血管新生”の両立:骨を再生するには血管が付いてこそ効率良く機能しますが、血管新生まで含めて実験的に示した点もポイントです。
- 物理刺激(LIPUS)による幹細胞活性化の可能性:将来的に「幹細胞移植」や「幹細胞を使った再生医療」の前処理として、LIPUSのような刺激を加えることで分泌物(=“分泌カクテル”)を高めておくという戦略が見えてきます。実際、論文でも「組織工学用途としてMSCの分泌物を制御する方法として、物理刺激が有効かもしれない」と書かれています。
また、実験系としてもきちんと幹細胞・内皮細胞・機能アッセイと段階的に検証されており、メカニズムに迫る内容として面白いものがあります。
注意点・限界:だから“すぐ臨床”というわけではない
が幹細胞を通じて骨をつくる&血管をつくる力を高める?-―-最新研究を解説-3-1024x576.jpg)
ただし、いくつか留意すべき点もあります。
- 試験管内実験(in vitro)である:この研究は細胞培養レベルでの検証であって、生体(動物モデル・臨床)で「骨折部でLIPUSをやったらIGF/VEGFが上がって、骨が治るスピードが速くなった」という因果を直接示したものではありません。
- 幹細胞の“分泌物”は多様・複雑:本研究では IGF-1/VEGF に注目していますが、幹細胞が出す物質(サイトカイン、成長因子、エクソソーム・マイクロRNAなど)は非常にたくさんあります。論文でも「これらは成長因子の一部に過ぎない」と記されています。)
- 刺激条件・パラメータが限定的:LIPUSの強度・時間・頻度などはこの実験条件(30 mW/cm²、1.5 MHz、20分/日)ですが、これが最適かどうか、他の条件でどうなるか、骨折部位・年齢・生体状況で変わるかどうかは未検証です。
- 骨・血管が“本当に”どうなるか、生体で検証する必要あり:細胞レベルでは「血管構造ができる」「造骨マーカーが上がる」ことは示されましたが、「その骨がちゃんと臨床的に役立つ(強くなる・早く癒える)」という証拠は、この研究では提供されていません。
つまり、この研究は「方向性として非常に興味深い」けれども、「これだけで臨床現場でLIPUSを変える/新しい治療プロトコルに即応用する」という段階ではありません。
臨床・治療へのインパクト:将来どうつながる?
が幹細胞を通じて骨をつくる&血管をつくる力を高める?-―-最新研究を解説-4-1024x576.jpg)
このような知見が将来どう骨折治療・骨再生治療に活かされるかを想像してみましょう。
- 骨折・骨移植・人工インプラント埋入後などで、骨・血管再生を促す補助手段としてLIPUSを使う可能性が、メカニズム研究として補強されました。
- 幹細胞を用いた再生医療(例:骨移植+幹細胞、幹細胞の分泌物を使った“細胞を使わない療法”)で、「幹細胞を使う前にLIPUS刺激を加えておく」といった“前処理戦略”が検討されうるようになります。
- 骨粗鬆症・高齢者・難治性骨折・骨移植・インプラント接合部など「骨再生が難しい」状況で、血管新生も含めて再生環境を整えるための物理刺激療法(LIPUSなど)が、より注目されるでしょう。
- ただし、どの骨折・どの患者・どのタイミングでLIPUSを使うべきか、そのパラメータ(出力・時間・回数)・併用療法(固定・移植・薬剤)などについては、今後の臨床試験を通じて明らかにされる必要があります。
まとめ:この論文が教えてくれること
が幹細胞を通じて骨をつくる&血管をつくる力を高める?-―-最新研究を解説-5-1024x576.jpg)
少し長くなりましたが、ポイントを整理しますと:
- LIPUSは骨再生を助ける物理療法として既に注目されてきました。
- 本研究は「幹細胞(BMSCs)の分泌物(IGF-1、VEGF)がLIPUSで増える」という新しいメカニズムを示しました。
- 増えた分泌物は、血管細胞の増殖・移動・管形成、幹細胞自身の造骨分化を促進することを、培養実験で確認しています。
- まだ生体/臨床レベルでは十分証明されておらず、あくまで“方向性を示した研究”ですが、骨折治療・再生医療の将来には興味深い足がかりとなります。
- 今後、どのような臨床応用ができるか、どの程度効果があるか、患者・骨の種類・治療タイミングなどの条件を決める大規模研究が待たれます。

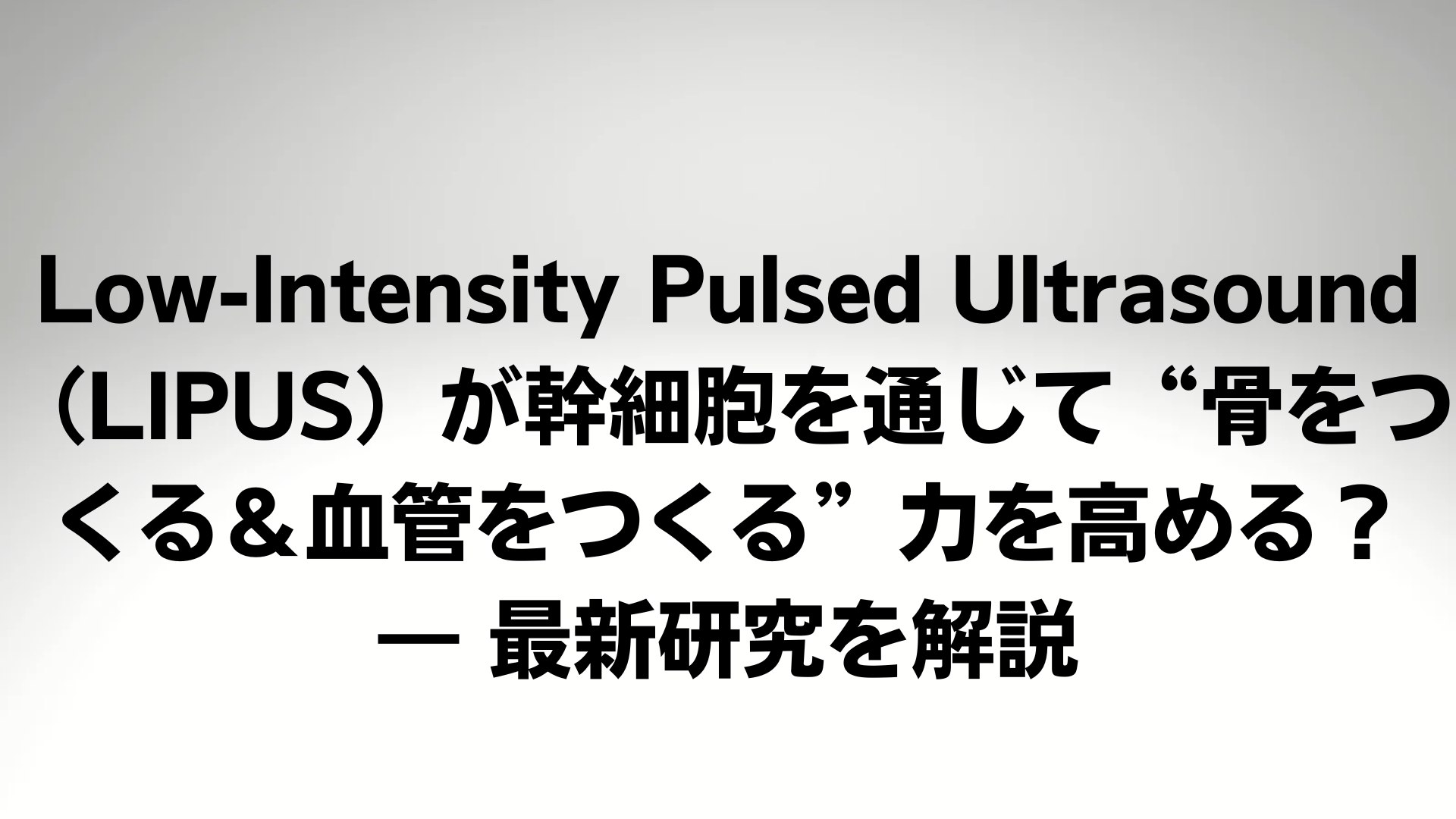
コメント