※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています
こんにちは!
陣内です。
今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。
いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。
ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)
セラピストやリハビリテーションの現場でよく使われる「超音波療法」について、最新の研究をもとにお話ししたいと思います。
特に、腱(けん)という組織がどのように温まりどんな効果が得られるのかを、できるだけわかりやすく解説していきますね。
今回の参考文献はこちら
すべてを鵜吞みにしないでご自分でも読んでみてくださいね!
超音波療法って何だろう?

まず基本から。
超音波療法は、人間の耳には聞こえない高い周波数の音波(20kHz以上)を使って、体の組織を温めたり、組織の修復を促したりする治療法です。
超音波の効果には大きく分けて2つあります。「非熱効果」と「熱効果」です。
非熱効果は、超音波の波が組織を通るときの機械的な作用で、細胞の透過性を高めたり、組織修復に関わる細胞の活動を活発にしたりします。まるで、静かな池に小石を投げ込んだときの波紋が、水面の汚れを少しずつ動かしていくようなイメージですね。
温熱効果は、超音波のエネルギーが組織に吸収されて熱に変わることで生じます。組織の分子が超音波のエネルギーを吸収すると、分子の振動が速くなり、その結果として組織が温まります。これは、手をこすり合わせると摩擦で温かくなるのと似ていますね。
温度が上がると何が起こるの?

組織温度がわずか1〜2℃上昇するだけで、代謝率が1℃あたり約13%増加します。これは体の修復プロセスにとってプラスに働きます。
さらに3〜4℃の上昇になると、痛みの軽減、筋肉の痙攣の緩和、慢性炎症の改善、そして血流の増加が期待できます。そして、今回の研究で特に注目したいのが、4℃以上の温度上昇によって、コラーゲン組織の伸展性が向上するという点です。
腱や靭帯などの結合組織は、主にコラーゲンというタンパク質でできています。このコラーゲンは、温めると少し柔らかくなって伸びやすくなる性質があります。
なぜ犬の腱を研究したの?

人間と動物では、組織の構造や性質に違いがあります。以前の研究から、人間と犬では筋肉の温まり方に違いがあることが示唆されていました。人間の筋肉は犬の筋肉よりも速く温まり、治療期間中その傾向が続き、人間の筋肉温度は犬の研究で報告された値のほぼ2倍に達しました。
また、タンパク質含有量の高い組織(骨、軟骨、腱、靭帯など)は、超音波の波からより多くのエネルギーを吸収するため、脂肪組織よりも急速に、そしてより高温に加熱されます。
つまり、組織の種類によって、また種(人間か犬か馬かなど)によって、超音波の効果が異なる可能性があるということです。だからこそ、獣医療の現場で適切な治療を行うためには、動物での研究が必要なんですね。
私たちは実際に動物を施術するわけではないですがこのデータから臨床につなげていくということですね。
今回の研究方法

研究者たちは、10頭の健康な成犬(4〜6歳、体重17〜30kg)を対象に、アキレス腱(専門的には踵骨腱といいます)に4種類の異なる超音波治療を行い、腱の温度変化を測定しました。
使用した設定は以下の通りです:
- 連続波 1.5 W/cm²
- 連続波 1.0 W/cm²
- パルス波(20%デューティサイクル)1.5 W/cm²
- パルス波(20%デューティサイクル)1.0 W/cm²
周波数はすべて3.3 MHzで、10分間の治療を行いました。
連続波とパルス波の違いを説明しますと、連続波は休みなく超音波を出し続ける方式で、パルス波は「出す・止める・出す・止める」を繰り返す方式です。パルス波は組織の過熱を防ぎながら、非熱効果を利用したい場合に使います。
腱の温度を測定するために、温度センサー付きの細い針を腱の中心部に挿入し、15秒ごとに温度を記録しました。これにより、リアルタイムで腱がどのように温まっていくかを正確に把握できるわけです。
研究結果

温度上昇のパターン
10分間の治療後、平均的な腱温度の上昇は、パルス波1.0 W/cm²で0.65℃、パルス波1.5 W/cm²で1.5℃、連続波1.0 W/cm²で2.5℃、そして連続波1.5 W/cm²で3.5℃でした。
最大温度上昇は、それぞれ0.9℃、1.7℃、3.1℃、4.1℃でした。
ここで注目すべき点が2つあります。
第一に、連続波1.5 W/cm²で治療した腱は、パルス波で治療した腱よりも有意に大きな温度上昇を示しました。これは、熱効果を目的とする場合、連続波が効果的であることを示しています。
第二に、そして非常に興味深いのが、超音波治療を受けた腱は、治療開始後3分未満で最大またはほぼ最大の温度に達しましたという点です。
これは何を意味するのでしょうか?例えば、お風呂を沸かすとき、最初は急速に温度が上がりますが、ある程度の温度に達すると、それ以上はなかなか上がらなくなりますよね。腱の温度上昇も似たようなパターンを示したのです。
連続波1.0 W/cm²の治療では、最初の1分間で腱の平均温度が2.0℃上昇し、1.5 W/cm²では2.1℃上昇しました。その後は、温度上昇が緩やかになり、ほぼ一定の温度を維持しました。
冷却のスピード
超音波治療を止めた後の最初の1分間で、連続波で治療した両グループの腱温度は有意に低下しました。1.0 W/cm²グループでは1℃以上、1.5 W/cm²グループでは1.8℃以上温度が下がりました。
これは非常に重要な発見です。なぜなら、温めた組織をストレッチするタイミングが非常に短い可能性があることを示しているからです。
これは経験則としても同じように感じることが多いです。
柔軟性への効果
連続波1.5 W/cm²で10分間治療した後、足首の曲げ角度(足関節の屈曲角度)は平均で6.6度増加し、これは初期測定値から5%の増加を示しました。
しかし、超音波治療を止めて5分後には、治療した足の平均足関節屈曲角度は、超音波治療前の値や未治療のコントロール側と比較して有意な差は見られませんでした。
つまり、柔軟性の向上効果は一時的なもので、すぐに元に戻ってしまったということです。
筋肉と腱の加熱パターンの違い

この研究で明らかになった興味深い点の一つは、腱と筋肉では超音波による加熱パターンが異なるということです。
以前の犬の筋肉を対象とした研究では、超音波治療中、筋肉温度は比較的安定した速度で上昇し続けました。一方、この研究では、犬のアキレス腱は最初の2分間で急速に温度が上昇し、その後約8分間はほぼ一定の温度を維持しました。
これはなぜでしょうか?考えられる理由はいくつかあります。
まず、腱は筋肉よりもコラーゲンの密度が高く、コラーゲン密度の高い構造は超音波エネルギーをより効率的に吸収するため、脂肪組織よりも急速に、そしてより高温に加熱されます。
また、腱は筋肉に比べて血管が少ない組織です。血流は体の自然な「冷却システム」として機能するので、血管が少ない腱は温まりやすく、また冷めやすい可能性があります。脚の下部では、腱が他の組織にあまり覆われていないため、環境温度の影響も受けやすいのです。
臨床での応用と注意点
この研究結果から、臨床現場で活用できるポイントがいくつか見えてきます。
1. 適切な治療設定
犬のアキレス腱を温める場合、連続波3.3 MHz、強度1.5 W/cm²で10分間の治療が、平均腱温度を3.0℃以上上昇させるのに最も効果的でした。この設定により、組織損傷のリスクなく、治療効果が期待できる温度上昇が得られます。
2. 治療時間の最適化
腱温度は治療開始後3分未満で最大に達し、その後約7分間高い温度を維持しました。これは、3分以上の超音波治療が追加的な温度上昇をもたらさない可能性を示唆しています。
ただし、これは「3分以上治療しても意味がない」ということではありません。治療効果を得るためには、組織を一定の温度で維持する時間も重要だからです。
3. ストレッチのタイミングが重要
超音波治療により足関節の屈曲は増加しましたが、その変化は一時的なものでした。したがって、ストレッチ運動は超音波治療中および直後に行うべきです。
この「ストレッチウィンドウ」は非常に短いため、治療計画を立てる際は、超音波治療の直後にすぐストレッチやモビライゼーション(関節を動かす手技)を行えるようスケジュールを組むことが重要です。
4. 個体差への配慮
研究では標準的な体型の犬を使用しましたが、実際の患者では、組織密度、解剖学的位置、周囲構造の特性、血流、治癒過程の段階、体組成など、さまざまな要因が組織の加熱に影響を与えるため、個々の患者における熱効果を予測することは困難です。
つまり、肥満傾向のある犬と痩せ型の犬では、同じ設定でも効果が異なる可能性があります。脂肪層が厚い場合、腱に到達する超音波エネルギーが減少する可能性があるからです。
人間と動物での違い

興味深いことに、人間と犬では組織の温まり方に違いがあります。
人間を対象とした研究では、1.0 W/cm²、3 MHzの超音波を4.5 cm²の範囲に10分間照射した場合、深さ0.8 cmの筋肉で温度が5.8℃上昇し、平均0.6℃/分の上昇率でした。一方、人間の膝蓋腱では4分間の超音波治療で8.3℃の温度上昇があり、平均2.1℃/分の上昇率で、腱の温度上昇率は筋肉の3.45倍速かったのです。
犬の場合、この研究では腱の温度上昇パターンが異なり、最初の数分で急速に上昇した後、比較的安定していました。
このような種間の差異は、それぞれの種に適した治療プロトコルの開発が必要であることを示しています。
今後の研究課題
この研究は重要な第一歩ですが、さらに探求すべき点もあります。
この研究では、形態学的に類似した健康な犬の小集団において、アキレス腱腱のみで加熱パターンを評価しました。他の腱は、脂肪や筋肉による断熱を含む異なる組織特性を持つ可能性があり、超音波エネルギーの吸収と保持を変化させる可能性があります。
例えば、体の奥深くにある腱と、表面近くの腱では、超音波の効果が異なるかもしれません。また、老犬と若い犬、大型犬と小型犬での違いも調べる価値があるでしょう。
さらに、麻酔薬の投与が体温調節機能を変化させる可能性があり、腱にも二次的な影響があるかどうかは不明です。実際の臨床では麻酔をかけずに治療を行うため、覚醒状態での反応を調べることも重要です。
まとめ:臨床での実践的アドバイス
この研究から得られた知見をまとめると、以下のようなポイントが重要です:
- 腱の柔軟性向上には連続波が効果的:連続波3.3 MHz、1.5 W/cm²の設定が最も効果的に腱を温めます。
- 加熱は速く起こる:腱は最初の2〜3分で急速に温まるため、治療時間の配分を考慮しましょう。
- ストレッチは即座に:柔軟性の向上は一時的なので、超音波治療中および直後にストレッチを行うことが重要です。
- 冷却も速い:治療を止めると急速に温度が下がるため、「黄金の5分間」を逃さないようにしましょう。
- 個体差を考慮:患者の体型、年齢、組織の状態に応じて治療計画を調整する必要があります。
超音波療法は、適切に使用すれば、腱や靭帯の柔軟性を改善し、リハビリテーションの効果を高める有用なツールです。ただし、その効果を最大限に引き出すには、組織の特性、加熱パターン、そしてタイミングを理解することが不可欠です。
参考文献
Acevedo, B., Millis, D. L., Levine, D., & Guevara, J. L. (2019). Effect of Therapeutic Ultrasound on Calcaneal Tendon Heating and Extensibility in Dogs. Frontiers in Veterinary Science, 6, 185. https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00185

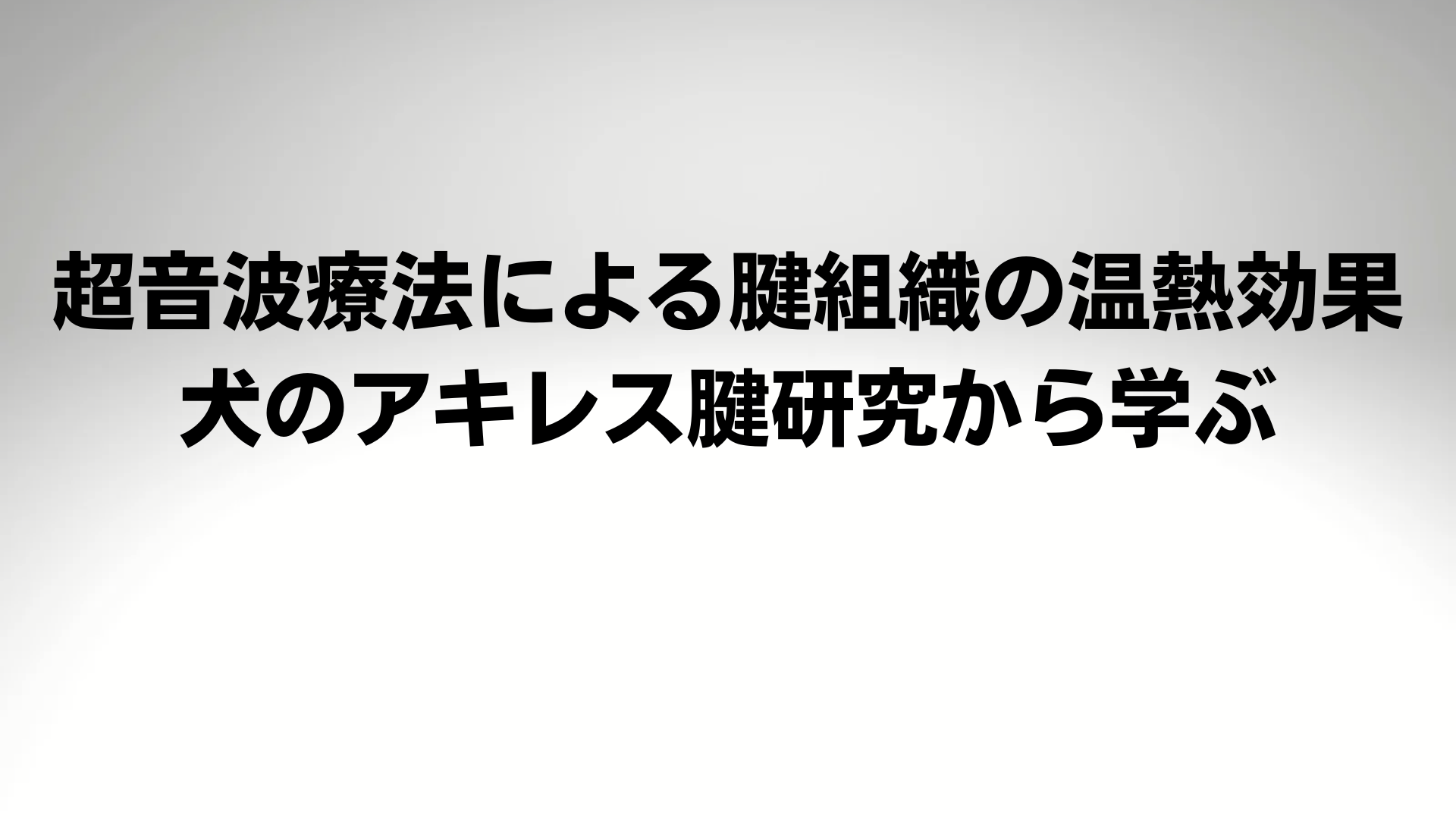
コメント